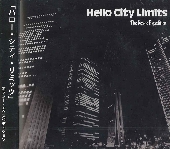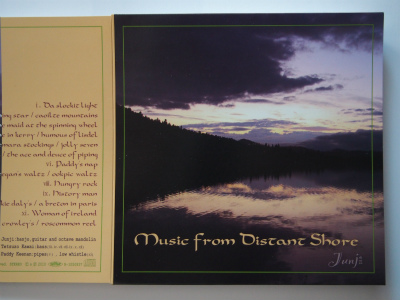本格的にアイルランド音楽を演奏するようになってから20年の月日が流れました。実に多くの演奏家たちと関わり、数千曲にも及ぶ楽曲を演奏してきました。
そろそろ自分の思うことや、経験してきたことなどを書き残していってもいい時期にきたような気がします。
マーティン・ヘイズ、パディ・キーナン、フランキー・ギャビンなど、錚々たる顔ぶれとの知られざる話などもゆくゆくは書いてみたいと思います。次回、先ずはどこからこの音楽に入っていったかを、自己紹介なども含めてスタートしてみます。 続きを読む
「Column」カテゴリーアーカイブ
アイルランド音楽について 2
アイルランド音楽。その魅力的な世界を垣間見たのは、1974~5年頃。
当時、最も愛好していたブルーグラスのレコードをレコード店であさっていたところ、一枚の見なれないジャケットが目に飛び込んできました。 続きを読む
パディ・キーナン
まだアイリッシュパイプなるものがどんなものか知らなかった70年代半ば、初めてボシーバンドのLPレコードを手にした。
アンドリュー・マクナマラ
僕をこの世界に導いてくれた張本人である彼は、生粋のカウンティ・クレア、タラ ボーイだ。 子供のころからマーティン・ヘイズ等と共にタラ・ケイリ・バンドで演奏していた。
ケヴィン・クロフォード
ここらでちょっと一服 ~Birdland Cafe~
美味しいコーヒーでも飲んでみましょうか。
ジョセフィン・マーシュ そして ケヴィン・グラケン
ジョセフィンはクレアのアコーディオン奏者。小さな身体と子供っぽい顔つきで、クレアらしいリラックスした、とても純粋な音を奏でる人だ。
トミー・ピープルス
トミー・ピープルスが西海岸にやって来る。それは本当に久しぶりのことで、この音楽のファンにとっては長い間待ち焦がれていたものだ。

パブのオーナーからの電話で僕がギターを弾くことになった。ふたりだけで、3時間近く演奏しなくてはならない。
スーザン・マッケオン& ジョニー・カニンガム
1999年、2月頃のある朝、いかにも都会の人らしい、とても綺麗な英語で電話がかかってきた。
ティプシー・ハウス
ギターあれこれ(ローデンにしびれるまで)
1963年頃だろうか、64年頃だろうか。ギターというものが日本に於いて、少しずつ人々の間に浸透していった。
5弦バンジョーあれこれ (グレイト・レイクスに溺れるまで)
初めてバンジョーの音を聴いたのは、ブルーグラスをブルーグラスとは知らずに聴いた時よりも、もう少し前になる。
マーティン・ヘイズ
何度も共演したが、いつでも思うことは、やはり人類史上最高のアイリッシュ・フィドラーのひとり、いやヴァイオリン弾きとしてもそう言える人ではないか、ということ。
ノエル・ヒル
写真を持って空港へ。初対面なので、勿論向こうは僕の顔は知らないはずだ。
キャサリン・マカヴォイ&メアリー・マクナマラ
メアリーは言わずと知れたアンドリュー・マクナマラのお姉ちゃん。初めてマクナマラ家を訪れた時、僕のために米を炊いてくれた。それとアイリッシュ・シチュー。シチューは何杯もおかわりした。米は日本人のようにはいかなかったのかもしれない。でも一生懸命考えて用意してくれたことを思うと、世界中にフォロワーがいるこのコンサルティーナ奏者も、いい主婦なんだな、と実感した。
RINKA、トゥレップ楽団、渡辺夫妻、平塚研太郎
氷点下を大幅に下回った3月上旬の札幌。それでも飛行機は予定通り千歳空港に降りたった。
ハリー・ブラッドリー&アシーナ・タルジス
日本のファンにはあまり馴染みのないコンビかもしれないが、それもその筈。彼らがコンビを組んでいたのは‘96年か‘97年頃のほんの短い期間だった。
アシーナはサン・フランシスコ出身のフィドラー。初めて彼女を見たのは、多分彼女がまだ17歳くらいの頃、メンドシーノという北カリフォルニアの小さな町で、ラーク・イン・ザ・モーニングという大民族フェスティバルの最中でのことだった。
若くてとびきり美人のフィドラーである彼女は華麗なる超絶テクニックで他を圧倒していた。
聞くところによると、スコティッシュ スタイルのフィドリングをアラスデァ・フレイシャーに師事したチャンピオンフィドラーらしい。
続きを読む
ジョン・ヒックス
日本のアイリッシュ・ミュージック愛好家たちには殆ど馴染みのない人物だろうが、かなりの腕前を持つギタリスト兼シンガーだ。
ブリーダ・スミス
彼女との出会いはもうかれこれ15年くらい前のことになるだろうか。当時、アンドリュー・マクナマラ&ロハウンズのフィドラーとして、よく西海岸を訪れていた。
2011年 アイルランドの旅 ~エニス その1~
2011年 アイルランドの旅 ~エニス その2~
2011年 アイルランドの旅~エニス その3~
今日は、午後2時にブレンダン・ベグリーと市内でおち合い、そのままケリーまで連れて行ってもらうことになっている。
2011年 アイルランドの旅 ~カウンティ ケリー その1~
ブレンダンは、緑深きケリーの道を軽快にすっ飛ばす。やがて、おそらくケリーで一番の観光地であろう、ディングルに着いた。
2011年 アイルランドの旅~カウンティ ケリー その2~
2011年 アイルランドの旅~カウンティ ケリー その3~
さあ、今日はディングルまで行ってバスキングをしてみよう。最初の日に寄った楽器屋のおやじに、いい場所がないか訊いてみてもいいし。

それに、ブレンダンは日本食にとても興味があるので、有難いことに米や醤油、インスタントの味噌汁までおいてある。
2011年 アイルランドの旅 ~カウンティ ケリー その4,5~
2011年 アイルランドの旅 ~ドゥーラン その1~
この地をアイリッシュ・ミュージックに於ける聖地のひとつに挙げる人は、世界中に数多く存在する。
この小さな町で(というか、村落とでも言えそうなところ)毎夜音楽が演奏されている。それも上質なトラディショナル・アイリッシュ・ミュージックが。
2011年 アイルランドの旅~ドゥーラン その2~
天気は上々だ。晴れ男としての面目は今のところ保たれている。とはいえ、ここは地の果てアルジェリア~…ではなく、アイルランドだ。山の天気のごとく変わりやすいのが常。
風も強く、肌寒いが、今ごろ日本ではみんな溶けているだろう。

遠くにモハーの断崖が見える。高所恐怖症のまれかは近くで見たがらないのでここからでいいだろう。かく言う僕も無類の高所恐怖症である。3度ほど行ったことがあるがいつでもへっぴり腰だった。
2011年 アイルランドの旅 ~フィークル その1~
今日から4日間、カウンティ・クレア フィークルだ。勿論ドゥーランも同じカウンティなので比較的近い。
途中、モハーの断崖を通るが、もの凄い霧と強風で何も見えない。こんな時には絶対に近寄りたくないところだ。くわばら、くわばら。
2011年 アイルランドの旅 ~フィークル その2~
朝食の前に、リビングルームで一緒にここに泊まっている人達としばし歓談をして楽しむ。一人は写真家で、この家に飾ってある数々の音楽家の素晴らしい写真は、彼が撮ったものらしい。
もう一人がイギリスから来ている、僕らが着いた時バンジョーを練習していた、50代前半くらいの人だ。
2011年 アイルランドの旅 ~フィークル その3~
2011年 アイルランドの旅 ~フィークル その4~
朝、リヴィングに行くと、イギリス人のバンジョー弾きが今か今かと待っている。例によって、朝飯前のセッションが始まる。
横で聴いていたカメラマンが言った。「Strayaway Childっていう曲知ってる?」実に懐かしい曲だ。70年代、ボシーバンドでよく聴いていた。もう懐かしすぎてメロディが定かではないが。
2011年 アイルランドの旅 ~フィークル その5~
もう書くこともあまり無い。今日もセッションだ。また、朝早くからバンジョーの音が聴こえてくる。
80年代、ヴァージニア州、ゲイラックスのオールドタイム・フィドラーズ・コンベンションを訪れた時、4日間で1時間程も眠らなかった覚えがある。勿論、若気の至りというか、若かったからできたことである。
続きを読む
2011年 アイルランドの旅 ~ゴールウェイ その1~
クレアから少し北、ゴールウェイに来ている。ここも観光客や学生が多い町だが、音楽はクレアにまけず劣らず、ひたすらに熱い。
まず、フランキー・ギャヴィンと連絡を取る。とても忙しそうだが、時間を作って会いに来てくれるそうだ。
2011年 アイルランドの旅 ~ゴールウェイ その2~
朝からどんよりした、いかにも少し北寄りの、肌寒ささえ感じるアイルランドらしい天気だ。そういえばアンドリューが言っていた。「アイルランドの夏は7月で終わりだ」
随分前は、よく北海道に行っていたが、あそこもこんな感じだった。特に秋の北海道の景色はたまらなく寂しかった記憶がある。
波に浮かんでプーカプカという南国とはぜんぜん違う音楽が生まれて当然だろう。
そういえば昔、ハワイの音楽にも憧れたなぁ。ギャビー・パヒヌイをはじめとするハワイアン・スラック・キーによるギタープレイにも影響を受けた。
パディ・キーナンの書いた“ジョニーズ・チューン”で僕がソロを弾くと、初めてそれを聴いたフランキー・ギャヴィンが「よ!ライ・クーダーじゅんじ!」と叫んだ。さすがに幅広いミュージシャンだ。ちょっとした音で僕がライ・クーダーの大ファンだということを見抜いてしまう。
ロバート・ジョンソン、B・Bキング、ジョニー・ウィンターからビリー・ホリディ、そのうえキング・クリムゾンやペンタングル。想い出せばきりがないくらい様々な音楽に影響を受けた。
そして、アイリッシュへ。
続きを読む
2011年 アイルランドの旅 ~ゴールウェイ その3~
アイリッシュブレックファーストを食べながら、昨日のフランキー・ギャヴィンは凄かった、という話で充分盛り上がることができた。
今日はバスキングに精を出してみよう。この町ならやりがいがあるかもしれない。だがバスキングの場所を探すのもなかなかに難しい。
2011年 アイルランドの旅 ~ゴールウェイ その4~
2011年 アイルランドの旅 ~ゴールウェイ その5~
ゴールウェイ最後の日。ここからはもう日本に帰る日がせまってきている。ダブリンに寄るがあの町にはそんなに魅力を感じていない。
ニュー・ヨークほどエキサイティングな印象もないし、いうなればロス・アンジェルスみたいなものかな。
これも人によって違うから、ただ単に僕にとって、というだけで、本当は知らずして面白いことが沢山あるのかもしれない。
なんか食べよう、と歩いていると、いつも見かける小さな店だが“世界でいちばん美味しいフィッシュ・アンド・チップス”みたいな大それたふれこみのファスト・フード店が、今日は珍しく空いていた。
続きを読む
2011年 アイルランドの旅 ~ダブリン その1~
旅もそろそろ終わりに近付いている。ダブリンからティペラリーにいるパディ・キーナンに電話した。
2日ほど前、車が故障して、今いるところから動けない、と言っていた。もし行けるようになったら、ぜひ君達に会いたいからダブリンに着いたら電話してくれといわれていたからだ。
2011年 アイルランドの旅 ~ダブリン その2~
パディが紹介してくれたパブはスウィニーズという名前だった。かなり広いパブで、セッションは2階でやっているようだ。
恐る恐る2階へ上がってみると、いたいた。若手が4~5人。
ギターを持った男が「あ、じゅんじ。パディから聞いたよ。前に会ったことあるのおぼえてるか?」確かに見覚えのある顔だ。
ジプシー・スウィングからドーグへ
1969年か‘70年頃、昔のことで記憶は曖昧ではあるが(もっと昔のことで、よく覚えている事柄もあるくせに)当時、聴いている音楽の殆どがブルーグラスだった僕の耳に心地よく入ってきた音楽があった。
“ホット・クラブ・オブ・フランス”というバンドはギターのジャンゴ・ラインハルト、そしてヴァイオリンのステファン・グラペリが中心となるご機嫌なスウィングジャズだった。
トニー・マクマホン
ある朝、枕元の電話が鳴った。出てみると、聞きなれたアイリッシュ・アクセントが耳に飛び込んできた。
「わたしはトニー・マクマホンといって、アコーディオン弾きだが、君はじゅんじか?実はカリフォルニアをツアーした後、日本に行くのだが、君が適役だと思って電話したんだ。いろんな人にギタリストは誰がいいか尋ねたら、みんな君の名前を出すんだ。どうだ、やってくれるか?日本での仕事は大使館主催のパーティ。わたしと君と、それからディ・ダナンが来る」
テリー・ビンガム
1999年、アンドリュー・マクナマラと共にカリフォルニアを訪れた彼。大の飛行機嫌いの彼にとっては長過ぎたフライトだったらしい。
這這の体とはああいうことを言うんだろう。まだ身体が震えている、と言ったが、一時間ほどでステージに上がらなくてはいけない。
とりあえずギネスさえ飲めば何事もなかったように回復することだろう。
ジェリー“フィドル”オコーナー
アンドリューの紹介だったが、その昔ちょっとの間“スカイラーク”というバンドで一緒にやっていたことがある、と言う。
とてもひとなつっこい、いいおじさんという感じで、アンドリューと共に日本に来てもらった時も、すしや刺身を盛んにトライしていた。
アンドリューは一切、手を付けなかったどころか、寿司屋でスパゲッティはないのか、と不届き千万なことを言っていた。
高橋 創
もう随分前のことになる。当時、まだ中学生だったひとりの男の子が両親に連れられて、あるいは両親が連れられてきたのか、兎に角アイリッシュスタイルのギターを習いたい、という理由で僕の元を訪れた。
特に音楽教育を受けたわけでもないようだったが、少しの弾ける曲にもセンスを感じたものだ。例えば“Shetland Air”などを隣の部屋で弾いているのを聴くと、CDから流れてくる、僕が録音したものと少しも変わらない。
内藤希花
約3年前の春、アイリッシュスタイルのフィドルを弾く人がいる、という話を、とある方からきき、その方の紹介で初めて会うことになった。
フランキー・ギャビン
アイリッシュ・ミュージックにおけるギタープレイ(DADGAD)
もうご存知の方が殆どと思われますが、僕はダドガドと呼ばれるチューニングを使っています。
DADGAD(6弦から)に調弦するこの方法を産んだのはデイビー・グラハム。
この調弦を僕は1974~5年ころからたまに使っていました。そして、アイリッシュ・ミュージックに本格的に関わり出した頃、ケヴィン・バークとミホー・オドンネルのオハイオ大学でのコンサートビデオを手に入れたことからお話しましょう。
アイリッシュミュージックに於けるギタープレイの真髄
アーティ・マグリン、ダヒ・スプロール、ミホー・オドンネル、ザン・マクロード、マーク・サイモス、ジョン・ヒックス、ジョン・ドイル、シンガーとしても高名なクリスティー・ムーア、ポール・ブレイディー、アンディ・アーヴァイン、ジョン・レンバーン、そして、ドーナル・クランシー…。
名前を挙げればきりなく、影響を受けたギタリストが想い出される。他にも無名ではあるが多くの素晴らしいギタリスト達と共演もした。
そして、その誰しもが素晴らしいトラッドアイリッシュの継承者たちであった。
ミック・モローニ
前回、アイリッシュのギタースタイルについて書いていたとき、突然思い出したことがあった。
10年前、ニューヨーク郊外に住んでいたミック・モロニー宅を訪れた時のことだ。
その日は昼間、コロンビア大学でアイリッシュカルチャーについての講義を担当するミックとともにデモンストレーション演奏の後、
フィラデルフィアの教会で大きなコンサートに出演する予定であった。
ミック・モロニーといえば、あのグリーン・フィールズ・オブ・アメリカの主メンバーで、
シェーマス・イーガンや、アイリーン・アイバースと共に、素晴らしい音楽を聴かせてくれたものだ。
僕は、随分前に(おそらく1995年頃)サンフランシスコのケルティックフェスティバル会場で、ジェイムス・キーンとユージン・オドンネル、
そしてミック・モロニー、というトリオを聴いた。
勿論、シンガーとしての彼も素晴らしかったし、キルケリー アイルランドという歌は涙なくしては聴けなかった。
苦しかった時代の、アイリッシュ・ファミリーの数年の出来事を切々と歌い上げる彼の歌には、いたく感激したものだ。
それと同時に、えも言われぬリズムでテナーバンジョーを弾く彼のスタイルにも感動を覚えた。
彼のインストゥルメンタルアルバムは僕のフェイバリットのひとつで、留守番電話のアナウンスメントにも使っていた。
彼の家はアイリッシュ・ミュージックとカルチャーについての資料館のようなものだった。
ありとあらゆるSP盤、テープ、書籍。日本にいたらまず見ることがないだろうものが山積みになっていた。
僕らが生まれるよりも遥かに前からのものもある。
彼は、それらを次から次へと出してきては見せてくれた。
そして、少しふたりで練習して、大学へと向かった。
大学の講義については、「アイリッシュ・ミュージックにおけるギタープレイの真髄」というコラムで少し書いたが、
英語での質疑応答は大変だった。
でも、大分彼が助けてくれた。
そして、夜には大きな教会でベネフィットのコンサートだ。
300人ほどの、アイルランド移民や2世、3世たちが一堂に集まっている。
数人のフィドラー、パイパー、アコーディオン奏者たちとの演奏は、さながらグリーン・フィールズ・オブ・アメリカを彷彿とさせるものだった。
聴衆も大喜びの様子だ。
そして、彼と二人で弾いた「マイ・ラブ・イズ・イン・アメリカ」
さらに、大好きだった「キルケリー アイルランド」を彼の歌とギターに僕のギターもかぶせて演奏した。
それは、長年の夢のひとつが叶った瞬間の1シーンであった。
パトリシア・ケネリー
日本のアイリッシュ・ミュージック愛好家の間では全く馴染みのない名前だろうが、アメリカ西海岸きってのダンサーだ。
サン・フランシスコにダンス学校を持っていて、多くの生徒さんをかかえている。
僕も、セント・パトリックス・デイなどの大きなお祭りでは必ず、彼女の生徒さんたちのダンスの伴奏をした。
アンドリュー・マクナマラとのほんまもののケイリと、ほんまもののダンス。それが実に見事に決まる。
生徒さんは大人から子供まで、ほとんどが女の子だった。
おもしろいエピソードがある。
車の中にはパトリシアとアンドリューとジェリー・フィドル・オコーナー、そして僕と三人の女子高生。
僕らは今夜のフェスティバル会場に向かっている。
彼女たちが「ねぇ、じゅんじ。アイカップのスペルを言って」僕は迷うことなく「アイ・シー・ユー・ピー」と答えた。
彼女たちはキャッキャ笑う。お分かりかな。(ピーはおしっこのこと)いっぱいくわされたわけだ。
そんな彼女たちも、本番が始まると一流のダンサーとなる。
パトリシアも勿論のこと素晴らしいダンスを披露する。
ここらで本題に入ろう。
パトリシアはアコーディオンを弾く。そして、それは決してテクニカルではないが、アイリッシュ・ミュージックに精通する人々は
口々に”ジョー・クーリーの再来”だと言う。
ジョー・クーリーは一時期、サン・フランシスコに住んでいたが、その頃からパトリシアのプレイは評判だったらしい。
彼亡き後、今、最も忠実に彼のプレイを再現する人はパトリシアだと言われている。
彼女はセッションに現れてもほとんど弾くことがない。
でも、僕は必ず彼女にリクエストしたものだ。「パトリシア。マスター・クローリー弾いて!」
目を閉じて聴いていると、本当にジョー・クーリーが目の前にいるようだ。
パブは一瞬静まり返る。パトリシアが目で合図する。「じゅんじ。ギターを弾いて」
ジョー・クーリーのサウンドは永遠に生き続ける。
スコット・レンフォート&ロビン・ピトリー
時は’93年。サンタ・ローザを拠点に活動していたフィドラーの、スコット・レンフォートとのデュオを始めた。
当時、彼はまだサン・フランシスコの人気バンド「ティプシー・ハウス」に参加しており、ちょうど次期フィドラーのポール・チェィフィーと交代する頃だった。
ケビン・バークをこよなく敬愛するスタイルを持った彼のフィドリングは、ミホー・オドンネルとケビン・バークの演奏に心酔していた頃の僕にとって、あこがれだった。
サイモン・ラトル
僕が語るのもおこがましいのですが、とても仲のいい超大物中の超大物です。クラシック音楽に興味のない方には馴染みのない名前かもしれませんが、現ベルリンフィルの首席指揮者で、芸術監督でもある人物です。
今までのコラムでも数回彼の名前は出しましたが、あらためて少しだけ書いておきます。
もう20年近く前のことになりますが、ひょんなことで2人の男の子を連れたもじゃもじゃ頭の男と友達になりました。
何故、彼がサイモン・ラトルという有名な指揮者であることを知ったかというと、多くの人が「昨夜のシンフォニーは素晴らしかった」と彼に声をかけていたからです。
そこで、音楽の話になり、僕の家にも遊びに来るようになりました。勿論、僕も彼の家に遊びに行ったりしていました。
2人の子供のベビーシッターをしたこともありました。
長男は少しコロンとしたサーシャ。当時で8歳か7歳くらいでした。次男は4歳くらいだったかな。エリオットという名前でした。
サーシャは既にピアノを弾いていたので、僕のギターと合わせ、そこに、幼少の頃はドラマーになりたかったというサイモンが打楽器で参加する、といったYouTubeにでものせたら大変な騒ぎになるだろう場面もありました。エリオットはお昼寝。
サイモンの仲のいい友達の中には、ボーイズ・オブ・ザ・ロックのアリ・ベインがいます。アイリッシュなんか音楽ではない、と言った”私こそ日本のクラシック音楽の発展を担う人物だ”とでも言いたげな、大阪の某クラシック専門楽器店のおやじと違い、とても幅の広い視野を持っています。
そんなサイモンも徐々に世界中に名が知れ渡る指揮者となり、あまり会うことができなくなりました。
2011年、サイモンがベルリン・フィルの指揮者として来日する、という話を希花から聞きました。彼女の母上もオーケストラでヴァイオリンを弾いている人。そういう人たちが知らないわけがありません。何としてでも行きたいから一緒に行きましょう、と誘われましたが、チケットは驚きの4万円。
もったいないからいい、と断っていましたが、発売当日、希花が電話の前で待機。いざかけてみるとなかなかつながらない。やっとつながったと思ったら、な、なんと、発売から2分で売り切れた、ということでした。正直、胸をなでおろしました。
当日、サントリーホールは日本公演最終日でした。希花が「もしかしたら会えるかもしれないから行こうよ」と言いますが、僕はそんな超大物だし、日本ではなかなかガードも固いだろうし、また別な機会でいいよ、と断りました。
しかしそこはさすがに、2浪してまでも行きたかった医学部にくいさがる人です。公演終了時間に合わせて連れて行かれてしまいました。
公演も終わり、多くのクラシックファンが会場から出てきました。僕は係の人にサイモンと会えるかどうか、事情を説明して交渉してみました。
やはりそれは無理だったので、もう帰ろう、というと、希花がオーケストラのメンバーらしき人たちに尋ねています。それでも「グッド・ラック」という返事しか得られませんでした。
まだ、たむろしていた数人の団員らしきひとたちの横を通り過ぎ、帰ろうとすると、ひとりの若者と目が合いました。どこからみても、ヨーロッパ人ではなく、アメリカ人という風情でした。僕は何気なしに「オーケストラのメンバー?」と訊くと彼が驚きの一言を発しました。
「ううん。僕はサイモン・ラトルの息子だ」ほんとうにびっくりしました。
「サーシャ?」「いや、僕はエリオットだ」なんという神様からの救いでしょうか。
「エリオット?僕だよジュンジだよ」キョトンとしていた彼が「ジュンジ!!」と叫ぶまでは、ほんの2~3秒しか掛からなかったのです。
当時、僕の腰くらいまでしかなかった彼も、もう180cmに近いくらいの大きさになっていました。約18年ぶりの再会です。通り過ぎてしまったら分かるわけがありません。
「これからパーティに行くんだ。親父もびっくりするだろうから一緒に行こうよ」僕は今一緒に音楽をやっている人だ、と希花を紹介して、エリオットの後について行きました。
20年ほど前は僕の後にエリオットが付いてきたものですが…。
会場に入るとタキシードとドレスに身を包んだ老若男女がシャンペンやワインを片手に談笑しています。焼酎など飲む人はいないようだ。
少しはましな格好をしてきたつもりでしたが、かなり場違いかな、と思わざるを得ませんでした。でもエリオットはジーンズにチェックのシャツ。そんな彼をアメリカ人と思ったからこそ声を掛けてみたのです。彼と一緒にいたらだれも文句はいわないでしょう。
しばらくすると、疲れきった表情のサイモンが多くの人に囲まれてやってきました。記者会見が終わったようです。
すかさずエリオットが「親父、ジュンジだよ」と紹介するとしばらく事情が呑み込めなかったらしく、息子と同じようにキョトンとしていましたが、周りの関係者も多いことだったので
静かに納得して2言、3言、言葉を交わすと、エリオットが紹介した希花とちゃっかりツーショットに収まってくれました。
あまり多くの人に囲まれて忙しそうなので、エリオットに「僕らはこれで失礼する」と伝え、アドレスや電話番号を交換して会場を出ました。
駅に向かいながら希花が言いました。「クラシックをやっていたらまず会うことなんか叶わなかった人に、アイリッシュをやっていて会えるなんてこんな不思議なことが世の中にあるんだ」
入ってきた電車に乗り込もうとした時、僕の携帯にメッセージが入っていることに気がつきました。聞いてみると、サイモンからです。「ジュンジ。帰ってしまったのか。後でゆっくり話をしたいと思っていたんだ。今どこにいる?」あれ、気がつかなかった、と思っていたところにまた電話が鳴りました。
「サイモン」「ジュンジ。話がしたい。戻って来れるか?」「うん、待っててくれ。15分位で戻る」このときの最初のメッセージは今も大事に残してあります。
会場に戻るとサイモン自ら出迎えてくれました。そこからはサイモン、エリオット、僕、そして希花と4人で1時間ほどワインを飲みながらゆっくり話をすることができました。
そして再会を誓うと、僕らは終電に間に合うように会場を後にしました。
僕が「良かった会えて。サイモンと友達なんて、でまかせだと思われてたかもしれないし」と言うと
希花が胸を張って言いました。「あたしの粘り強さと、じゅんじさんの運かな」
希花が興奮して実家に戻ると、母上が地団駄踏んでいたらしい…。
アイリッシュ・ギター
かねてから僕は、アイリッシュ・ギターなどという分野は存在しないのではないか、ということを言ってきた。
何故そう思うのかが、自分でもようやく分かりかけてきた。これは決して通常で言う”正しい意見”などというものではない。あくまで僕個人の見解なのだが。
音楽は結局のところ、好きか嫌いかでしかない。自分の見解がどこでもまかり通るはずはないのだから。
さて、いろいろ見てみると、アイリッシュ・ギターあるいはケルティック・ギターと言われているもののほとんどが、ロンドンデリー・エアーないし、サリー・ガーデン、ウォーター・イズ・ワイド、シーベッグ・シーモアといったスローエアーやバラッドを素材にしている。
そしてそれらを演奏する人たちはリールやジグ、ホーンパイプ、スライド、ポルカなど、いわゆるダンスのための伴奏などをしたことがないひとがほとんどだ。
だが、何故か彼らは”アイリッシュ・ギタリスト””ケルティック・ギタリスト”として名を連ねている。
彼らは一様に、実に素晴らしいテクニックを持った、フィンガー・ピッキング・ギタリストだ。オキャロランの曲や、美しいメロディを持った古くからのアイリッシュ、スコティッシュの曲は彼らにとっては、いわゆる”おいしいところ”なのだろう。
では、彼らに果たしてダンス曲の伴奏が出来るかどうか、と言う点においては微妙であるし、今まで見てきた無理な例というものも知っている。
アイリッシュ・ミュージックの伴奏におけるギターについては、よくこんなことを言う人がいた。「ウォッシュボード・ギターだ」どういうことか分かると思うが、いわゆるリズムだけを延々と奏でる(勿論スローな曲ではアルペジオやフィンガーを使うが)そういう人たちのことだ。
伴奏ではリズム感さえある程度あれば(今時の若い人たちはいいリズム感覚を持っていると思う)なんとかサマにはなる。
おそらく、フィンガーピッキングによる演奏ではかなりのテクニックが必要ではあるが、タブ譜なり、教室などである程度習うことが出来るだろう。しかし細かいテクニックはさほど要求されない伴奏のほうは何故かそういうわけにはいかない。
ある程度基本的なテクニックは、見たり聴いたりで習得することができるだろうが、メロディは自分で覚えなくてはいけないし、それを体の奥底まで入れなくてはいけないのだ。その上に各楽曲に最良の音使いを自ら選び出す。100曲なら100通り。500曲なら500通り。適当にやっていると先に言った「ウォッシュボード・ギター」になってしまう。
スローエアーやバラッドを演奏するギタリストのほとんどに僕が抵抗を感じているのは、たかだか50曲程度のスローエアーやバラッドをレパートリーに取り入れていることで、アイリッシュ・ギタリストという枠の中に名を連ねることだ。いや、彼らにとっては様々な音楽を追求するなかで出会った美しい音楽のひとつなのだろうから、彼らをひとくくりにしてアイリッシュ・ギタリストと呼んでしまうこの国の音楽事情が関係しているところなのだろう。くどいようだが、彼らは飽くなき探求心を持った素晴らしい音楽家たちなのだ。
しかし、ここまでくると頑固な年寄りのたわごと、と思われてしまうかもしれない。
そこで、僕が今まで関わりを持った、あるいは参考にしたギタリストの特徴などを書いておくので、これからアイリッシュ・ミュージックのギターを真剣に取り組んでみよう、と思っている方々にも参考にしていただけたら、と思う。
★Arty MacGlynn 「Lead the Knave」というアルバムではエレクトリック・ギターを駆使した、俗に言われる”サーフ・ギター・サウンド”(カリフォルニアだけかもしれないけど)で度肝を抜いた。ソロから伴奏まで、素晴らしく参考になること間違いなし。
★Michael O’Domhnaill Bothy Band やKevin Burkeとのデュオで知られる今は亡き珠玉のシンガー兼ギタリスト。特にトラッドのフィドルプレイに対して、ギターはどうあるべきかを探り出すには最良の手掛かりとなる。
★John Doyle Solasのギタリストであった時代から、おそらく日本では一番追従者が多い人であろう。抜群のリズム感覚とフラット・ピッキングでのリード、フィンガー・スタイル、そして歌、どこをとっても若い人なら確実にノックアウトされてしまうはずだ。
★Donough Hennessy Lunasaのギタリストであった時代から上記のJohn Doyleと同じくらい人気は高かったが、珍しくベースの入ったバンドでこちらはどうしてもTrever Huchinsonのベースとの連携プレイから作り出されるサウンドが頭に残り、一人ではなかなかフォローできないものかもしれない。
★Jon Hicks 恐るべきハイ・テクニックのフラット・ピッカーであり、シンガーでもある。今年の始め、タイまでよく遊びにきているから呼んでくれたら日本まで行くぞ、とメールが入った。もし、日本のアイリッシュ、特にギタリストを目指す人たちが見たら、あまりに自由奔放なスタイルとトラッドを熟知したスタイルに圧倒されるだろう。
★Steve Boughman 日本の人たちには馴染みはないかもしれないが、中国語ぺらぺらの弁護士であり、優秀な伴奏者であり、高度なテクニックを誇るフィンガー・ピッカーだ。アンドリュー・マクナマラが初めて彼をセッションで見た時「ジュンジ、ファッキン・ジョン・デンバーがいる」と、けたけた笑いながらアコーディオンを弾いていた。確かに見かけは似ている。おっと、また脱線してしまった。
★Randal Bayes フィドラーでもある彼は、クラシックギターからのアイデアを駆使した美しい伴奏を聴かせてくれる。そしてソロによるエアーなどでも美しすぎるほどのサウンドを聴かせてくれる。
★Dennis Cahill 彼のギタースタイルについてはMartin Hayesありき、というところでしか語れない部分もあるが、マーティンとやり始めた時から彼を見てきた僕にとって、あれだけタイトな伴奏をするようになるとは、正直驚いた。相当きっちりトラッドを勉強した上、自らのスタイルとマーティンの音の好みを究極まで突き詰めることで、そのすべてを把握できる伴奏者になったのではないかと思わざるを得ない。
★Daithi Sproule 彼のプレイに初めて接したのはLiz Carroll のアルバムからだ。その他Paddy O’BrienとJames Kelly とのトリオ、そしてAltanへとつながった。派手ではないが、素晴らしい伴奏者でシンガーだ。
他にも思い出せばきりがないかもしれないが、彼らの殆どは素晴らしいフィンガー・ピッカーであり、素晴らしいトラッド伴奏者である。その両方があって、初めて”アイリッシュ・ギタリスト””ケルティック・ギタリスト”といえるのだろう。
それでも、アイリッシュ・ギターという呼びかたには抵抗を感じている。
2012年アイルランドの旅 ~ダブリン~
7月9日、気温16度、曇り。ダブリンに着いた。今回はスムーズに荷物が出てきた。コぺンハーゲン乗換えという、過去に経験のないルートを使ったため、心配はひとしおだったが、ギターのケースに大きく書いた“ダブリン、アイルランド”という紙を貼っておいたのが利いたのかも知れない。それでも違うところに行くようだったら、この辺の空港職員は日本の政治家並みだ。
なにはともあれ、今日は偶然にもダブリン市内で、クリスティー・ムーアのコンサートがあり、ゲストにマーチン・オコーナーバンドが出る、ということだ。
フィドルとバンジョーにカハル・ヘイデン、ギターはシェイミー・オダウドだ。シェイミーとは彼がダーヴィッシュにいたころから仲が良かった。 続きを読む
2012年アイルランドの旅 ~7月11日 ミルタウンマルベイ~
ダブリンからリムリック/エニス経由で目的地へ。ブレンダンの末娘であるクリーナがモロニーズというパブで待ってくれている、ということだ。沢山の人で埋め尽くされた店の中に入るとまず、12~3人のセッションのかたまりの中に高橋創君の友人、リアムが巨体をゆらしてコンサルティーナを操っているのが見えた。チラッとこちらを見て首を一瞬斜めに倒す。アイルランド人独特の挨拶だ。こちらも同じようにして、挨拶を済まし、さらに奥へと進む。すると、パティオのようになった場所に7~8人のティーンエイジャーのセッションを見つけた。小学生くらいの男の子がアコーディオンを弾いているその隣にクリーナを発見。めでたく再会を果たし、一緒にいたシェーマス・ベグリーの娘のミーブとともにベグリー家に向かった。
街の中心部から車で5分ほどのところにベグリー家がある。途中、牛が並んでこちらを見ていたり、 犬が飛び出してきて一緒に走ったり、アイルランドの田舎のどことも変わらない景色を通り過ぎて、広い広いベグリー家に到着。ブレンダンはまだ来ていない。とりあえず荷物を置いて再び街の中心部、セッションで盛り上がっているところに出かけるが、どこもかしこも人、人、人で都心並みだ。 続きを読む
犬が飛び出してきて一緒に走ったり、アイルランドの田舎のどことも変わらない景色を通り過ぎて、広い広いベグリー家に到着。ブレンダンはまだ来ていない。とりあえず荷物を置いて再び街の中心部、セッションで盛り上がっているところに出かけるが、どこもかしこも人、人、人で都心並みだ。 続きを読む
2012年アイルランドの旅 ~7月12日 ミルタウンマルベイ~
今日もどんよりとして寒く、時折激しい雨が降ってはサッと止む。
朝、キッチンに行くとブレンダンがコーヒーを淹れていた。再会を祝し、コーヒーとポリッジでしばし歓談。今日は午前中アコーディオンのクラスがあるので、午後ちょっと先のベルブリッジホテルというところのロビーで待ち合わせることにした。
2012年アイルランドの旅 ~7月13日 ミルタウンマルベイ~
今日は午後からブレンダンとラジオに出演して演奏することが決まっている。さらに、予てから連絡を取り合っていたジョン・ヒックスともどこかで会えるだろう。そして夜はジョセフィンと一緒。予定が山盛りだ。
ラジオはすべてがゲール語で進行している。僕と希花は何もわからず、ただすわってにこにこしているだけ。ブレンダンが曲目を言ってカウントを取って、Ukepick Waitzをまず演奏し、そしてまたにこにこして、Master Crowleysを演奏して15分の出演が無事終了した。
ブレンダンと別れてまた、ぶらぶらしているとカハル・マコーネルに出会った。少し立ち話をして別れると、通りをにこにこして一目散に渡ってくる奴がいる。その風貌を見て希花が「あっ、ジョン・ヒックス」と叫んだ。
実に17~8年ぶりだ。少しも変わっていない。どこかでやろう、と一緒に引き連れてきた仲間を一通り紹介してくれた。僕のほうも、いつも一緒にやっていて、どれだけ君の事を話しているか…といって希花を紹介。そして場所探しにあるきまわり、あるパブの裏手にあるパティオに落ち着いた。さすがに鼻が利く。
久しぶりに彼の凄まじいテクニックと、えもいわれぬタイミングでぐいぐい押してくる独特のギタープレイに酔った。
しかし、他の音にじっと目をつぶって、真剣に耳を傾ける姿はさすがに一流のプレイヤーである。自分の音だけを押し出してくるわけではない。日本のアイリッシュミュージックファン達が彼のプレイを生で聴いたことがない、というのは不幸だ。いつか是非日本の地を踏ませたいものだ。
4時間ほど彼と一緒に過ごした後、ジョセフィンとの待ち合わせの場所に行った。そして途中少し彼女の家に寄り、相方のミック・キンセラをピックアップして一路キルラッシュへ。すぐ近くよ、と言っていたが軽く一時間ほどすっ飛ばして目的地であるパブに着いた。
地元のフィドラーが3人ほど加わった一番いいパターンの落ち着いたセッションだ。ミックはコンサルティーナを弾きながら、ボブ・ディランのようにホルダーにセットしたハーモニカを吹いて歌を歌ったりする。
それにジョセフィンのアコーディオンが絡む極上の音楽を楽しんでいると、よく知っている顔が入ってきた。もちろん体も一緒だ。そしてその体全身で驚きを示した。こちらに長いこと住んでいるコンサルティーナのウノヒロコさんだ。
コンサルティーナという楽器に惚れて、アイルランドの音楽をこよなく愛し、とうとうアイルランドに来てしまったという、いつもにこやかでパワフルな人だ。
まさか僕らがここに居るとは思わなかったらしい。いい感じのテリー・ビンガム譲りのプレイを聴かせてくれた。
1時をまわったころブレンダンの家に戻ると、15~6人の若者たちが騒いでいた。みんなミュージシャンだ。ほとんどがブレンダンの娘やシェーマスの子供たちの友人や、そのまた友人達。困ったことにケリーから来ているらしい。ケリーの人間は疲れ知らずで朝までどんちゃん騒ぎをする。結局、寝る態勢にはいったのもつかの間、4時ころから一大ポルカ大会に何故か加わっていた。
2012年アイルランドの旅 ~7月14日 ミルタウンマルベイ~
曇っているが時々太陽が顔をのぞかせる。
前の晩からの大騒ぎで少々寝不足気味。ここでケリーの人たちと過ごすのだったら覚悟が必要だ。
今日は前日に会ったウノさんと、大阪の上沼君とでセッションに出かけてみよう、と相談がまとまっていた。
そして、どこに行こうかと話をしているところにジョセフィンから電話が入った。もし暇だったらヒラリーズというパブに行くから是非来てほしい、という。
ジョセフィン・マーシュは以前コラムでも書いたが、実にセンスのいい滑らかな音と抜群のリズム感覚と鋭いコード感覚を持ち合わせたプレイヤーだ。そして小柄でかわいくて、とてもいい人だ。みんなから好かれている。
そんなジョセフィンから再三誘われるということはとても光栄だ。ぼくはみんなを引き連れて一目散にヒラリーズに向かった。
ウノさん、上沼君、そして希花と僕がジョセフィンを囲んで後から数人の人たちが集まってセッションをしていると、またしても見た顔が驚いている。僕も非常に驚いた。その昔、サンフランシスコのプラウ・アンド・スターズのセッションによく来ていた牧師さんであり、フルート吹きのジョン・グリフィンだ。
ミュージシャンとしての付き合いではなく、それでもセッションではよくお話したものだが、そういえば97~8年ころからあまり見かけなくなり、誰かが彼はアイルランドに戻ったよ、と言っていた。
じつに彼ともそれ以来だが、全然変わっていないのには驚いた。めちゃくちゃにいい人だ。沢山のひとが見ている中、日本人4人がジョセフィンを囲んでいる様は他のパブとは異質に見えたのかもしれない。ジョンもそんな光景にふと、足を止めてみたら僕が居た、というところだろう。
嬉しい再会が沢山あったミルタウン・マルベイとも今日一日でお別れ。明日はエニスに向かうのだが、また帰ったらケリーの人たちが大騒ぎすることだろう。
だがそれは、予想をはるかに超える凄まじいものだった。
2時ころからポルカが始まり、数人が雑魚寝していたちょうど僕の枕元で、あれは4時ころだと記憶しているが、激しいステップを踏んでしばらくして出て行った奴がいた。あとで、あれはブレンダンの息子で、コンサルティーナの名手、コーマックだ、と言った人がいたが、彼のキャラではない。絶対にシェーマス・ベグリーの息子の、これまたコンサルティーナの名手、オーインにまちがいない。彼だったらやりかねない。
なにはともあれ、音楽はいくら酔っ払っていても大したものなのだ。ひとりの若者が僕の足元で携帯を握り締めて、そんな大騒ぎの中でいびきをかいている。それをみてもやっぱり白人はタフだな、と思ってしまう。
踊るアホウに寝るアホウだ。
朝方、ほとんど寝ていないはずのコーマックがコンサルティーナを練習していた。何度も何度も同じフレーズを続けていた。その真剣な姿はさすがに27歳という若さでありながら、この楽器のマイスターの一人として名を連ねているだけはあるな、と思わざるを得ない。同時に悪乗りして枕元でダンスをするようなキャラにもみえない。
ミルタウン・マルベイで最後に見た素晴らしい光景はコーマック・ベグリーの真剣な眼差しだった。
2012年アイルランドの旅 ~7月15日 エニス~
7月15日 曇り。
ウノさんと上沼君と希花でエニスへ。上沼君はそのままゴールウェイに向かった。ジョニー・リンゴ・マクドナウにボウランの手ほどきを受ける約束があるらしい。僕らもゴールウェイに行く予定があるので、リンゴとは会うだろうし、日本に帰ったらまた、上沼君とも会えるだろう。
そして、今後はイギリスに住むことになるだろうウノさんとも、どこかでまた会うことができたら嬉しい。
みんなと別れて宿泊先に向かった。今夜はジョセフィンがブローガンズというパブでのセッションに誘ってくれている。
9pm,この人は珍しくほぼ時間通りにセッションを始める。さぁ、始めようとしたときギターをかついだ女性が入ってきて「ジュンジ、久しぶり。ニーヴよ」とおおきなハグをした。「ニーヴ・パーソンズ?」エドモントン・フォーク・フェスティバル以来だ。10年ぶりになるだろうか。
そしてその日、彼女はいっぱい歌を唄ってくれた。パブでは演奏の時には少々うるさくても仕方ないが、歌の時には静かにすることを要求されるし、またそれが礼儀でもある。
グラスを叩いたり、シーッとみんなで言ったりする。それでも気がつかず、あるいはおかまいなしにしゃべっているひとがいることもあるが、その時のニーヴはさすがだった。こう言ったのだ
「大丈夫よ。あたしが歌いだしたらみんな静かになるから」そして、アンディ・M・スチュアートの名曲“Where Are You Tonight”を唄いだした。凄い。一瞬にして騒々しかったパブを別世界にひきずり込んでしまったのだ。
「ジュンジ、一緒にギターを弾いて」と目で合図する。僕も大好きな曲だし、ディアンタというグループのメアリー・ディロンのレコーディングを希花に聴かせてからは彼女のフェイヴァリットソングでもあった。
僕とニーヴの間にはさまれた希花にとっても極上の瞬間だっただろう。
そして、またジョセフィンとミックとのチューンに入る。この日たまたま居合わせたお客さんにも素晴らしいひと時となっただろう。
普段ニーヴがひとりでフラッとパブに現れるなどあり得ない、ということなので、ジョセフィンが僕のために仕組んだサプライズだったのだろう。
感謝、感謝の一日だった。
2012年アイルランドの旅 ~7月16日 エニス~
7月16日 朝からほとんど雨。
朝食を食べていたら、ラジオから聴いたような演奏が流れてきた。どう聴いても僕のギタースタイル以外の何ものでもない
よくよく聴いてみると、先日ミルタウン・マルベイでラジオ出演したときのものが再放送されている。
同じところに泊まり、朝食を共に楽しんでいた人たちにも「これ、僕たち」と思いっきり自慢した。
午後からカスティーズ(楽器屋さん)に出かける。
いろいろと物色していると、希花がコンサルティーナを見つけた。ラチナルというメーカーのセコンドハンドだがソフトでとてもいい音がする。少し触ってみると、かねてから持ち合わせていたコンサルティーナ熱に火がついた。決して安いものではない。それに本当に欲しいタイプのものでもない。が、しかし本当に欲しいものは今目の前にあるものの倍ほどの値段で、しかもオーダーしてから手元に届くまで、最低でも4年はかかる。
いろいろ考えていると、オーナーの一人であるジョンが「2週間持っていたらいい。いろんな人に相談するなりして、それから決めればいい」と、なんと貸してくれるという。
2012年アイルランドの旅 ~7月17日 エニス~
7月17日 晴れ。珍しく汗ばむくらいの陽気だ。
今日は古い友人のサラ・コリーの家に泊めてもらうことになっている。それがどこなのか分からないが、エニスからそう遠くないところらしい。
夜9時に待ち合わせしているので、かなり時間がある。
去年、トミー・ピープルスに声をかけられたあの場所でバスキングでもして時間をつぶそう、ということになり、始めていると、よっぱらったおじさんが3人現れた。ふたりは楽器を持っている。アコーディオンとフィドルだ。
横に座ってしばらく聴いていると「入っていいか?」と言う。そして矢庭に弾き出すとこれまた単なる酔っ払いのレベルではない。
とことん力強くどぎついリズムでガンガン迫ってくる。フィドルのおじさんは鼻のあたまを真っ赤にして、農作業のあとの楽しみは酒と音楽だ!という、まさに生活に根付いた音を奏でる。いかにも、子供のころ納屋にころがっていたひいおじいちゃんのフィドルを触ってみたら面白かったので、そのままフィドラーになり、フィドルもそのまま使っている、とい感じだ。ただものすごく酔っ払っているので同じ曲を何度もやる。
アコーディオンのおじさんも眠っていたかと思うと、突然さっきやった曲を弾き始める。1時間ほど一緒にやると「これからすぐそこのパブでやるからかならず来いよ」と言い残してもう一人の友人かマネージャーみたいな人とフラフラ帰っていった。
完全に生活に根付いた音楽を目の当たりにして、さあ、あの酔っ払いたち覚えているだろうか、とパブをのぞくと、いたいた。テーブルには山のようなギネス、ウイスキーが見える。
「おっ!来た来た。なんか飲むか」と言ったかと思ったら、さっき何度もやったリールを弾き出して、早く楽器を出せ、と催促する。
結局、また2時間ほどつかまってこっちも酔っ払いとなったのだが、フィドラーはトニーという名前で、年のころは70半ばくらい。
希花に一生懸命なにか言っていたが、どうも結婚式のギグがあるから一緒に演奏できるか、ということだが、もしかしたら結婚しようといわれたのかもしれない。なんだか電話番号をよこしたが、いかにせん、コネマラというゲール語地域から出てきた半端でない酔っ払いのおじいさん、近くにいたアメリカ人ですらなにを言っているかよく分からないそうだ。
アコーディオンは、どうも“ジョン・キング”という、名のある人らしい。あとで色んな人に話して分かったことだが、とにかくよく飲む、それはアイルランド人ですら驚くくらいよく飲むベテランミュージシャンらしい。
後で会ったテリー・ビンガムが言っていた。「昼からかなり飲んで演奏しているのを見かけたけど、夜中に見に行ったらまだ飲んでいて、次の日の朝まだ飲んで演奏していて、夜、見たらまだ飲んでいて、次の朝まだ飲んで演奏していた。ウオッカのビンとウイスキーがいたるところに散乱していた。ありゃ只者ではない。一緒にいたフィドラーはトニーだろ。あのふたりの体の中身は全部酒だ」
サラと会うのはもう20年ぶりくらいだろう。アメリカ西海岸のバークレイ出身サラは、フィドラーだ。弟のデイブがバンジョーを弾くが、まだ彼らが10代のころから良く知っている。因みに今のご主人であるダミアンはフルート吹きだ。
家はエニスから車で20分ほどのところ、緑に囲まれた雄大な景色が広がる。
ここで2日とめてもらってから“ジェリー・フィドル・オコーナー”が来ているリムリックに行くことになっている。
ここがキッチンでここがシャワーよ、といろいろ説明してもらっているとき、希花がシャワー室にナメちゃんがいる、と叫んだ。
見るとナメクジが2匹ほど張り付いている。よっぽどびびったのか、今日一日だけにして何とか明日中にジェリーに連絡をとってリムリックに行くことにしたいと、懇願する。
ちょうど、サラが午後からリムリックに行くことにもなっているし、それはナメクジに感謝かもしれない。
しかしこれだから温室育ちは困ったものだ。
かくして希花はナメクジの恐怖におびえながらベッドに入った。僕はサラと昔話に花を咲かせてから眠りについた。
2012年アイルランドの旅 ~7月18日 エニス~
7月18日 曇ったり降ったり…晴れたり。
サラと食事をして、庭に飼っているウサギたちを見に行く。12~3匹のウサギがまーるくなっていてとても可愛い。
そして、近くの史跡のような、しかし誰もいない処に散歩にいったら、牛と馬が会話していた。成り立っていたのだろうか。とにかくそんな風にみえた。
自分が生涯住めるとは思わないが、こういうところに身をおくというのは僕らのやっている音楽にとっても有意義なことだ。僕はナメクジの2匹や3匹、どうもないし…。
リムリックに到着すると早速ジェリーから電話が入り、9時ころにミュージシャン達が宿泊しているところに来い、という。
今、リムリックでは“メヘル”というトラッド音楽のいわゆるスパルタ合宿のようなものが行われていて、ジェリーをはじめ、名のあるミュージシャンが教師として集結している。
そして、アパートの一室で、フルートのアラン・ドハティ、コンサルティーナのエデル・フォックス、フィドルのゾーイ・コンウェイなどとみんなでセッション。 エデルはほとんど喋ってばかりだが、弾き始めるとやたらと上手い。当たり前のことだが。とにかくこういう人たちとパブでのセッションではなく、個人的に会えることは希花にとっても貴重な体験になるはずだ。
エデルはほとんど喋ってばかりだが、弾き始めるとやたらと上手い。当たり前のことだが。とにかくこういう人たちとパブでのセッションではなく、個人的に会えることは希花にとっても貴重な体験になるはずだ。
2012年アイルランドの旅 ~7月19、20日 リムリック~
7月19日 曇り。相変わらず上着が必要なくらい涼しい。
お昼はゆっくりして、夜、ドーランズというパブに出かけてみる。地元の人が薦めてくれた、“音楽だったらここだ”という処。
中に入ると、華麗にアコーディオンを操る若者とフィドラーの女の子がいた。早速自己紹介して座ると、ジェリーからメールだ。「ドーランズというところに行くから来い」すかさず「今来ている」と文章を作った矢先、ジェリー様一行がエデル・フォックスの大きな話し声と共に入ってきた。
それから先は特筆すべきこともない。いつにも増して、ジェリーのフィドルがうねり、エデルの声とコンサルティーナが響き渡りる中、夜も更けていく。
しかし、みんな朝からかなりのスケジュールをこなし、教えられるほうだけでなく、教える側も疲れているだろうに、やはり強靭な体力と、これが生活、人生、その全てなんだろうな、と思わざるを得ない。
7月20日 くもり時々晴れ
今日はメヘルの最終日に行われるコンサートにジェリーが招待してくれた。会場では楽器を持った子供たちがいたるところで練習している。
ここで学ぼうとする子供たちはもうかなりの凄腕だが、いつになっても基礎というものを忘れることがない。だからこそ、こうして強化合宿に参加して、他のプレイヤーの演奏も聴き、普段会うことの出来ない伝説的な教師たちの指導を受けることがいかに大切か、ということも分かっているのだろう。
恐るべきガキ共だ。
この日、教師のひとりであるフィドラーのマナス・マクガイヤーを見た(聴いた)。ムーヴィング・クラウド以来の好きなフィドラーだ。
ジェリー・オコーナー、ちょっと体をこわし、大変だったらしいけどいつまでも元気でいいおじさんぶりを発揮して欲しい。
貴重な体験をありがとう。
2012年アイルランドの旅 ~7月21,22日エニス~
7月21日 めずらしくよく晴れている。
リムリックを発ってエニスへ。
バスにフィドルを持った東洋人の女性が乗ってきた。日本人でないことは明らかだが、どこの国の人だろう。むかし、アメリカに住んでいる日本人のフィドラーが言っていた。「僕ら、よく中国人に間違われますけど、中国人は自分の国の文化に誇りを持っているから、他の国の音楽なんかやらないですよ」もしかしたら一理あるかもしれない。
同じところで降りたので声をかけてみた。
タイ人でニュージーランドに住んでいるらしい。そして友人がやっているアイリッシュにはまった、ビギナーフィドラーだ。
宿泊するところが同じなので一緒に歩いた。僕らは着いたらすぐにカスティーズ向かった。やっぱりあまり長い間コンサルティーナを借りているのは心配なのでとりあえず返すことにしたからだ。
店に行くと、貸してくれたジョンはおらず、イタリア人のパウロというアコーディオン弾きが店番をしていた。
そこで、事情を話し、それでもまだ考えているから、誰か他に欲しいという人が現れたら必ず連絡をくれるように念を押しておいた。ジョンにも話しておいてくれる、ということで、しばしコンサルティーナとお別れ。
夜は久しぶりにケリーズというパブでアンドリューとの演奏を楽しんだ。
7月22日 曇り。夜から雨になる。
お昼、ホステルの台所を使って、フレンチトーストを作るが、火は弱いわ、フライパンは引っ付くわで、まるでスクランブルエッグのようなものが出来た。
それでも、アイルランド人の朝食よりはましかもしれない。
それから、近くのスーパーマーケットにでかけると、いたるところにアンドリューみたいな人がいる。
彼は典型的アイリッシュ顔かもしれない。あれもアンドリューみたい、あれもアンドリューみたい、あれ、あそこから歩いてくるのも…といっていたらアンドリューだった。
夜は購入した豚としょうがとしょうゆで“豚のしょうが焼き定食”を作った。あー、なんと素晴らしい味だろうか。しょう油は偉大だ。
ブローガンズというパブでジョセフィンとミックがセッションをするので、8時ころ街にでかけた。
セッションには例のタイ人も来た。やはり日本人の奥ゆかしさと違い、数少ないレパートリーを結構頻繁に弾いたりする。そうして数年後にはかなり弾けるようになるのかも知れないが、知らない曲にまで適当に参加されてしまうと、こちらのコード感覚に支障をきたす。気になって分からなくなってしまうのだ。
その日は、こちらに住む日本人のフルートを演奏する“ユカさん”ともお会いして、話が弾んだ。
ジョセフィンのセッションは彼女の人柄からとても人気があるそうで、僕らにとっても大好きなプレイヤーの一人だ。
2012年アイルランドの旅 ~7月23日 ドゥーラン~
7月23日 朝から雨。
その雨の中、ボー(タイ人の名前)は朝早くからモハーの断崖を見るために出かけて行った。
僕らも同じ方向であるドゥーランに向かう予定であったが、僕らは昼過ぎに着けばいいので、ゆっくり食事をしてから出ることにした。
またコンサルティーナのテリー・ビンガムが待ってくれている。今日はオコーナーズというパブでクリスティー・バリーとのセッションだ。
エニスを昼前に出るバスに乗ると、途中、モハーの断崖を通る。雨と霧と風で一寸先も見えないくらいだ。ふと見ると、ボーが乗ってきた。
どうだった?と訊くと、やはり何も見えなかったので入場料も取られなかったそうだ。僕が初めてここに来たのは、‘99年頃。アンドリューが連れてきてくれた。その時は勝手に空いているところに車を止めて、柵も無い断崖絶壁に恐怖を覚えたものだ。そんな風に普通に立ち止まれる観光スポットであった。
しばらくして、ユーロ圏に変わると入場料(たしか突然4ユーロだったと思う)を払うようになった。御土産屋もできた。柵もできた。そして今は6ユーロらしい。
お金をはらって怖い思いもしたくはないが、天気さえよければたしかに一見の価値は十分過ぎるくらいにある。
ボーは少しドゥーランを歩いてエニスに戻る、と言っていた。僕らはテリーと待ち合わせしてエニスタイモンという近くの町へ買い物に出かけた。
この辺では少し大きめの町なのでなかなかに大きなマーケットがあった。出入りする人がそれぞれに「やー、テリー」と声をかけていく。
いろいろ物色をしていると、とても美味しそうなアップルパイを発見。20cm以上の大きさもあろうパイがわずか2ユーロだ。まよわずそれをカゴの中に入れて他のものを見てまわっていると、希花が「あっ、こっちのほうが美味しそう」と別のアップルパイを見つけて叫んだ。
たしかに形は綺麗で上品だ。少し小さめではあるが同じ2ユーロ。テリーがジッと見つめてひとこと。「いや、こっちは形はいいけどリンゴの量が少ない」かくして最初のほうに決めたのだが、これが大正解だった。
味もよく、あふれんばかりのリンゴが入っていたのだ。アップルパイのちがいが分かる男、テリー・ビンガムだ。
夜、オコーナーズに向かうと、フィドラーのジェリー・ハリントンも来ていた。アメリカであって以来15年ぶりくらいだ。「やぁジュンジ」と独特なかん高い声が響いた。
ジェリーはかなり高名なフィドラーで、そのむかし僕が初めて会ったころには元ディ・ダナンのチャーリー・ピゴットと一緒にまわっていたはずだ。
ケタケタとよく笑う人だが、さすがに一人で弾いたエアーは胸に響いた。本当の本物だった。
2012年アイルランドの旅 ~7月24日 ドゥーラン~
7月24日 くもりのち雨、のち、くもり。大体こんな感じである。
お昼からテリーが近辺を案内してくれた。朽ち果てた教会や、海の見える丘などを見ながらも音楽の話になる。
テリーはやっぱり根っからのトラッド・ミュージシャンだ。心に響いてこないものは音楽とは思わない。彼の音からは確かに人間の息使いが聴こえる。
帰りにすぐ近くのおじさんでコンサルティーナを2つ持っていて、最近、売りたいようなことを言っていたひとがいる、ということで、ある家に連れて行ってもらった。
そこは数多いB&Bのひとつで、なんと僕らが去年、飛び込みで見つけたのだが、部屋が空いておらず、親切にもいろんなところに電話して最終的にすぐ近くの宿を見つけてくれたところだった。
そして奥さんが電話をかけまくっている最中に、だんなさんがコンサルティーナを弾いてくれた、まさにその人のところだった。
テリーがちょいちょいと弾いてくれて、いい物だけど安くはないし(コンサルティーナという楽器自体、いい物はかなりの値段だ)ゆっくり考えたほうがいい、と意見を聞かせてくれた。
アップルパイとコンサルティーナの違いの分かる男だ。
一旦テリーと別れた後、ギタリストでシンガーのナイルからお茶でも飲みに来いよ、と電話が入った。
去年知り合った、日本人の奥さんがいるもの静かでやさしい人だ。ドゥーランの中心部から少し離れた家に着くと、ふたりの子供と奥さんが出迎えてくれた。ひとりはまだ生まれて間もないが、もうひとりはやんちゃ盛りの男の子だ。
美味しいキャロットケーキと極上のコーヒーでひと時を過ごした。奥さんももの静かな人でとてもお似合いの夫婦だ。
ふたりにお礼を言って別れた後、またテリーとクリスティとセッションに興じて1時半頃に眠りについた。
2012年アイルランドの旅 ~7月25日、26日、27日 ゴールウェイ~
7月25日 晴れ
一路ゴルウェーへ。6時からデクラン・コリーのセッションだが、そのあと、8時からそのセッションのあるパブの裏手にある“セント・ニコラス”という教会でコンサートがあるのだ。コンサルティーナプレイヤーのコーマック・ベグリーがホスト役のそのコンサートは、週3回トラッド音楽が静かな教会の中でじっくり聴ける貴重なものだ。
実際、今回デクランのセッションでも、あまりにモダンでスピードも速く、それが結局はトラッドもよく分からないアイリッシュ音楽ファンに受けるためのものとして、この地でもてはやされているものの大半だな、という気がした。
コーマックは僕と希花をステージに呼び込んでくれた。とても生真面目な青年で彼のプレイからは彼自身の人間そのものが現れてくる。
「ところでコーマック。このあいだ僕の枕元で踊っていたのは君か?」
「いや、僕じゃない。でも全然覚えてない」そんな会話でお客さんも大爆笑。そして僕と希花の“フォギー・デュー”をはさんでジグとリールを演奏した。
そしてその日、コーマックが今オーダーしていてすでに4年経ったドイツ製の素晴らしいコンサルティーナの権利を、希花に譲ってもいいと考えている、という話を彼から受けた。
また、熱が上がった。まだ決まったわけではないが、うれしい悩みが増えたようだ。
7月26日 晴れ。
特になし。ただ、パブ“チ・コリ”の前で元ディ・ダナン、いや今の“オールド・ディ・ダナン”のジョニー“リンゴ”マクドナーと会って長話をする。
リンゴは今のディ・ダナンのことを“リアル・ディ・ダナン”と呼ぶ。フランキー・ギャビン以外のメンバーが彼と仲たがいして作ったバンドだ。
明日、バンジョーのブライアン・マグラーと一緒にセッションがあるから是非来ないか、と誘われたので、二つ返事でオーケーした。
明後日、フランキーと会う約束があることは黙っておこう。
7月27日 晴れ。窓辺にいると暑いくらいだ。
リンゴから再三電話が入り、6時半からチ・コリでセッション。ブライアンの素晴らしいバンジョープレイと希花のフィドル、リンゴのボウランに僕のギターというシンプルなトラッドセッションだった。
リノさんという名前の日本人の女の子のフィドラーも来た。元々ブルーグラスをやっていたそうだが、この人あとでびっくりさせてくれた。それは後に書くとして。
今日はまたコーマックの会が教会で8時から始まる。今夜はバンジョー弾きのポーラック・マクドナーと一緒だ。
ずっと前、アンドリューがベストバンジョープレイヤーと賞していた人だ。初対面だがとても気さくですぐに一緒に出演することになった。
それからは幾度となく共に演奏することになる。アンドリューとは大の仲良しらしい。
2012年アイルランドの旅 ~7月28日 ゴールウェイ~
7月28日 晴れ。ゴールウェイに来てからはずっといい天気だ。
今日は希花が初体験をすることになっている。生牡蠣を食べるのだ。ゴールウェイに来たらやってみたいことのひとつであったらしい。
僕も決して自分からすすんで食べようとは思わないので、誰かが食べるのなら、ということで付いていった。
5時ちょっと過ぎにマクドナーというかなり有名なレストランに行くと、5時にディナーがオープンしたばかりなのに、もういっぱいだ。
その懸案の牡蠣については希花がまた何かにつけ話をするかブログにでも書くことだろう。
食事をしているとフランキーからテキストが入って、7時頃、クレインズというパブで一緒にやろうといってくれた。
忙しく飛び回って時差ぼけが完治しない中、それでも駆けつけてくれることに感謝だ。
そしてその日、奥さんであるシンガーのミッシェルも来てくれた。
それに、フランキーのお兄ちゃんであるアコーディオンのショーン・ギャビンも駆けつけてくれて、とてもいいセッションとなった。
ミッシェルの歌声は天使のようだった。
そのときの様子がYoutubeにあがっている。
http://www.youtube.com/watch?v=qGh4q-e-z5Y
2012年アイルランドの旅 ~7月29日、30日 エニス~
7月29日 朝のうち少し雨、その後晴れ。
エニスに向かう。
8時半頃から“オキーフス”というパブでセッションがあるらしいのででかけてみた。予定ではフルートのジョン・リンがホストのはずだが、アイルランドらしく、9時をまわっても誰も現れない。
ただ一人だけ暗そうな男がフィドルを持って来たので、セッションがあるのか尋ねると「うん」とだけ答えた。
そうこうしている間に見たことのある人物が入ってきた。ニーヴ・パーソンズだ。そしてニーヴとずっと一緒のギタリスト、グラハム・ダンも一緒だった。
もう一人再会を祝す人物に出会ったわけだ。
またしてもニーヴの素晴らしい歌声に酔いしれた。そして意外にも先ほどの暗いフィドラー(リアムというらしい)はとてもいいプレイを聴かせてくれた。
こういう人がどこにでもいる。一見そうは見えないのに…。アイルランド人にとっては僕らもそうだろうが。
7月30日 晴れ。
ジョセフィンから電話で、今日はブローガンズでフィドラーのイヴォンヌ・ケイシーとセッションをやるからおいで、という。
野菜サラダをうんと食べてからでかけた。そろそろ野菜が恋しくなっている。いも以外の。
2012年アイルランドの旅 ~7月31日 ドゥーラン~
7月31日 小雨。
お昼のバスでドゥーランに向かう。またしても雨に見舞われるドゥーランだ。宿泊先のB&Bに着いても誰もいない。
屋根のないところで雨も降るし、お向かいさんのドアを叩き少しの間雨宿りをさせてもらった。
やがて、おばちゃんが帰ってきて一件落着。
今日もテリーとのセッションがある。クリスティ・バリーもいる。そこにちょっとだけ見たことのある人が入ってきた。「やぁ、ジュンジ」まただ。いつだったか、どこでだったか、と思いを張り巡らせていると、テリーが初めて飛行機に乗って西海岸にやってきた時、あれは‘99年頃、アメリカで会っているのだ。
だが、名前が思い出せない。仕方がないので思い切って訊く事にした。「お名前は?」
「バリーだ。ステージネームは“ルカ・ブルーム”」どひゃー、ルカ・ブルーム。信じられない。そんな有名人まで知っていたっけ。
思わず希花に、あのトミー・ピープルズの時のように「おい、大変だ。ルカ・ブルームだって」と言ったが、シンガーとして高名な人で日本のアイリッシュ・ミュージックの演奏者たちにはあまり馴染みが無いかもしれない。
しかしその夜、歌をいっぱい唄ってくれた彼の人柄と力強い歌声に希花も完全にノックアウトされてしまった。
ニーヴ・パーソンズと共に今回の旅の大きな収穫のひとつだ。希花もこうしてどんどんいろんな人に自分の存在を示していけばいい。
因みにルカは、僕らが初日にダブリンでコンサートに行った、あの、クリスティ・ムーアの弟にあたる人だ。
2012年アイルランドの旅 ~8月1日 ドゥーラン~
8月1日 晴れのち雨のちくもり
すぐ隣のホステルの談話室で練習させてもらっていたら、パディから電話が入った。今ディングルからダブリンに帰る途中だけど、僕らがドゥーランに来ているし、久しぶりにドゥーランに寄ってもいいな、と言っている。
是非そうしてくれ、という話になり3時過ぎに来ることが決定。
去年、なかなか連絡が取れなくて、同じ時期アイルランドにいたのだが、会うことが出来なかった。
とても楽しみだ。
3時半。パディから電話がきた。マクガンズにいる、と言う。すぐ近くのパブだ。てくてく歩くと、ちょうど時代劇のさびれた茶屋で浪人が茶をすすっているような、そんな雰囲気でパディが一杯飲んでいた。
見渡す限り広がる山、そして山。その真ん中に一本だけ続く道。遠くには牛や羊が何を考えているのか、ジーッとしているのが見える。
時折通る車、そしてトラクター。店の前に張り出したベンチに腰掛けて、長いコートに帽子といういでたちで佇む男。
どこから見ても絵になる。
再会を祝して、僕らも一杯。その後、何も無いドゥーランだが三人で散歩に出ることにした。
そこで僕は人生初体験をすることになる。
数日前から、とある民家の前庭にロバが佇んでいた。そのロバを入れて写真を撮ろうと、パディがカメラを構え、僕と希花が石塀にもたれかかったその時、突然ロバが僕の腕に噛み付いた。
緑の服を着ていたので草と間違ったのだろうか。ロバは肉食ではないはずだ。結構痛かったが、あまりのおかしさに3人で大笑い。


←いたそう
まれか大笑い→
青あざは1週間くらい残った。
夜はマクガンズでパディとセッション。といってもパディはパイプを持って来ず、最近凝っているバンジョーだ。しかし、兄であるバンジョー弾きの、今は亡き ジョニー譲りのいい感じで音を奏でる。
9時半過ぎからバンジョー弾きのケヴィン・グリフィンと若いフィドラーも加わった。その後、近くのフィッツ・パトリックというパブでエニスから来ている若者テクニシャン3人が演奏していたことを知っていたので、もうとっくに終わっていることは承知の上でテクテク歩いて出かけた。
ロバはもう眠っているかな。
パブに着くと3人のうちパイパーであるブラッキー・オドンネルが僕らを今か今かと待ち構えていた。
パイパーにとっては神様であるパディーが来ている、という噂は彼らにも届いていたようだ。
さっそくセッションしよう、と、どぎついブラッキーのパイプがうねりまくる。ここではパディもブラッキーのパイプを借りて円熟した音を聴かせてくれた。
結局4時まで演奏しまくった。
帰り道、ロバを見たが「あ、俺が噛んだ奴が歩いてる」というような目つきでこちらを見ていた。まだ痛かった。
2012年アイルランドの旅 ~8月2日 ドゥーラン~
2012年アイルランドの旅 ~8月3、4、5日 エニス~
8月3日 曇り
ドゥーランを出てエニスへ。
コンサルティーナをコーマックから買うことが決まったので、その旨を伝えにカスティーズに行ってみると、ありゃ、僕らが一応ホールドしておいてくれ、と頼んだはずのものが無い。
「あれ、売れたよ」と何事も無かったように言うジョン。結果的には問題ないが、僕らはパウロにあれだけ念をおしておいたのに、と取り合えず不満をぶつけた。
日本ではなかなか考えられないことだ。
夜はいくつかのセッションを見学してから、オールド・グランド・ホテルのパブで演奏している、ブラッキーたちのセッションに出かける。
バンジョーのカロル、ブズーキのショニー、フィドルのジョン・ケリーなどと、生きのいいセッションを楽しみ、1時半ころB&Bに戻る。
アイルランドのセッションとしては比較的早く帰れたほうだ。
8月4日 曇ったり降ったり。
B&Bで一緒に泊まっているドイツ人、フランス人、アメリカ人などと、ワインを飲みながら一日ゆっくりする。
たまにはこんな日もあっていいだろう。
8月5日 曇り時々晴れ。
夜7時からブラッキーのセッションを覗き、久々にブズーキのシリル・オドナヒューにも会い、渋いヴォーカルを聴かせて貰った。
9時からはまたブローガンズでジョセフィンのセッションがある。待っていると、パウロがやって来た。あっ、まずい!と思ったのだろうか。なんとなく存在を打ち消すように
していた。それでもちゃんとセッションには参加していた。
10年以上前にエニスで会った、“フー”こと赤峰君も来ていていろいろ昔話に花が咲いた。アンドリューもカウンターで飲んでいたが、いつの間にか出ていったらしい。パウロもいつの間にか、いなかった。
2012年アイルランドの旅 ~8月6日 タラ~
8月6日 曇り
エニスを出てアンドリューの家があるタラに向かう。ひたすら寒い。そして、何年も変わっていない景色が広がる。
まるで故郷に帰ってきたようだ。僕にとってのアイリッシュ・ミュージック発祥の土地である。
アンドリューが彼のセコンドカーであるメルセデスベンツを軽快に飛ばしながら言った。「今晩ポーラック(バンジョー)がミノーグスで集まろう、と言ってきている」彼の言葉はいつでもセンテンスが短い。余計なことは言わない。
僕も「オーケー」と答えた。
ミノーグスはあの伝統のバンド“タラ・ケイリ・バンド”発祥のパブだ。
8時過ぎ、出かけていたアンドリューから電話が入った。「ポーラックがミノーグスで待っている。おれも後から行く」
店に行くとポーラックがすぐに言った「なんか飲むか?」みんな先ずそう訊く。
僕はカールスバーグ、希花は最近のお気に入り、ホット・ウィスキーをもらった。そして彼が言った。
「もうすぐミーブ・ドナリーもやってくる」
クレアーのフィドラーでアメリカやヨーロッパでもかなり名の通った女性だ。僕も一度
だけアメリカで会ったことがある。
かくしてまたまたセッションの始まり。途中からアンドリューもやってきて1時半過ぎまで続いた。
次から次へと運ばれてくるギネスやホット・ウィスキー、それに大量のサンドウィッチまで。全部オーナーの計らいだ。
アンドリューが言っていた。「最近、ここ10年くらい、このタラですらもなかなかトラッドが聴けないようになって来た。寂しいもんだ」
僕らはこの地に、久々にトラッドの風を運んできたのかもしれない。
2012年アイルランドの旅 ~8月7日 タラ~
8月7日 曇り
今日は一大イベントが待っている。この地に最初に訪れた時から必ず通っているパブ“マッカーサー”通称“フランの店”に行くことだ。
来年になると生きているかわからない高齢のフランが、夜10時半頃開ける店だ。昨夜ミノーグスの帰りに外からフランがいるのは確認しておいた。
法律上12時過ぎに店に新たなお客さんを入れる事が禁じられているので、窓越しに「明日来るから」と言った。
温度差でくもったガラスをゴシゴシしながら合槌をうっていたフラン。ちゃんと覚えていたかな。
「昨日、きてくれたな」ちゃんと覚えてくれていた。まだしっかりしたもんだ。足を痛めて少し入院していたらしいが、相変わらずピシッと決めたスーツがかっこいい。
アイルランド最高のギネスを2杯オーダーした。ここまでギネスは極力控えてきていた。彼の注ぐギネスを今日まで待ちわびていたからだ。
カウンターでお金を払おうとすると「いいから一杯やってくれ」という。僕はとことん希花に自慢して「どうだ。これがギネスだ。他と違うだろう。この道60数年の匠の技が生きているんだ」と言うと、希花も「うん、確かに美味しい」と言って、「でも悪いから何か他のものもオーダーしよう」と言う。
それじゃぁ何か頼んでおいで、と促すと、カウンターの奥でフランがヌッと立ち上がった。
希花が言った「ワン・ホット・ウィスキー」フランがグラスをおもむろに“二つ”用意した。
そして出てきたものがウォッカとウィスキー。
確かに言葉は似ている。しかしフランのホット・ウィスキーは注文があるとおもむろに湯沸かし器に水を注ぎ、じっとお湯が沸くのを待ち、ウィスキーと混ぜて終わりなのでそんなに匠の技は生きていない。
なのでそれはそれでいいとして、希花のおかげでウォッカまで飲むことになってしまった。
来年また来るから元気でいてね、とフランに別れを告げて店を出ると、ほとんど電気の無い広大な土地に沢山の星が降りそそいでいた。
2012年アイルランドの旅 ~8月8,9日 フィークル~
8月8日 曇り。めずらしく暑い。
暑いとは言えども、たかが27~8℃。そんなことでへたっているアイルランド人に比べると、日本人は大したものだ。
一路フィークルへ。今日から5日間、ここでのフェスティバルに参加する。金曜日には、アンドリューとテリーとのギグ。土曜日にはジョセフィンとミックとのギグが控えている。
散歩していると、これから始まるこの村の一年に一度の大イベントのために来ている人達に出会った。
去年、同じB&Bに泊まっていたイギリス人の夫婦に会った。旦那さんがバンジョーを一日中練習しているのをにっこり見ていた奥さん。
二人ともちっとも変わらず、しばらく立ち話に興じた。最近はフィドルに凝っているそうで、一生懸命希花に質問を浴びせかけていた。奥さんはにこにこして彼を見ていた。
マーティン・ヘイズともしばらく立ち話をし、デニス・カヒルとも挨拶を交わし、道行く見ず知らずの人達ともすぐに友達になった。
とりあえず、今日は軽くセッションだ。ホステルのすぐ近くのパブのひとつ“ショッツ”で10時半頃から2時まで。(勿論、夜)
アメリカ人の若者が、「あっ、ジュンジ。ジョディース・へブンだ。俺の町に演奏に来た時に行ったよ」と陽気に話しかけてきた。驚いたものだ。
彼と、それからドイツ人のかなりの腕前のフルート吹き(クラウス)とのセッションは、パブのオーナーにも随分気に入られ、来年はここで君たちにセッションホストをやってもらう、とまで言ってくれた。
また楽しみが増えた。
ホステルに戻るとポーラックからメッセージが入った。たった今、着いた。ボーハンズ(4軒のパブのひとつ)でやってるから来い。
見ると8時頃入るはずだったメッセージが今ごろ届いている。ここでは電波もゆっくりだ。
僕の返事にしてもいつ届くか分からない。とりあえずメッセージを出して眠ることにした。
8月9日 曇り時々晴れ。今日も少し暑い。
結局ポーラックとも連絡が取れた。そして彼が言った。「今晩、アコーディオンのダニー・オマホニーと俺がやるんだけど、ギターを弾いてくれないか?」
勿論オーケーだ。
ペパーズで9時に始まったそのセッションは2時をまわってもますます白熱してくる一方。しかし、どこでも誰でもアイリッシュ・ミュージシャンはタフだ。
僕と希花と、前日に仲良くなったクラウスは3時を少しまわった頃失礼して10分程歩いたホステルに向かった。
あたりは見事に真っ暗だ。でもこんな時間に犬の散歩をしている人がいる。犬にもアイリッシュタイムがしみついているんだろうなぁ。
ホステルのすぐ近くのショッツを覗くと、本当はもう中には入れないはずなのに、店のオーナーである、ジェリーが気前よく中に入れてくれ、ビールをおごってくれた。
彼はいったいいつ眠っているんだろう。そして、後で聞いた話だが、ポーラックとダニーは朝8時頃まだ演奏していたらしい。
2012年アイルランドの旅 ~8月10日 フィークル~
8月10日 晴れ。珍しくまだ暑い日が続いている。
朝、クラウスが、他の奴のいびきがうるさくて、トイレットペーパーを耳に突っ込んで寝たらどうもそのはしっこが詰まってしまったらしい、といって困っていた。
希ちゃん先生の出番である。さすがにドイツ人相手に「バカじゃないの!」とはいわなかったが、覗いても見えなかったので綿棒を渡していた。
昼からのチューターズ・コンサート(ワークショップでのインストラクターによるコンサート)を聴いてから、ブローガンズに寄ると誰も演奏していなかったので、僕と希花の二人で始めてしまった。
そこへ、続々とインストラクター達が入ってきた。
フルートのレオン・アグニューとタラ・ダイアモンド、そしてフィドルのブレンダン・ラリシー。超一流どころが、じっと僕らの演奏に聴き入っている。
そして、是非一緒にやろうじゃないか、と僕らを取り囲んだ。彼らのプレイは本物だが、こちらも百戦錬磨だ。いけ!希花!チャンスだ、と攻め立てる。
彼らは一同にぼくらの演奏を気にいってくれたようだ。3時間ほどのセッションがあっと言う間に終わった。
でも、本当は彼らがホストのセッションがそこで行われる時間だったようなのだ。そんなことになっていようとは知らなかったが、彼らもなにも言わず、僕らの演奏に耳を傾けてくれたのだ。
夜は9時からアンドリューとペパーズでセッションだ。今朝テリーから電話で、どうしてもダブリンに行かなくてはならないから、希花と3人でセッション・ホストをやってくれ、という旨の連絡が入った。
アンドリューは生粋のタラ・ケイリ・バンドのメンバーだ。この音楽のリズムを体で覚えるのには最適の相手の一人だ。
耳からやっとトイレットペーパーが外れたクラウスも希ちゃん先生にお礼を言ってフルートを気持ちよさそうに吹いていた。
またまたアンドリューが大爆発。
ホステルに戻ったら3時を少しまわっていた。
2012年アイルランドの旅 ~8月11日 フィークル~
8月11日 曇り。いい風が吹いて涼しい。
ホステルのキッチンを使って豚の生姜焼きを作ってみた。醤油とはなんと偉大な調味料だろうか。
ごはんも炊いた。納豆でもあったらもっといい。
若い頃、初めてアメリカへ行った時には、2週間毎食ハンバーガーでもなんとも思わなかった。でも、40歳もこえた頃からやっぱりごはんが食べたくなった。
結婚式の仕事に出かけた時などは、どんなに手をかけたケータリングの食事よりもお茶づけが食べたかった。
そんな話をしながら食事を済ませ、9時からのジョセフィンとのセッションのために少し昼寝をすることにした。
これじゃあ太るだろうなぁ。
彼らとのセッションはいつでも楽しい。ジョセフィンはセンスがとてもいい。口でなかなか説明できないので、いつか日本に呼べたらな、と思っている。
終わってショッツで飲んでいると激しい雨が降ってきた。やっぱりアイルランドだ。でもあと少しでお別れかと思うと寂しい。
ジェリーがにこやかに言った。「忘れるなよ。来年は君達ふたりがここのセッションホストだ」
少し小降りになったので、ジェリーに別れを告げて店を出た。雲の切れ目から少しだけ星が顔をのぞかせていた。また3時過ぎていた。
2012年アイルランドの旅 ~8月12日 フィークル~
8月12日 曇り
とうとう、かなり疲れてきたみたいだ。昼過ぎまで寝てしまった。散歩しようと表に出ると、ジョン・キングとバッタリ。飲んではいるようだが、まだまだギネス50杯くらいだろう。会話も成立したし、しっかりしたもんだった。
空が暗くなってきた。ポツポツときた、と思ったら、次の瞬間バケツどころか海をひっくり返したくらいの雨になった。ほんの2~3秒だ。もし外で楽器でも弾いていたら片づける暇はなかっただろう。
ジョニー“リンゴ”から電話がかかった。フィークルに来ているんだけど、どこかで一緒にできないか、という。
雨も手伝って殆どのパブはもう人でいっぱいだし、セッションもホストが決まっていてなかなか場所がない。
ふとみると、モロニーズという、昨夜ジョセフィンと演奏したパブの裏庭なら屋根もあるし、今のところ空いているようだ。
すぐにリンゴに電話をすると、日本人の女の子を2人連れてきた。そのうちの一人は、ゴールウェイで出会ったリノさんだった。
彼女がおもむろに言った「すみません。神戸でバンジョーを弾いていた、三津谷って覚えてますか」
「あー、勿論。ロッコーマウンテン・ボーイズだったかな。当時評判のバンジョー弾きだったよ。すごく上手かった。どうして彼のことを知っているの?」
「あたし、三津谷の娘です」本当に驚いた。僕は多分、大学時代から知っていたはずだ。「たしか“三津谷組”っていうファミリー・バンドやってたよね」
「そうです、フィドルをやってました」
早速、希花と“ジェルサレム・リッジ”のデュエット。
三津谷君、またどこかで会えたら嬉しいな。
ホステルに戻ると、フィドラーのブレンダン・ラリシーから、また会いたいから連絡をくれ、とメッセージが入っていた。
明日エニスに戻るので、そこで会うことにしよう。
フィークル最後の晩、ショッツでゆっくりビールでも飲もうと出かけてみると、数人がセッションをしていた。
結局つかまってしまい、セッションに加わることになり、また3時過ぎに戻ることとなった。
2012年アイルランドの旅 ~8月13日 フィークル、エニス 最終回~
8月13日 (最終回) 晴れて涼しい。
いよいよフィークルともお別れだ。そして僕らの旅もここが終わればもう終わったようなものである。
ホステルを出て、エニス行きのバス乗り場まで行く途中、ジョディス・ヘブンを見た、というアメリカ人の若者“ブレイク”と出会った。いかにもカリフォルニアの若者で、とても陽気な男だった。
去年、会った犬もいた。
 コーマックとポーラックが千鳥足で歩いてきた。「今からペパーズでやるぞ。来るか?」さんざんやってきただろうに、場所が変わればまた別物なんだろう。
コーマックとポーラックが千鳥足で歩いてきた。「今からペパーズでやるぞ。来るか?」さんざんやってきただろうに、場所が変わればまた別物なんだろう。
「いや、僕らはエニスに行くから、また来年やろう。元気でな」別れはつらいものである。
ジェリーも通りかかった。
フェスティバル自体も今日で終わりだ。また明日からは、みんな普段の生活に戻り、村は静かになるだろう。
しばし感傷に浸る…。
エニスに着くとブレンダン・ラリシーが待っていた。彼は僕らとちょっとしたビジネスの話もしたくて、なんか高級そうなホテルのラウンジで食事をすることにした。
ランチでサーモンのディッシュがあったのでそれにしたが、タルタルソースの乗ったサーモンは美味しかった。が、しかし、サイドにはマッシュポテトとフレンチ・フライ、そしてパテになったじゃがいも。それもすべて山のように付いている。もう、いもはこりごりだ。
ブレンダンは素晴らしいフィドラーであると同時に、音楽プロデューサーとしても高名なひとだ。
僕らが常日頃言っている、「何をやっても自由だが、基本、トラッドを大切にしなくてはこの音楽を演奏する資格は無い」という姿勢を僕らの演奏から感じ取ってもらったことは本当に嬉しい。
彼とのビジネストークはここでは書かないが、これからもいろんな意味で彼と関われたらそれは素晴らしい事だ。
日本に帰ってからも連絡を取り合う約束をして、僕らはそのままダブリンに向かった。
ダブリンには帰りの飛行機の関係上寄るのだが、いくつかの都会らしい音楽に触れることはできるだろう。
しかし、僕らはやっぱりシンプルでも心温まる田園風景が、羊が牛が、そしてロバが見えてくるような、そんな音楽に恋をしてしまう。
そして、そういう人達が世界中からやってきて、言葉も生活環境も全く違うのに、共に音を紡ぎだしていく。出会いと別れの真ん中に音楽がある。
今回の旅で出会った全ての人に感謝すると同時に、みんなが幸せに暮らしていって、またどこかで会えたら、それがなにより嬉しい。
Jon Hicks来日
世紀のスーパーフラットピッキング・アイリッシュギタリスト
ジョン・ヒックスがとうとうやってきます。
あまり多くの公演はいたしません。世界を股にかけて活躍するジョンですが、恐らく彼のスーパーピッキングを目の当たりにする機会はなかなか無いものと思われます。
90年初頭、まだアイリッシュ・ミュージックのギタースタイルを模索していた頃、彼に出会いました。正直、やばい!と感じました。世界の大きさを知らされました。日本でアイリッシュ・ミュージックをこよなく愛し、また、演奏している人達にも、是非そんな感覚を味わってもらいたいものです。
公演予定はライブスケジュールにのっています。また彼については、このwebのコラムにも記事が載っています。お問い合わせは 10strings.j@gmail.com へ。
ジョン・ヒックス 10/26
ジョン・ヒックス、やってきました。
「俺は誰のクローンでもない」という彼のギタープレイはますます凄い。さんざん弾きまくってもう眠りに入りました。
心臓が今でも高鳴りを覚えています。とても言葉では表せないけど、もしアイリッシュ・ミュージックというものに少しでも興味があったら、ノックアウトされてみませんか?
現在アイリッシュ・ミュージックを深く演奏している人も、これから演奏してみようかと思っている人も 今までのだれからも聴いたことのない、強烈な音が聴けることまちがいありません。
ジョン・ヒックス ギター・クリニックAt ギター・プラネット
またしても気持ちのいいお天気にめぐまれ、ジョンを連れて僕と希花は一路お茶の水へ。
沢山のギターのなかから、特に僕もジョンも使っているローデン・ギターの選定をおこなうが、どれをとっても素晴らしいものばかりで選ぶのはとても難しい。
それでも僕とジョンで一本ずつ“これ”と思うものに、認定書を付けてくれた。是非トライして欲しいものだ。
さて、クリニックの方はというと、なかなか説明するのも難しいものだが、充分に彼の彼らしいギター・プレイを味わっていただいたものと思う。
お客さんの中に、アイリッシュミュージックを実際に演奏している人がひとりもいなかったことは残念だ。
僕は95年に彼のギター・プレイを聴いたことがひとつの飛躍の素となった。ショックだったのである。
これはいかん。いつまでも同じ所にとどまって、じぶんこそは、などと思っている場合
ではない。次にいかなくては、自分のスタイルを創り上げなければ、と必死になったものである。
ことさら、アイリッシュというカテゴリーをひとつの核としてこの東京でも活躍しているひとたちが、もしかしたら次のステップのヒントを得られるかもしれないチャンスを掴もうとしないことは重ねがさね残念でならない。
まぁ、諸々の事情があるだろうし、こんな歳寄りのたわごとはこれくらいにしておいて、この日のために多くの人が集まってくれたことを感謝いたします。
フラメンコギターを弾いている、という若者は、一番前で食い入るように、時に嬉しくて笑いが止まらない、という表情をしていたのが印象的でした。
店の前でぶらぶらしていたニュー・ヨークから来た、というおじさんも全く知らなかったはずなのに感激して最後まで聴いていってくれました。
昔からの友人である村松さんはぜーぜーいいながら(でもないか)「会社終わって間に合いそうだからすっ飛んできた」と言いながらやってきてくれました。
遠い新潟から駆けつけてくれた白井さん。ホワイティーと呼んでくれ、と、けったいなことを言っていたけど、すっかりジョンと仲良くなってしまい、かえりにはビールからラーメンに至るまで、全て僕らにご馳走してくれました。
今度また新潟に遊びに行かせてください。
お店のスタッフのかた。セッティングご苦労様でした。後片づけ、大変だったでしょう。
あんな感じで良かったのかな、と反省しておりますが、また是非よろしくお願いします。
ローデン・ギター、売れるといいですね。
ジョン・ヒックス 次の土地へ
火曜日の夜、厳密には水曜日になったばかりのフライトで無事、タイに向けて飛んでいきました。
全く嵐のような男でした。
過去に、ジャック・ギルダーのアパートに居候していたことがあったので、今、僕の所にジョンがいるぞ、とメールしたところ、壊れそうなもの、大切なものは帰るまで別な処に保管しておけ、という返事が返ってきた。
まだ20代前半だった彼は破天荒の駆け出しだったのかもしれないが、今ではその破天荒ぶりにも磨きがかかり、なかなかの人間に成長していた。
10歳のころ「おれはヴァン・モリソンのギタリストになりたい」と母親に話したら、こう言われたそうだ。
「ジョン。あなたは誰のためのミュージシャンになってもいけない。あなたはあなた自身のために音楽をやりなさい。あなた自身になりなさい」
そうして15歳で家を飛び出し、世界各地で自分を磨いていったのだ。
だが、あまりに多くの納得がいかない事柄に接してきたせいか、語り出すと止まるところを知らない。結構理屈っぽくて面倒な男ではある。
多分、スケジュールがあまりタイトではなく、時間を持て余していたのだろう。とにかく毎日でもステージ上で音楽がやりたいのだ。
彼を呼ぼう、と決めた時、本当にちゃんとやってくるかな、ということがいちばん心配だった。
イタリアからやってきて、タイに帰る、というのも非常に面倒くさい。見た感じ、なんかやばいもの持っていても不思議ではなさそうだし。
そんなこともあり、スケジュールをあまり詰めなかった。そして、もうひとつの大きな理由が交通費と集客の兼ね合いだ。
いくら、素晴らしいミュージシャンでも大手の呼び屋さんがやるようにはいかない。おまけに、アイリッシュ・ミュージックに関わっている人達の動員が全く望めない、という考えられない状況。
さんざん言ってきたので、もうやめておこう。
来てくれた人達は、一様に度肝を抜かれたに違いない。熱い男がまだ少年の頃から探し求めてきた彼でしか聴くことのできない音だ。
希花に彼を紹介した時「呼ぼうよ」と強く求められた。他にも彼女が押している人物がいる。
僕はそうして、彼女に多くの凄腕ミュージシャンを紹介しているが、つい昨日、フランキー・ギャビンからオファーのメールがきた。
彼のフィドル・オーケストラの初代日本人フィドラーとして希花を起用したい、ということだ。
ジョンがそのメールをみて、「やれよ」というが、どうだろう。まだ勉学があるし。僕とジョンでメールをした。
「とてもありがたいが、まだ大学でのやるべきことが残っているので、今すぐにはできないけど、将来のために場所をのこしておいてくれるか?」という趣旨。
ジョンがいたおかげで、素晴らしい文章が送れたらしい。すぐにフランキーから返事がきた。「勿論、彼女の席は置いておく。時期をズラスかもしれないし」
いい話を受けるにはいいタイミングというのも必要である。
ジョンは言う。「アイリッシュ・ミュージックにおいてギタリストはどこまでも脇役だ。どんなに素晴らしくても、人々が相手にするのはリード楽器だ。だから俺はアイリッシュ・ミュージックからある意味さよならした。毎日まいにち同じような曲をやってはいられない。そしてアイリッシュ・チューンであってもギター一本で勝負するスタイルを創ったんだ」
彼の生き方の中では一理ある。
僕は言う「アンサンブルというのがとても好きで、アイリッシュ・ミュージックの中で独特なアンサンブルを創り出すこと、それを素材として自分なりの解釈を広げていくこと、そんなやり方に今は興味がある。希花との出会いでそれが実現している。少なくとも今は」
将来、彼女がミュージシャンとして大きく成長していけるよう、ジョンにも協力をお願いした。
語り出すと面倒くさいが、かなりインテリで、経験豊富な男だ。そしてギタリストとして飛び抜けていることも事実だ。
そうこう言っているうちにタイからメールがきた。
「いろいろありがとう。俺はいま短パンとTシャツに着替えたぞ」
だって。
東京でのライブのお知らせ(詳しくはLive Scheduleをご覧ください)
12月8日
いつもの蒲田教会で、Mareka&Junjiのアイリッシュ・ミュージックをメインにしたコンサートを行います。
今回は事実上、2人による2nd albumの発表の場となります。
Music in the Airというタイトルで、美しく、やさしいメロディを揃えております。
新しい作品ではありますが、僕らは又、次のことを考えなくてはなりません。
8日のコンサートを、今と将来とを合わせて見つめられる、そんな場に出来るよう考えています。
12月15日
阿佐ヶ谷のバルトで城田純二、坂庭省悟を唄う、という会を店主である森谷君と企画いたしました。
僕にとってはこういう題目で初めてです。
あまり過去を振り返っても仕方ないのですが、彼は大学時代からの最も近い友人でした。
静かに彼の歌を唄います。いや、みんなも一緒にお願いします。
当日、内藤希花も参加いたします。
花嫁、初恋、別れの唄、一本の樹、心の旅、ハードタイムス、力をあわせて、旅立つ前に等、みなさんも練習しておいて僕を助けてください。
ほんの少しだけアイリッシュもやります。
彼ともよくアイリッシュ・チューンで遊びました。
企画して頂いた森谷君に感謝しています。
MUSIC IN THE AIR

Music in the Air出来上がってきました。とてもリラックスして聴けるアルバムだと思います。
行程のほとんどを自分たちでやったので、これからもっともっと勉強していかなくてはいけない部分もあります。
勉強は希花さんの得意とするところであります。僕の方は残り少ない人生を、現状維持していきながら、少し前へ進めたらいいな。
早々と次の事も考えていますが、ひとまず今回のMusic in the Airを聴いていただくと、僕らの音楽観が分かっていただけると思います。
僕らは二人とも、元はクラシック出身です。そのせいかどうか分からないけど、根本的に、美しい音楽、美しい音使いというものが好きです。
勿論、力強くも美しい、という言葉があるように、両方が揃ってこそ音楽、更に、人々が抱える喜怒哀楽を表現できれば、それこそが音楽、と言えるでしょう。
そして、ひとつひとつの音に理由がある。そんな音使いが二人とも好きなのです。なぜこの音を使うのか、ということは、なぜこの言葉を使うのか、ということと全く同じなのです。
そして、それがことさらに理屈っぽくならずに、ごく自然に打ち出せたら、本当に心からの音楽が演奏できるようになるでしょう。
そんな第一歩となるようなアルバムに仕上がったと思います。
僕達の音楽に耳を傾けてくれる全ての皆様に感謝いたします。
師走
そろそろ今年1年を振り返る時が来た。早いもんだ。歳をとると時間が早く過ぎていくようだ、と言う人がほとんどだ。
朝は早く眼が覚めるので、一日が長いようだが、気がついたらもう日が暮れそうな時間になっていることもよくある。
20代では、自分が60代になるなんて考えたこともなかった。とにかくバンジョーを弾きまくっていたものだ。
今のように便利な時代ではなかった。
レコード屋さんで同じ曲を何度もかけてもらい、頭の中で復唱しながらバスで下宿まで戻り、確かこんな感じだった、と何時間にもわたって弾き、また次の日に細かいところの確認のためにレコード屋さんに出向いてゆく。そんな毎日を過ごしていた。
めったにお目にかかれない外タレのコンサートではいつでも、どうやって弾いているんだろう、と興味津々だった。
よく覚えているが、ビートルズのヘルプで、かっこいいリードギターのリフのところを見るために一日中映画館にいたこともあった。それも3日間連続で。
結局、その部分はジョージ・ハリソンの手元がぼやけるような映像であったのだが…。
そんな風に、大きく分けると、フォーク、ブルーグラス、アイリッシュと演奏をしてきて今に至っている。
今年1年も沢山の人たちに支えられ、助けてもらって無事ここまで来れた。
音楽面でいえば、春には北海道でrinkaのおふたりの素晴らしい演奏に触れることが出来た。オートハープのご夫妻には驚かされた。
ひさしぶりに会った北のブルーグラス・フィドラーは、ただならぬブルースフィーリングを漂わせていた。
アイルランドでは各地で独特な演奏を繰り広げる人たちから沢山の刺激を受けた。やっぱり伝承音楽が好きだ。
イベントチックなものにしか興味が無い、と言った日本のアイリッシュ関係者がいたが、僕にはまったく理解できない。
選挙に当選しようと、軽々しい発言をしている政治家と同じレベルとしか思えない。
ところで、今ほど政治家というものがいい加減な存在だと思ったことは無かった。かといって、どうしようもないのだが。
いくら国民が反対しても、いつの間にか彼らの思い通りになっている。気がついた時にはそうなっているのだ。
先日、3・11関連の書物に触れたが、国会の廊下をギャラリーにして、写真展ができないだろうか。
政治家は毎日、震災で苦しんでいる人たち、ひとりひとりの顔を見るべきだ。街角でぎゃーぎゃーパフォーマンスしていないで、基本に戻るべきだが、その基本と言うものが無いのだろう。
間違いなく誰にでも人生の終わりが来る。60も過ぎると、あと20年くらいかな、なんて考えてしまう。
いや、もしかしたら1年先かもしれないし、40年も生きてしまうかもしれない。こればかりは自分でも分からない。
本当は音楽関連のことのみ書こうと思っていたが、1年が終わるということになると、いろいろなことが思い出され、まとまりのないものになってしまいそうだ。
しかし困ったことにこの歳になると、若いときにはとても言えなかった事や、決して言ってはいけなかったことなども、ついつい言ってしまって、若い人から煙たがられるものだ。くわばら、くわばら。
今年は秋がほとんどなかったように思う。季節では秋がいちばん好きだ。春もいいが、これから苦手な暑い夏が来ると思うとつらいものがある。
一時期、アラスカに住みたい、と思ったこともあった。それくらい寒い気候が好きだったが、最近は結構寒さも身にしみるようになってきたみたいだ。
大体、暑いだの寒いだの言い始めるのは年とった証拠らしい。確かに友人に出会ったときに「暑くなりましたね。寒くなりましたね」と言う挨拶は若いときにはまず交わさなかったものだ。
しかし日本の四季というものは素晴らしい。春の桜は誰にでも見せてあげたいし、紅葉に包まれてもの思いに耽るのもいい。
そうだ、京都へ行こう。なかなかに上手いキャッチコピーだ。
今年は京都でのライブが最後になりそうだ。63歳の誕生日。
一年の締めのつもりで書き始めたが、全く締まらないものになってしまった。またなにか思うことができたら書くことにしよう。
阿佐ヶ谷バルト 坂庭省悟をうたう
ハープのイントロで始めた花嫁。僕の青春時代、多数のページを埋めた想い出にのせて全13曲ほどを唄いました。
最後のインスト“青春の光と影”まで、師走の忙しい時に来ていただいたみなさん、一緒に唄って頂いて心底嬉しかったです。
特に彼を偲ぶ、ということではなく、彼が愛した歌(他にも沢山あるが)を今のかたちに蘇らせるというのが、最大の供養かもしれない。
勿論、その中に彼が生きている。あいつの独特な声、独特な唄いまわしでないと雰囲気が出ない歌、心を揺さぶることができない歌、いっぱいあります。
それでもみなさんの温かい気持ちが僕を支えてくれました。多分、省悟も支えてくれていたのかもしれないし。
フォークソングもブルーグラスもアイリッシュも省悟にとっても、僕にとっても全て大切な音楽。
僕は新しいパートナーとこれからも本物の音楽を演奏し唄っていきたいと思っています。
店主の森谷君。こんな機会を与えてくれてありがとう。キッチンで忙しくしておられた中村さん、お疲れ様でした。ありがとう。
音響を担当してくれた横澤さんにはいつも最大の気配りをしていただいて感謝しています。
会うことが叶わなかった省悟の歌に絶妙に伴奏を付けてくれた若い希花に感謝。
一緒に唄って頂いたみなさんに感謝。
そして、坂庭省悟に。「ありがとう」
アイリッシュ・ミュージックにおけるギタープレイその2
久々にケヴィン・バークとミホーのデュオを観た。勿論ユーチューブで、だが。しかしながら、この映像についてはずっと心に残るものがあった。
本格的にこの音楽に取り組みだした1991年のころ、ホームスパンから入手したものだったが、友人に貸したまま今はどこにあるか分からない。
なにはともあれ、まだまだギタースタイルを模索中だった僕にとっては衝撃的なものだった。
ミホーの編み出す音は、どれもこれも完璧だった。フィドルとギターという最低限の編成で、いかに音楽を構成しているのか、穴のあくほど見つめ、寝ても覚めても、1曲目の“ピジョン・オン・ザ・ゲイト”から 最後の“フェアーウェル・トゥ・エリン”に至るまで、その全ての音のうねりが頭の中を巡っていた。
カポタストはゴムのものを使用し、まだクィックチェンジなるものが出る前だったのかもしれない。ほとんどが同じキーの進行で構成されていた。
余談だが、僕らがフォークソングを始めた頃、まだカポタストを手に入れる、という観念が無く、短くなった鉛筆に沢山の輪ゴムを絡ませて作ったものだ。それでも結構いけたもんだ。
そういえば、弦は針金を張ってみたこともあった。最低の音だった。もう50年近く前のことだ。
さて、話しを戻そう。ミホーは僕が最も影響を受けたギタリストの一人であることは間違いない。
もしかしたら、僕自身のスタイルはミホーと、もうひとり、ランダル・ベイズをミックスさせたもの、それからクラシック、大好きなジョー・パスなどが使うコード進行を取り入れたもの、ということが言えるかもしれない。
ジョン・ドイルやドナウ・ヘネシーなどは、90年代半ばにはもう同じ立場に立っていたので、さほど影響を受けた覚えはないが、どちらも素晴らしいギタリストだった。
勿論、去年来日したジョン・ヒックスも素晴らしいギタリストだ。だが、彼らも一様に口を揃えて素晴らしいギタリストだと絶賛するのがミホーだ。
フィドルとギター、という究極の組み合わせは、沢山の楽器を擁する編成のバンドと違って、ある意味とても難しい。
しかし、彼らの演奏は胸が熱くなるほど郷愁に満ち溢れている。それは民族の歴史であり、かれらを取り囲む自然であり、そういうものが音楽という媒体をとおしてひしひしと伝わってくるからだ。
僕らが生活の一部としているアイルランドの音楽。さらに今年からは心して取り組まなくては、という思いにかられる。
ユーチューブというものが果たしていいものかどうかはわからないが、こうして彼らの音を再び聴くことが出来た、というのはとても嬉しいことだ。アップしてくれたモハーさんに感謝。
アイリッシュ・ミュージックと楽譜 2013年1月に思うこと
よく、「あの曲の楽譜ありませんか?」という質問を受けます。タブ譜もしかりです。ブルーグラスでバンジョーを弾いていた時にはタブ譜を読んだり書いたりしていました。実際にピート・シーガーの教則本にフォギー・マウンテン・ブレークダウンのタブ譜があり、それまでに弾いていたものと照らし合わせて弾いてみました。
後にアール・スクラッグスの教則本をみると、1小節目から右手の指使いが違っていました。そう言った意味ではタブ譜というものは参考になります。
しかし、もうそんなものを見ながら弾く余裕も、そんなものを書く根気もありません。当時、映像も何もなく、来日するミュージシャンを目の当たりにする機会も極めて少なかった為にしつこいほどに聴いてはコピーし、また聴いてはタブ譜をつくる、といった作業に明け暮れていました。
妥協は許されなかったのです。あくまで自分自身で、という意味ですが。
時は移り、あれからかれこれ45年ほど、うわー、すごい。(希花談)
今、アイリッシュ・ミュージックを演奏していて、よく楽譜のことを訊かれますが、そんな時僕は必ず「ないこともないけど、耳で聴いて体で覚える。もうこれしかないです」と答えます。
事実、The Sessionというサイトには数千にも及ぶ曲の楽譜が掲載されています。そしてその中のひとつの曲をとってみても、これまでに弾かれた数々のバージョンが存在しています。
僕がこのサイトを利用するのは、20年も前に演奏した曲の最後の小節を忘れてしまった、とか、タイトルの一部を忘れた、とか、そういった時ですが、それでもちょっと記憶とは違うバージョンが載っていたりします。
そんな時には、一旦楽譜をみてから、あの人はこう弾いてたな、とか、このほうが理にかなっている、などと考え、その曲に関する様々な意見や見解が投稿されているcommentsの部分を注意深く読みます。
一緒にやっていたジャック・ギルダーはこのcommentsの常連。
そしてとにかく弾いて弾いて弾きまくって自分の体の中に入れていく。それからそれらの音の進行に合わせたコード創りをかんがえる。
新たに覚えた曲などはそうしてものにしていきます。600~700もの曲を演奏していると絶対に忘れる。そのタイトルも、細かい部分も。
しかしながら、体で覚えたものは忘れにくいものです。それに引き換え、楽譜で覚えたようなものはいとも簡単に忘れてしまいます。
みんながそうではないのでしょうけど、少なくとも僕はそうです。
アイリッシュ・ミュージックはフォームとしてはとても簡単な音楽に聴こえるでしょう。しかしとても難しいものです。そして経験すればするほど、その難しさがいやおうなしに襲ってきます。
そして、その難しさが解ってしまったら…僕らが他人に教えるなんていうことは多分、100年早いことだ、と考えてしまいます。
今日もまたThe Sessionで曲を確認している。まだまだ習うべきことがいっぱいあります。
そしてまた、アイルランドで素晴らしい演奏家たちから沢山の曲を習ったり、想い出させてもらったり、結局死ぬまで習い続けるのかな。
最初、ティプシー・ハウスのメンバーとして迎え入れられた時、とりあえず200曲、彼らのレパートリーをきっちり覚えなくては、このバンドでアイリッシュ・ミュージックをやっています、なんて恥ずかしくて言えない、と必死になったものです。
その頃の感覚はいつまでも持ち続けようと思っています。
ここ40年にわたる日本の音楽事情に思うこと
40年、とはいっても、結局こんなことを思ってしまうのはここ数年のことかもしれない。
70年代初頭から音楽を職業にしてきたが、自分の大切にしてきた希少なタイプの音楽に対する姿勢は崩すことが無かった。
それもグループ(ザ・ナターシャー・セブン)の姿勢であったことはとてもラッキーだったかもしれないし、時代背景というものも忘れてはならないことだ。
当時はもう名の通ったリーダーであった高石ともや氏が、すでにこの国の音楽に対する懐の浅さ、というものをいち早く感じていただけに、僕らは彼と共に他とは違うものを創り出すことができたのだ。
彼の残した功績は計り知れないし、そこに参加できたことは大きな財産であり、また誇りに思う。
最近、ネット社会になって他人の見解などを覗いてしまう機会も増え、また、何気なしにテレビなどを見てしまうと、ずいぶん“すっとんきょう”な意見を述べている音楽関係者もいるもんだな、と感心してしまう。
少し前に亡くなった横森良造さんのことを“アコーディオンという楽器に、ダサいもの、という観念を植え付けたひと”と評した音楽関係者がいた。悪気はないのだろうし、ツイッターという短い文章を作るものだったため、他にも言いたいことはあったのかもしれないが、困ったものだ。
思うことは勝手だが、その道60年にも及ぶ先人のことだ。やはりなにかしらフォローはして欲しいものだ。
また、最近テレビをみていたら、昔デビューしたことがある歌手、という女性が、ご主人のアコーディオン奏者を引き連れて、今一度唄いたい、ということで登場した。
歌もそこそこ上手く、ご主人のアコーディオンプレイもツボを得ていたものだったが、それを聴いたレコード会社のひとりが、こういったのだ。
「とてもよかったです。どこかアイリッシュな雰囲気がして」思わず「どこがや!」とつっこんでしまった。
アイリッシュ的、という言葉が流行っているのかな。あの業界では。
また、公開されたミュージカル映画“レ・ミゼラブル”を取り上げた番組で、かなりの枠を使って作品の素晴らしさを紹介していたが、ある著名人がこう言ったのだ。
「素晴らしい映画でした。涙が止まらなかったです。これを観た後、たまらなくカラオケに行きたくなりました」
番組の終わりに出たコメントで、すべてが帳消しになってしまった。
さらに、出演者が口々に「いいですねぇ、いきましょう。これからいきますか」
あきれてものがいえなかった。ま、そう感じたのも僕だけだったかもしれないし、あまり僕もそんなことに目くじらたてるのもよくないことだろうけど、いろんなところでこの国の音楽事情には失望させられる。
と、まぁ失望してばかりでは仕方ないので、わが道をひたすらいかなくてはならないのだが、支持していただけるひとたちのためにも頑張らなくてはいけない、と思う今日この頃です。
アイリッシュ・ミュージックに於けるギター(チューニング編)
ギターというのは完璧なチューニングをすることが非常に難しい楽器だ。では完璧なチューニングとは?
僕らは(僕と希花)チューニング・メーターというものを使わない。フィドルとギターが合っていればいい、という考え方だ。
彼女が442を出す。曰く、その日のコンディションで微妙な“違い”があるそうだ。そこに合わせる。
そしてギターに於いては、それぞれの弦の音程よりも、全体のバランスを整える。そのため、自分が使うギターの“くせ”というものは熟知していなくてはならない。
いつも思うがDADGADのチューニング方法では2弦の5フレット目と(D)と1弦の開放(D)の関係が非常に微妙だ。
それと3弦2フレット目の(A)と2弦開放の(A)そしてこれをクリアしてもカポタストを2フレット目にして弾くとすでに微妙な“ずれ”が生じている。
これはなにもこのチューニングに限って言えることではないが、特にこのようなほとんどオープン・チューニングと言えるものでは顕著に現れる。
僕は自分のギターの、6弦と2弦の“くせ”を把握しておく。6弦は重要だ。キーが変わって開放から7フレット目にカポを着けた場合、その距離は相当なものになる。
もちろん、曲によっては開放のままのAポジションのほうが曲の持っているニュアンス、そしてその曲のメロディーの進行状況に適している場合もあるが。
アンドリュー・マクナマラと初めて演奏した時から、次に出てくる曲のキーだけを直前に叫んでもらい、それに合わせてカポを移動する。
その時に“くるい”が生じていたら1秒以内に直す。まず6弦を直し、曲を把握しながら他の弦も直していく。これが大変だが、決して糸巻きで直していくばかりではない。右手でピッキングしながら特定の弦を抑えたりしているのだ。
気が付いている人もあまりいないだろうが、実に巧妙に細かい調整をしている。問題はまた元のキーに戻った時、それらの調整でバラつきが出ていないかということだ。そこも考慮に入れてチューニングをする。
それはレコーディング・エンジニアですらも気が付かないほどの巧妙さだ、と言えるだろう。
事実、ジョディース・ヘブンのレコーディングの時でもかなりの曲でカポタストを移動させ、調整しながら弾いていた。
因みにその時のエンジニアは、ウイリアム・コルターというサンタ・クルーズ・エリアきっての美しいギタープレイを聴かせるギタリストだったが、全てのレコーディングが終えた後、ネタばらしをすると、彼は本当に驚いていた。全く気が付かなかったそうだ。
なにはともあれ、ずいぶん前は僕もチューニング・メーターなるものを使っていたが、結局そんなものに合わせるよりは、微妙に違うその時の弦のコンディションだったり、体調だったり、その楽器の特性だったりに合わせた方が良かったりするものだ。それに、長いこと弾いていると、大体、弦の張り具合でも分かるものだ。
後はその時一緒にやる人と合わせればいいだろう。
それでも、ケースから出してすぐに弾ける、アコーディオンやコンサルティーナはいいなぁ。ハーモニカもだ。
2月、3月のライブ予定
2月9日。名古屋のDOXYというお店に参ります。最近名古屋では5弦バンジョーがトレンディーだ、という噂を聞きました。そのむかし、パディ・キーナンとカナダのエドモントン・フォーク・フェスに参加した時、ティム・オブライエンとパディ・キーナンに囲まれてバンジョーを弾きました。アイリッシュとブルーグラスが、音楽の形として、だけではなく、見事に結びついていました。日本でもそんな風になったらいいなぁ、と思っています。
2月10日。鳥取に参ります。このデュオでは初めてです。ほとんどの人が初めて聴くスタイルの音楽になるかもしれません。主催の方々の熱い思いに応えるべく、いい音楽会にしていくことを考えております。
2月16日。京都の法然院に参ります。愛蘭(アイルランド)と和の音楽、というタイトルです。
アイルランドと日本の文化の違い、そして共通点など、音楽を通して感じていただきたいと思っております。
2月23日。東京の蒲田教会でコンサルティーナの若手ホープ、コーマック・ベグリーを招いてのコンサートです。彼の、この楽器に対する並々ならぬ情熱を目の前で感じ取ることが、そして彼のような若手ミュージシャンがいかにトラッドを大切にしているかを垣間見ることができる、またとないチャンスです
3月16日。南浦和の宮内家という一風変わった名前のお店に参ります。ここも初めてです。近郊の方、よろしくお願いします。
3月20日。横浜のサムズ・アップというところに参ります。ここも初めてです。その日は松田“アリ”幸一さんをゲストにお呼びしてアリます。数曲一緒にやってもらうつもりでアリます。僕らもデュオとしては初めての、「街の灯りがとてもきれいね横浜たそがれ」です。希花さんにはわからないでしょう。
3月23日。三島のVia701という、これまた初めてのところに参ります。静岡県人である僕からも是非よろしくお願いします。
3月24日。東京の大森にある“風に吹かれて”で松田“アリ”幸一さんとの、今度は横浜とは違ったかたちのコンサートを行います。恐らくレパートリーも3人の絡みも全く違うものになるでしょう。
3月28日。岡崎。3月29日。中津川アーニー・ホール。3月30日。常滑。この3か所はアリさんとのトリオです。
今現在このようになっております。また他にも小さな会があるかもしれません。その都度お知らせいたします。ライブスケジュールの方も合わせてご覧ください。
ザ・ナターシャー・セブンとその時代背景 1
1971年、1月。高石ともや氏と出会った。ちょうど同じ時期、ブルーグラス45の2代目がアメリカ・ツァーをするので、バンジョーで参加して欲しい、という依頼があった、と記憶している。僕の記憶が確かなら、僕の代わりに黒川君というとても上手いバンジョー弾きが行ったと思う。
何と言っても、もう40年以上前のことだ。そうそう覚えていない。だが、この話はちょうどナターシャーをやり始めた頃にぶつかっている、という点に於いて、とても似た話しが僕にはあるので、確かである。
その似た話しというのは…ちょうどアイリッシュを始めた時、ピーター・ローワンから電話があり、新しいプロジェクトでバンジョーを弾いてくれないか、ということだった。
今はアイリッシュにぞっこんだから、と言って断った。1991年のことだ。
さて、ナターシャーの話に戻ろう。
みなさん知っているように、高石氏は当時、すでに高名なフォークシンガーであったが、やはり根っから音楽が好きな人である。
お金とかいうものにはかなり無頓着な人だ。名声というものはこの商売に関わる人にとっては魅力的なものだ。それは当り前のこと。
ただ、彼がキャリアを一旦捨てて、本当のフォークソング探しの旅に出たことが、後にナターシャー・セブンを生む事になったのだから、“富も名声も捨てて”という表現があてはまるのだろう。
事実、ナターシャーの初期「高石ともやは気が狂ったか」と評した人達もいたそうだ。そして、ブルーグラスを日本語で唄うという事に対しても「もうすでにブルーグラスではない」「ブルーグラスをバカにしている」などいろいろあったものだ。
だが、僕や坂庭君は気にもせず、高石氏の素晴らしいアイディアを追従しながら、とことんトラッドな20年代のスキレット・リッカーズやリリー・ブラザース、モリス・ブラザースなどにも聴き入り、自分たちなりにブルーグラスやオールドタイムも研究していた。
ニュー・ロスト・シティ・ランブラーズもしかりだ。思うに高石氏も僕も坂庭君も、うわべの音楽が嫌いだったのだ。
ちょうど当時、ニッティ・グリッティ・ダート・バンドとクロスビー・スティルス&ナッシュ(ニール・ヤング加入前)のアルバムが出た頃で、たしか高石氏のお気に入りの二つであった。特に、ニッティ…ではフィドルとバンジョーのジョン・マッキューエンがひと際彼らの音楽にスパイスを加えていた。いや、カントリー・ロックの中にブルーグラス魂を開花させていた。それは、当時多く存在した、どのカントリー・ロック・バンドとも違うサウンドを生みだしていた。
そして、こんな音楽でありたい、というのが高石氏の口癖だった。
僕が当時良く聴いていたのは確かピ-ト・シーガーの“ウィー・シャル・オーバー・カム”というタイトルのライブ盤だった。なんか逆みたいだが…。そんなものをまだ、クライマックスで売れまくっていた坂庭君が加入する前に高石氏と二人でよく聴いたものだ。
そして、ある時アメリカから里帰りした元ブルーグラス45の大塚あきらさんとバッタリ東京駅で出会った。その時に彼が持って帰ってきたアルバムの中に“ニュー・グラス・リバイバル”のデビュー盤があった。
今のブルーグラスで一押しだ、という彼の言葉を信じて早速購入。そして、針を置いたとたん体中を稲妻が走ったようだった。火の玉ロックから始まったそのアルバムにはまさにぶっ飛んだ。
時に、ほとんどリアル・タイムで日本に到着したニュー・グラスの幕開けに、僕らも必死になって“ロンサム・フィドル・ブルース”をコピーし、演奏したものだ。
後になって、事実上のリーダーであるサム・ブッシュが参加していた69年頃のバンド“プアー・リチャーズ・アルマナック”を聴くことにより、彼の素晴らしいトラッド志向と限りなく幅広いアレンジ能力を知るのだ。
1972~3年。ナターシャー・セブン初期のこと。ほどなくして、ボシー・バンドやディ・ダナンのレコード盤と出会うことになる。
ザ・ナターシャー・セブンとその時代背景 2
初めて高石氏と練習した曲は“Roll in my Sweet Baby’s Arms”だったと記憶している。そう、“あの娘のひざまくら”だ。
ニュー・ロスト・シティ・ランブラーズや、バスター・カーター&プレストン・ヤングを参考にして、何度も何度もくりかえし歌った。
当時、まだ僕は日本語で歌う、ということ、特にブルーグラスではそのことに慣れていなかったので、なんか変だなと思ったことも事実だ。多分、大学時代にさんざん英語で歌っていたものだから、だろう。
もちろん、‘66年頃の“バラが咲いた”から始まった日本のフォーク・ブームだったし、いくつかのフォークソングは日本語でも唄っていた。高校時代のバンドではオリジナルもよく作ったものだ。
ちょっと昔話。最初に聴いたフォーク・グループは“ブラザース・フォァ”だった、と記憶している。
まだ小学生の頃、“遥かなるアラモ”という映画を観るために東京まで出かけて行った。その時Dm~Dmajorという進行で美しく唄われた“The Green Leaves of Summer”は後に僕がギターを手にした時の最初の課題曲だった。
やがて、バンジョーを手に入れると、その演奏技術がもう少し高かった“キングストン・トリオ”へと移行していったが…。
当時は“ハイウェイメン”“タリアーズ”“トラベラーズ・スリー”それに少しあとになって“モダーン・フォーク・カルテット”などをよく聴いていた。
余談だが、“トラベラーズ・スリー”のレコードジャケットを虫眼鏡で見て、バンジョーのピックの付け方を研究したものだ。
ナターシャーを始める少し前は“モダーン…”とブルーグラス、オールドタイミーをミックスしたようなバンドを作っていた。
その当時は、ジャンゴの“ホット・クラブ・オブ・フランス”もよく聴いていたうちのひとつだ。
“モダーン…”は当時のフォーク・グループでは珍しく、コーラスが“フォァー・フレッシュ・メン”ばりのジャジーなものだったが、かなり忠実にコピーした。
コーラスのパートひとりひとりの音階は面白いように飛んでいる。今までの僕らの常識では考えられなかった。高校時代から聴いてはいたが、正式にコピーし出したのは‘69年から‘70年にかけてくらいだろう。
京都産業大学ブルーリッジ・マウンテン・ボーイズで先輩と喧嘩してグループをぬけることになる前後かな。
大学では法学部(京産では別名“ぁ法学部”)に在籍していたが、ブルーグラスを演奏するために行っていたようなものだったので、将来何をするかも考えていなかった。
音楽で生活をすることも考えていなかった。もし、母親があんなに早く亡くならなければ確実にピアニストの道を選んでいただろうけど。
そんなときに高石氏と出会ったわけだ。あの娘のひざまくら~と唄いながら、変だなぁと感じつつも、これは面白いかも、って思っていた。
やがて三木トリローの“サン・サン・サン”や“近江の子守唄”などもレパートリーとして取り入れた。
もちろん“Foggy Mountain Breakdown”も。そして、日本語で唄う、ということにもだいぶ慣れてきた。
高石氏の歌は、人々の心の奥深くまで感動を与えるほどの魅力あふれるものであったし、僕も彼と出会ったことで音楽観が変化していくだろう予感がした。
いろいろ変わった人達とも共演した。イッセー尾方、ツノダヒロ、なぜかアイドル歌手の渋谷哲平と仲が良くなった。岩崎宏美とも仲良しだった。
小沢昭一、野坂昭如、永六輔、若林美宏(11PMのベッド体操の人)浅川マキ、などとも一緒に出演したものだ。
野坂さんが僕らの楽屋に来て「新人歌手の野坂です」とすっとぼけた挨拶をして出て行ったこともあった。
浅川マキさんと同じ楽屋になった時「あたしが化粧を落とした顔を観たのはあんたたちが初めてよ」とすごまれた。
若林美宏が突然ステージで素っ裸になったのには度肝を抜かれた。あれはどこだっただろう。渋谷公会堂だったかな。超満員のお客さんは一瞬言葉を失った。他の出演者もスタッフもオロオロするばかり。
しかし、あまり見事すぎて、そして自然発生すぎて、大胆すぎて何が起こったのか分からないくらいに時間が過ぎてしまった。“ワイルドだろぉ~”どころではない世界だ。
まだ初期の頃、僕らは高石氏の文化人としての活躍ぶりに目を見張るばかりだった。
ザ・ナターシャー・セブンとその時代背景 3
1973年後半から坂庭省悟が加わった。クライマックスでさんざん売れた後、もうこりごり、と大学に戻った彼をまんまと引きずり込んだかたちだ。
彼との出会いについては、もう多くの人が知っているはずだ。京都産業大学で共にバンジョーを弾いていた。
彼は“ザ・マヨネーズ”というフォーク・グループ。僕はブルー・リッジ・マウンテン・ボーイズだ。
よく僕の部室に来ては一緒に弾いたものだ。彼もブルーグラス・バンジョーに大きなあこがれを抱いていた。そんな中で印象深かったのは、彼の弾く小気味よいリズム・ギターだった。
ちょうど映画“卒業”が流行っていて、主役のダスティン・ホフマンが赤いスポーツカー(発売されたばかりのアルファ・ロメオ・スパイダーらしい)を走らせているとガス欠になって、徐々にスローダウンして車が止まってしまう。
そのシーンでギターのカッティングが段々ゆっくりになっていくのを、ものの見事に楽しそうに再現していた。
アイビールックに身を包んだ彼は、まるで映画のシーンそのもののようにうれしそうに弾いていたものだ。
やがて音楽に関する熱い思いを語り合うようになる。
加茂川の河川敷で夜通し“Earl’s Breakdown”を弾いたこともあった。あの、エリック・ワイズバーグとマーシャル・ブリックマンのダブル・バンジョーのコピーだ。
彼は無類のリズムおたく。僕は無類のコードおたく。ちょうどいい組み合わせだった。
かくして、ザ・ナターシャー・セブンは、いわゆる社会派フォークシンガーとして突出した高石氏、エンタティナーとしての限りない才能を持ち、リズム感に優れた坂庭省悟、そして僕とで、他に類を見ない、それこそまわりのほとんどが、オリジナルで世に出るのが個性であり、売れることが音楽を目指す者の使命だと思っている中、トラッド志向を大切にした稀有な存在として日本のフォーク界に一石を投じたのだ。
僕に於いてはその信念は今も変わっていない。自分がもしブルーグラスを、アイリッシュを愛しているのなら、そしてそれらに生かされているのなら、どんな苦しみをもそれらの為に捧げたいし、今日よりは明日、そしてその次の日も研究を惜しむわけにはいかない。トラディショナルに身も心も捧げる者の宿命だ。
それは高石氏の提案した107ソング・ブックを見ても分かる通り、やはり元のかたちを知ろうとする気持ちが無ければ、うわべだけの新しいものになってしまう。
今、107ソング・ブックを読み返してみると、よくこんなものを作ったな、と感心させられる。
ラジオの深夜放送が終わってから、また、ツァーから戻ってきては、地味な糊づけをし続けた。来る日も来る日も。
くしゃみもできない。せきもできない。印刷屋に頼めば簡単なことを自分たちの手で作り上げたのだ。
もっとも、監修者の笠木透は、これしか方法は無いと言っていた。ぼくらは、じゃぁ仕方がないな、と彼を信じた。でも実際はもっと簡単にできる方法はいくつかあった、と後できかされたのだ。
でも彼曰く「苦労して作ったものほど愛おしいものは無い。この日々をわすれてはいかんぞ」
そうして出来た本をそれぞれに30冊ほど持って売りに歩いた。文字通り北は北海道から南は九州、沖縄まで。
自分たちの知らないところで、自分たちの作ったものが、知らない人に買われるよりも、買ってくれた人の顔を見て、話を聞いて、そうして世に送り出してあげようじゃないか、という考えだ。
なんでこんなことをしてまでも、という気持ちは正直あったが、その経験は音楽上でも生かされているだろう。
未だにそのころのザ・ナターシャー・セブンの思いを胸に抱いてくれている人達、共有してくれている人達が日本全国に一杯いる。そんな人達に感謝すると同時に、107ソング・ブック作りを提案した高石氏の音楽に対する一種生真面目さにも、そして製本のために苦労した仲間達にも、みんなに感謝だ。
ステージ作りに関しても、高石氏は他に真似のできないものを持っていた。もちろん、そこには僕と省悟という稀有な存在が必要不可欠であっただろうが。
間違いなく、ザ・ナターシャー・セブンの黄金期は1973年から始まっていたのだ。
ザ・ナターシャー・セブンとその時代背景 4
1974年になると月に20日も外に出ることもあった。それでも新幹線の連結部分では必ず練習に励んだものだ。
今だったら騒音防止法とかいうものがあるのだろうけど。それでもさすがにバンジョーは練習しなかったかな。
省悟と二人で、マンドリンとギターを出してビル・モンローの曲やドック・ワトソンの曲など、よく弾いていた。
青函連絡船の甲板でも弾いた。本当に疲れている時でも、いつもいつも「ここ、こうしようか」「このほうがいいんじゃない?」なんていいながらやっていたものだ。
そしてお互い家に戻ってからも、電話で「さっきのあれ、こうじゃないか?」なんていいながら、肩で受話器を抱えて弾いたものだ。
僕らはコンサートの中でも必ずそれなりの曲(漠然としたいい方だが。受ける受けない関係ないという意味で)を数曲やらせてもらった。
ビル・キース、デビッド・グリスマン、ダン・クレイリー、様々なインストゥルメンタルをやりながら、日本語のブルーグラスをつくりあげていった。
日本民謡もずいぶんやった。高石氏が持ってくる多くのアイディアを僕らがアレンジしてかたちにしていった。
それらのいくつかは、今でも演奏させてもらっている。どこへ行く時もその土地のことを意識する、というのは素晴らしいことだ。
そして、今、僕らがアイルランドで演奏する時もそういったレパートリーを持っていることが自分のアイデンティティ-を明確にする上でとても役に立つのだ。
去年(2012年)のアイルランド、フィークルのペパーズというパブでアンドリュー・マクナマラと演奏した時のことだ。
アンドリューは鉄砲獅子踊り歌が大好きで、もう随分前から(多分15年くらい前から)一緒にやっている。とても覚えにくい節回しらしく、4文字言葉を連発しながら練習に励んでいたものだ。
彼は必ず僕に、唄ってくれ、とせがむ。そして本当に嬉しそうにアコーディオンをかき鳴らす。
そして2012年の夏。午前3時頃、最後の曲でお開きになった直後、みんなになんでもいいから日本の古い歌を聞かせてやってくれ、とアンドリューが言った。
いろいろ迷ったが、僕は“そでやま節”を唄った。その時、パブが一瞬水を打ったようになってしまった。大体、歌が始まると礼儀として静かにするものだが、ほとんどの人達が、明らかに異文化に触れている不思議な感覚を味わっている、という顔をしていた。
1984年にジャネット・カーターと、ヴァージニアの小さな小学校を訪れた時、ジャネットの唄う“School House on the Hill”をそのまま日本語で「背よりも高い~」と続けた時の子供たちの驚き様は今でも鮮明に覚えている。
フィークルではその時と同じような感覚だった。
これらの歌は、もし高石氏の思い描くザ・ナターシャー・セブンをやっていなかったら自分のレパートリーには無かったものだ。
初代高橋竹山の元を訪れたのはいつごろだったか。76年のよいよい山コンサートで、竹山師匠をゲストとして呼んでいるし、その前にも75年には何度かご一緒させてもらっているので、74年くらいだったかもしれない。
僕と省悟の二人で青森の小湊という小さな町に降りたった。
当時、弟子をとらないことで有名だった竹山師匠の元に、拝み倒して弟子にしてもらったという、東京から来た18歳くらいの女の子がいたが、それが今の2代目高橋竹山だ。
僕はバンジョーを師匠に渡し、僕が師匠の三味線を弾かせてもらった。そこで津軽じょんがら節のセッションとなったのだ。
情けないことに日本人であるはずの僕でも、日本の民謡は覚えにくい。アイリッシュの曲だったら500~600、苦でもないのだが。
そうして3日ほど泊めていただいて僕らは北海道へと渡り、また演奏に出た。
時に、ザ・ナターシャー・セブン、もう京都では知らない人がいないくらいの、押しも押されもせぬ大スターだったが、地方に行けば誰も知らなかった。
また青函連絡船のデッキで練習をしたが、新しく津軽じょんがら節もレパートリーに加わっていた。
全てはザ・ナターシャー・セブンで得た大きな財産だと言える。
ザ・ナターシャー・セブンとその時代背景 5
1975年初期になると、メンバーに木田たかすけを加え、さらにバンドとして厚みが増してきた。
木田たかすけは見事にそれまでのナターシャーサウンドに溶け込んでくれた。
もちろん、音楽に関しては何もかもお見通しの彼だったが、非常に寛容で、あれだけポップスの第一線で活躍していたのにブルーグラスにも鋭く反応してくれた。
彼はナターシャーに入るまでベースを弾いたことはなかった。なんの楽器でもそうだったが、「ちょっと待っててね」と言って、考え事をすること10分程。「よし、じゃぁいこうか」
どこかでイングリッシュ・コンサルティーナを買って来た時もそうだった。もちろん、流暢に弾くわけではないが、簡単な音階はアッと言う間に弾いていた。
ティン・ホイッスルの時もそうだった。手にして10分後にはレコーディングにまで使っていた。
「こういうもんは雰囲気だから」柔和な笑顔でいつもそんな風に言っていた。
かくして、歌い手として、またショーマンとしても超一流である高石ともや、フラットピッキング・ギターの名手でコメディ・センス抜群のハスキー・ボイス坂庭省悟、編曲家として高名であり、幅広い視野を持つ木田たかすけ、そして僕という、前代未聞の組み合わせのバンドが完成した。
ザ・ナターシャー・セブン第2期黄金時代の幕開けだ。第1期と第2期があまりに近すぎるような気もするが、細かいことは抜きにして…。
そしてこの頃になると当時の売れっ子バンド“ダウン・タウン・ブギ・ウギ・バンド”ともよくツァーをすることがあった。
一見(一聴)全然関係なさそうだが意外と共通点があった。ギターの和田は静岡市に住んでいたことがあるらしく、ローカルな話題に華が咲いた。彼が良く言っていた言葉を想い出す「フォークはいいなぁ。歳が言ってもそれなりに出来るし。でもロックはいつまでもやってられないしなぁ」体力的なことを言っていたのだろうけど、どうして、どうして、まだまだ現役だ。
宇崎さんはカントリーもこよなく愛し、“ブルー・ムーン・オブ・ケンタッキー”を僕らと一緒にやったりした。途中で何故か“月の法善寺横丁”に変わっていってしまうのだ。
鼻にティッシュ・ペーパーをいっぱい詰めて“ほうちょういっぽん、さらしにま~いて~」と唄う様は見事だった。
そんなふうにがっぷり組んでのジョイント・ツァーは結構続いたものだ。ダウン・タウン・ブギ・ウギ・バンドを聴きに来て、半ば事故のようにザ・ナターシャー・セブンという、海のものとも山のものとも分からぬグループを見てしまったおかげで、今もバンジョーを弾き続けているひともいる。
野球もそれぞれにチームを作ってやったものだ。
そういえば、ビル・モンローも野球チームを作っていたんじゃなかったかな。他にも松山千春チームというのもあったな。もちろんコンサートでもよく一緒になったものだが、野球での彼は、当時読売ジャイアンツにいた新浦から教わった、という“フォークボール”でバッタバッタと三振の山を築いていた。僕も2三振食らった。
そんな人達とのジョイントも、木田たかすけという有能なアレンジャーがいたからこそ、音楽的にも楽に物事が進んでいったのだろう。
1980年、バンドを離れて、再度アレンジャーとしてスタートしはじめていた木田たかすけが事故で亡くなった。
そのすぐ後、松山千春と野球をやった。 彼が僕の肩を抱くようにして言った「残念だったね。お互い頑張ろうね」
すでにバンドを離れていたとはいえ、木田たかすけは、それから先のザ・ナターシャー・セブンにも多大な影響を与え続けたメンバーだ。
ザ・ナターシャー・セブンとその時代背景 6
グループも、もはや破竹の勢いで邁進していた。
思えば、結成当時は、高石ともや29歳、僕は21歳だった。すぐ後に高石氏が30歳になり、19歳の金海たかひろをメンバーに迎えた時、3世代揃ったバンドだ、と言っていた。
確かにほとんどのフォーク・グループが同じ世代で構成されていた事を考えると、それだけでも珍しい存在であったかもしれない。
そこにもってきて、他のグループが成しえない編成で(あくまで、レコード会社に所属するプロのミュージシャンという意味で)他のグループが取り入れることのない形態の音楽を演奏し、なお且つエンターティメント性溢れるステージ、ということになるとある意味最強だ。
しかも、意固地になって京都から全てを発信している。これは高石氏の素晴らしいこだわりであった。なにも全てが東京に行く必要はないのだ。
今でこそ当たり前の考え方だが、当時は少し名前が出るとみんな東京に移り住んだものだ。また、それでなければ仕事にならなかった一面もある。
でも、本当にいいものだったら別に東京にいなくたって、逆に東京のひとが聴きに来ればいいじゃないか。
毎年やっていた春、秋の昼下がりコンサートでは、修学旅行の学生たちがなにも気付かずに通り過ぎるのに、舞妓さん達が「あっ、ナターシャーがやったはる」と口ぐちに言って行くくらいだった。
かくして、京都をベースにした僕らを、京都の人達、また、特筆すべきは、高校生や中学生が厚く支持してくれた。驚くことに70年代中期には、京都のどの高校にも、ひとクラスに3~4人はバンジョー、マンドリンを持った子がいた。
そのうちのひとり、進藤さとひこが後のベースマンとなるが、最初はバンジョーを弾いていた。
どこから見ても育ちの良さそうな、か弱い中学生だった彼も、僕と省悟の“愛のムチ”で、驚くほどの成長ぶりをみせた。余計な部分でも…かな。
そして、‘84年に僕が抜けたあとも、彼は坂庭省悟とともにザ・ナターシャー・セブンの重要なメンバーとしてその地位を確立していった。
世の中の音楽事情は、というと、全てがデジタル化されてきたようで、どこか味気なかったような気がする。
それはなにも日本に限ったことではなかったが、日本ではフォーク・ソングというものが明らかに歌謡曲となっていった。
ザ・ナターシャー・セブン結成当時からよくイベントに一緒に出ていたフォーク歌手たちはいつしか演歌歌手となっていき、ニュー・ミュージックなどと訳の分からない呼び名で持て囃されていた。
もちろん、それで稼いでいるわけだし、お金は沢山作れるほうがいいだろう。だが、それがフォーク歌手と言われてしまうことが不思議だ。
僕にはフォークっぽいものや、ブルーグラスっぽいもの、それにアイリッシュっぽいものは馴染まない。
おそらく、ザ・ナターシャー・セブンが世に出た頃、ブルーグラスをこよなく愛する人達はブルーグラスっぽいものとして僕らの存在を嫌ったのだろうが、高石ともやは本物の筋金入りフォークシンガーだった。
彼はブルーグラスもオールド・タイムもフォーク・ソングも、すでに遥かに越えた彼独特の世界をその歌唱力に中に持っていた。彼は間違いなくパイオニアだ。
坂庭省悟はドック・ワトソンやクラレンス・ホワイトをこよなく愛し、フラットピッキング・ギターを弾かせたら、これまた坂庭省悟独特の世界でありながら、常に彼らのスタイルの研究に励んでいた。
そんなグループであったから、世の中がいくら変わってもそれまでの姿勢を崩すことはなかった。
それでも当時のレコード会社は売る気でいたんだろうなぁ。そのへんのことは僕にはよく分からないけど、そんな矢先にマネージャーが亡くなった。
1982年のことだった。思えば彼が、京都で音曲に親しんでいる若者たちの中から僕を選んでくれたのだ。
そんな意味では、僕にとってのザ・ナターシャー・セブンはその時に終わりをみていたのかもしれない。
ザ・ナターシャー・セブンとその時代背景 7(最終回)
本当は最初に書くべきことかもしれないけど、敢えてこの最終回に書いてみようかな、という事柄からまず始めます。
高石氏が住んでいたところ、福井県、当時は遠敷郡名田庄村といっていたが、今は合併されて名前が変わっているそうだ。
初めて名田庄村を訪れた時、これから吹き始めるだろう新しい風をまだ感じることはできなかった。
大学にも、ろくに行っていない中途半端な学生気分だったのだろう。
でも、来る日も来る日も、近くのお不動さんの滝のところまで山道を歩いては、声を出して自然の中からかえってくる自分の声に耳をすませた。
今、演奏しているアイリッシュ・ミュージックも同じだ。自分の演奏は自然の中に溶け込んでいかなくてはいけない。それでこそ音楽を演奏している、といえることだ。多くのアイリッシュ・ミュージシャンから後に学んだことは、今思えば1971年から体の中にいれていたのかもしれない。
山の彼方からかえってくるカーター・ファミリーソングの数々。それに、バンジョーの小気味よい音も、マンドリンのトレモロも、ギターのベースランも、みんなみんな山の中に吸い込まれて、そうして、かえってくる。
フォークソングの真の姿がそこにあった。いや、全ての音楽の真の姿がそこにあった、と言えるだろう。
名田庄村から始まったザ・ナターシャー・セブン。世に名前が出てくると、普通の音楽に物足りなさを感じていた若者たちが、まるで名田庄村を聖地のように訪ねてきた。
確かに、その時代背景の中にあって、他に類をみないグループであった。本当に高石氏という稀有な存在がなかったら、僕らも開花しなかっただろう。
そして、数多くいたブルーグラスの演奏者たちのなかから、これはなにかを持っている、新しい風を起こすことができるかもしれない、と感じて僕らを起用してくれたことに於いても、並はずれた感性を持ち合わせていた、と思わざるを得ない。
実際、多くのフォークイベントにも参加したが、僕らのようなスタイルは皆無だった。そういう時代からずっと日本の音楽界に感じることは、誰かみたいなサウンド、というものが多すぎることだ。
ナターシャーの最初のころ、よく高石氏が言っていた。「お客さんは、アール・スクラッグスも、ジョン・マキューエンも知らない。知っているのは今目の前にいるあなただけだ」
そして、それはアメリカでアイリッシュを始めた時もずっと意識してきたことにつながっていった。
最近面白い話を聞いたが、ある友人のハーモニカ・プレイヤーの教室に、他でも習っている、という若者が訪れたそうだ。
そして、まず、なにか吹いてみてくれ、というと「オリジナルです」といって訳の分からないものを吹き始めた。そこで「例えば、ブルースのスケールのようなものはどう?」と訊くと「それってなんですか?」という答えがかえってきたそうだ。
他のところでは「まず、オリジナルを作れ、と教えられた」ということらしい。
オリジナルというのが、果たしてオリジナリティーだろうか。もちろん、僕にしても多少のオリジナル作品はあるが、それは当然のことだろう。
ナターシャーにもオリジナル作品は数多くある。
だが、音楽に於いて本当のオリジナリティーというものは、そのサウンドを聴いた時、他の誰でもない、という音を提供できるかどうか、ということだろう。
並みいるマンドリン弾きの中でも、サム・ブッシュの音は明らかに違う。デビッド・グリスマンもそうだ。ジェスロ・バーンズも。B・Bキングの歌とギターは…とにかく、音に歌に個性が溢れ出ている。
ザ・ナターシャー・セブンが1971年からずっと追い求めていたもの、そして数多くの人達を惹きつけてきた理由は、ザ・ナターシャー・セブンでしかない何かが確実にあったからだといえる。
‘84年までしか分からなくて申し訳ないが、井芹まこと(フィドル)蓑岡修(ベース)山本よしき(ベース)北村けん(ベース)金海たかひろ(マンドリン)伊藤芳彦(ベース)木田たかすけ(全て)兼松豊(パーカッション)進藤さとひこ(ベース)そして、大学時代からの無二の親友だった、坂庭省悟(いろいろ)これだけの人達が、ザ・ナターシャー・セブンとして一緒に唄い、演奏した。
今僕は、ナターシャーで得たお金には代えがたい財産と、新たな音楽パートナーとで、他の誰とも違う音楽を目指している。
同じアイリッシュを演奏していても、最もシンプルな「フィドルとギター」という、決定的に難易度の高い組み合わせをどう表現するか。
ナターシャーで唄ってきた歌を自分たちの基本であるアイリッシュ・ミュージックと、どう組み合わせて他と違うものを創り出していくか。
ピアノから音楽を始めて、かれこれ60年、今までに聴いてきた音楽、演奏してきた音楽をいかに自分のスタイルにしていくか。
まだまだ課題は山積みだが、ザ・ナターシャー・セブンで培ってきたものは、今また新たなパートナーと共に、自分の中でふくらみつつある。
高石ともや氏、そして、マネージャーであった故榊原詩朗氏に、そして僕らの為に働いてくれたスタッフの面々に、そしてもちろん、あの時代、どこにもなかったへんてこなサウンドを支持し、そして今でもその気持ちを変わらず持ち続けておられる皆さんに深く感謝いたします。
また、なにか思いついたら書きますが、ひとまずこれで終わり。
Cormac Begley上陸
ネッシー・エクスペディション
久しぶりにわくわくする気持ちでCDを購入した。試聴させていただいた彼らの演奏があまりに力強く、素晴らしかったからだ。
ネッシー・エクスペディションのそれは、1976年に録音されたものらしいが、勿論その当時も聴いていたものである。彼らは東京のブルーグラス・シーンでは、今もベテラン・バンドのひとつとして演奏している。
このアルバム、最初から度肝を抜かれる。そして最後まで、全27曲も入っているが、どれも力強く、ブルーグラスの魂であるハイ・ロンサムがひしひしと伝わってきて、本当に心からの感動を呼ぶ。
彼らの歌や演奏のテクニックもさることながら、やはりそういうところに目が(耳が)いきがちな若いころとはまた違う、彼らの“本気ぶり”にこちらも歳と共に気が付かされたのかもしれない。
このアルバムのCD化を実現させてくれた皆さんに感謝すると同時に、情報が少なかったあの時代に、こんなに素晴らしい演奏を残してくれたバンド・メンバーにも、心からの「ありがとう」を言いたい。
ブルーグラス・ミュージック
今まで、ほとんどをアイリッシュ・ミュージックについて書いてきたが、自分のひとつの歴史であるブルーグラスについてすこし書いてみよう。
バンジョーという楽器を始めたのはフォークソングからだった。1964年か65年くらいだったと思う。
ピアレスという日本製のバンジョーは確か15000円くらいで、当時としては目の玉が飛び出るくらいの値段だった。他にナルダンという会社のものもあって、12000円くらいだった記憶がある。
ピアレスのほうが、音にメリハリがあるような気がして、そちらを選んだのだと思う。なんといってもバンジョーなる楽器にそうそうお目にかかれる時代ではなかっただけに、よくは分からなかったのだが。
とにかくブラザース・フォアをお手本にしてポロポロと弾いていたが、幾つかの彼らのレコーディングで衝撃的な音を聴いた。
ダーリン・コリーという曲でイントロからずっと流れているバンジョーは明らかに違っていた。
解説には「ご機嫌なバンジョーはマイク・カークランド」となっていたが、どうも疑わしかった。
後にだれかが「あれは、グレン・キャンベルだ」と言ったり「エリック・ワイズバーグ」だ、と言ったりしたが、本当のところは僕には分からない。
そして、当時はそれがブルーグラス・スタイルのバンジョー・プレイだということも知らなかった。
それからキングストン・トリオを聴くと、もう少し音がバラけていて細かい動きをしているように聴こえた。だが、まだブルーグラスではなかった。
そしてその頃はアリアというメーカーのロングネック・バンジョーを使っていた。ロングネックはもちろん、ウィーバースやクランシー・ブラザース以来、ほとんどのフォーク・バンジョー奏者が弾いていたものだ。
ほどなくしてフォギー・マウンテン・ブレイク・ダウンを聴いたときの衝撃は、とても文章で言い表せるものではなかった。
これは間違いなく2~3人でよってたかって弾いているに違いない。あるいは回転数を間違えたか…、などと思ったりしたものだ。
大学に入学するすこし前にフォギー・マウンテン・ボーイズを東京まで観にいった。そうか、これこそがブルーグラスか。大学ではこれをやろう、と心に誓った。
そして、入学したその日からバンジョーを持って、構内を歩いたところ、数人の先輩と思しき人から声をかけられた。
京都産業大学ブルーリッジ・マウンテン・ボーイズの初代の人たちだった。バンジョーが酒井さん、フィドルが松井さん、ギターとボーカルが細谷さん、そしてベースが山本さん。マンドリンにあまり目立たない人があとから少しの間加わっていた記憶もある。
ビル・モンローはもちろんのこと、フォギー・マウンテン・ボーイズ、スタンレー・ブラザース、レノ・アンド・スマイリー、オズボーン・ブラザース、ジム・アンド・ジェシー、ジミー・マーティン、それらが人気だったあの時代。
アメリカ文化センターという、たしか四条烏丸あたりにあった場所で、毎月一回ブルーグラス・コンサートが開かれていた。
常連は、立命館のサニー・マウンテン・ボーイズ、同志社のマリース・ロック・マウンテニアーズ、そしてわが産大のブルーリッジだ。時々ブルーグラス45や、桃山学院ブルーグラス・ランブラーズなんかも来ていたかな。京都大学にもグループがあったなぁ。
産業大学では、僕がエディ・アドコック好きだったので徐々にカントリー・ジェントルメンのレパートリーが増えていった。
当時の僕のアイドルはエディともうひとり、ビル・キースだった。全く違うスタイルの二人だったが、エディのギャロッピングとシングル・ストリングの早弾きと、ビルの滑らかなメロディック奏法はどちらも魅力的だった。
とにかく来る日も来る日も、耳に入るものは全てコピーしまくった。まだ若かったから根気もあっただろうし、脳みそも柔らかかったのだろう。いちど聴いてすぐそれなりに弾いたりしたものだ。
楽譜があるわけでもない。実際に弾いているところが見れるわけでもない。頼りになるのは自分の耳だけだ。
そうして勉強もほとんどせず、大学時代を過ごしたが、以後、日本にも多くのブルーグラス・バンドが来日するようになった。
スタンレー・ブラザース、カントリー・ジェントルメン、ジム・アンド・ジェシー、デル・マッカーリー、ジミー・マーティン、ピーター・ローワン、J.D・クロウ、セルダム・シーン、ニュー・グラス・リバイバル、レッド・レクターや、ブルーグラスともちょっと違うけど、リリー・ブラザースも来ていた。もちろんビル・モンローもだ。
75年には衝撃のデビッド・グリスマンも。
ブルーグラスは徐々にその全貌を見せていった。本物のトラッドから、ニュー・グラスまで。
しかし、そのニュー・グラスの演奏者の誰もが、素晴らしいトラッド追従者であったことは印象的なことだ。
思うにブルーグラスの演奏家たちは、例えばバンジョー弾きは、アール・スクラッグスを出来る限り忠実にコピーすることから始まるような感があるし、フィドルはテキサス・スタイルにせよ、バージニア・スタイルにせよ、ケニー・ベイカーやテーター・テイトなどをとことん研究することから始まるような感があるし、マンドリンはやっぱりビル・モンローだろう。
歌とギターはレスター・フラットでドブロはアンクル・ジョッシュ、ベースはセドリック・レインウォーター、あるいはトム・グレイか…、もちろんあくまで個人的な見解だが。
それにひきかえ、アイリッシュはたとえば、クラシックをやっている人が興味を持ったら楽譜でも見ればその日のうちに弾くことが(吹くことが)出来るものだ。ところがそこが大きな落とし穴だ。
希花が研太郎に初めてあったとき、希花のブルーグラスをじっと目をつぶって聴いていた研太郎が「ブルーグラスはもっといい加減に弾いたらいいよ」と言ったのが印象的だった。
こう書くと、また誰かがこの言葉だけに反応して何か言いそうだが、僕にはその言葉の深い意味が凄くよく分かる。
希花のように、アイリッシュにおいて、どれほどにトラッドを体の中に入れなくてはいけないかを学んでいると、生半可なことは出来なくなってくるもんだ。
そこを敢えて「いい加減に」というのは、ジャンルの違いであれ、とことん体にその景色と音を入れてきた男が言える言葉だ。
だから、決してアイリッシュはいい加減ではいけなくて、ブルーグラスはいい加減でいい、などということではない。
彼の言葉の意味が分かるようになるには、おそらく何十年もの間、この音楽に身も心も捧げる努力を惜しまなくてはならない。
まだまだ若い希花のこれからの課題のひとつである。
また、研太郎はテキサス・スタイルとバージニア・スタイルの違いなども聴かせてくれた。
日本のブルーグラス・フィドラーの中でも、もっともブルース・フィーリング溢れる演奏をする男だ。
アイリッシュにもブルーグラスにもブルース・フィーリングは不可欠だ。淡谷のり子先生もそう言っていた…(?)ズロースの女王、と間違い表記されたこともあるらしいが。
ブルーグラスにおいては、70年代から始まったニュー・グラスの嵐、そして、80、90、2000年とずいぶん変わってきたが、若い演奏家たちがとんでもない音のシャワーを浴びせながらも、とことんトラッドもやってのける。
日本のブルーグラス演奏者たちにもそんな心意気を感じる。それはアイリッシュの世界よりも顕著かもしれない。
ルナサやソーラスは確かにかっこいい。しかし忘れてならないのは、かれらは一同に素晴らしい伝統音楽の継承者なのだ。
同じようにサム・ブッシュやトニー・ライスはめちゃくちゃかっこいい。だが、かれらは一同にビル・モンローの音楽を最も大切なものとしている。
日本ではアイリッシュよりもブルーグラスの演奏者たちのほうが、その辺の大切さがわかっているように思えてならない。
さて、84年、アメリカ大陸を横断したとき、いろんなバンジョー弾きやギター弾きに出会った。
ラマー・グリアーと会ったその日の昼に息子のデビッド・グリアーとも会った。まだ金髪のさらさらのロングヘアーをなびかせて、ディキシー・ブレイク・ダウンを猛スピードで弾いていた。
ラマー・グリアーのバンジョーは、驚くほどネックが細かった。
同じワシントンDCではセルダム・シーンの面々ともよく一緒に演奏した。もちろん大塚あきらさんのバンド“グラズ・マタズ”とも。
ナッシュビルではよく、ジェイムス・マッキニーという若いバンジョー弾きと会ってはセッションを繰り返した。
まだ若かった頃のベラ・フレックともステイション・インの前でジム・ルーニーなどを交えて立ち話に興じた。
ダグラス・ディラードとも会ったが、かなり酔っていた(彼が)。
ニュー・ヨークではパット・クラウドのバンドを見て首をかしげていたケニー・ベイカーの姿が印象的だった。
ブルーグラスは僕にとって今でも魅力溢れる音楽だ。自分が「これ凄い」と思い、影響を受けてきたブルーグラスを順を追って書いてみよう。
フォギー・マウンテン・ボーイズ、ブルー・グラス・ボーイズ、スタンレー・ブラザース、テネシー・カッタップス、バージニア・ボーイズ、オズボーン・ブラザース、ディキシー・パルズ、ニュー・イングランド・ボーイズ、グリーン・ブライヤー・ボーイズ、カントリー・ジェントルメン、ディラーズ、ニュー・シェイズ・オブ・グラス、ニュー・グラス・リバイバル、セルダム・シーン、
個人の名前を出したらきりがない。
だが、今自分も年とって「やっぱりいいなぁ」と思えるもののトップは、もしかしたら往年のスタンレー・ブラザースかもしれない。
アイリッシュ・ミュージックの真の姿を追い続けているうちに、本当に心あるブルーグラスを聴きたくなってきたのだ。
ブルーグラス・ミュージック その2(ブルーグラス・バンジョー)
京都産業大学に入学して、すぐにブルーリッジ・マウンテン・ボーイズに入部(?)した。詳しくは軽音楽部だったかな。
先輩の酒井さんはフラムスのバンジョーを使っていた。時々、みんなで立命館大学に行って、サニー・マウンテン・ボーイズの練習を聴いた。
覚えている限りバンジョーは中さん、マンドリンが新谷君、ギターとボーカルが池田さん、フィドルが赤城さんだったと思う。ベースは亀井さんだったかな。
亀井さんは後に同志社のマリース・ロック・マウンテニアーズでベースを弾いていたような記憶がある。
マリース…もなかなかの面子だった。ギターとボーカルが田川さん(ギターのボディをくりぬいてホイールキャップをはめ込み、ドブロを作ってしまった人)マンドリンに伊藤さん、フィドルとバンジョーに“天才”石田じゅんじ、そしてベースがやっぱり亀井さんだったかな。
とにかく京都ではこの三つのブルーグラス・バンドが競り合っていたと思う。立命の中さんのバンジョーはやっぱりフラムスだった。
荒神口(当時、立命があったところ)のよしやという楽器屋に行くとフラムスが置いてあった。
お店の人に「立命でもこれ使っているよ」と言われたが、どこかドイツ製、というところがしっくりこなかった。
とはいっても、とてもじゃないがギブソンやベガなんて買えるわけがない。よく、梅田のナカイ楽器に、これ見よがしに飾ってある、マーティンD-28とギブソンF-5と、そしてあれは多分ギブソンRB-250だったのだろう。大学から直接、阪急電車に乗って観に行ったものだ。そう、ただ観るだけの為に。
そしてため息をついて帰ってくるのだ。
当時、関西ではフラムスが主流だった。あとは“ケイ”だったかな。この辺のことは以前にもコラムで書いている。
とにもかくにも頭の中は16分音符がいつもぐるぐる回っていた。バンジョーという楽器の魅力は、とくにブルーグラス・バンジョーの魅力はなんといっても、ごく小さな手の動きから生み出される、はっきりした大きな音と、目にも留らぬスピードで繰り出される音の嵐だろう。
手掛かりはレコードだけ。ドン・レノのグリーン・マウンテン・ホップ、ダグラス・ディラードのディキシー・ブレイクダウン、エディ・アドコックのブルー・ベル、ビル・キースのセイラーズ・ホーンパイプ、みんなみんなレコードを聴いて覚えた。
どんなに小さな音も逃すまいと必死になったものだ。少しでも彼らに近付きたくて、友人たちと「ここはこうだな。いや、こうかな?」と夜通し議論しては弾いたあのころは、やはりアンテナを全開させる能力を養う、ということに於いてはかなりためになったのかもしれない。
ブルーグラスはとてつもなく難しい音楽だ。一人ではできない。二人でもできない。三人いても足りない。4人からが初めてブルーグラス、といえるかもしれない。
グループのレベルがある程度揃っている必要もある。アンサンブルの妙というところは肝だ。少なくとも3人以上は唄えなくてはならないし、コーラスができなくてはいけない。
大体バンジョー弾きはバリトンだ。別に決まっているわけではないけれど、マンドリン弾きがテナーというのは、やはりビル・モンローの音楽だからだろうか。セイクレッド・ソングもアカペラでこなせなくてはならない。
バンジョーの話しに戻るが、最近つくづく思うことは、メロディック奏法は難しい、ということだ。
なんとなくロールでメロディを創り出していくものは平和な感じがする。すこしブランクがあってもリカバーできるが、メロディック奏法はイライラしてくる。右指はメロディに合わせて自由自在に動かす必要があるし、それに合わせて左指のポジションも考慮にいれなくてはならない。
ノラ、ビーティング・アラウンド・ザ・ブッシュ、トルコ行進曲…40年くらい前は事もなげに弾いていたが、最近思うことは、2つ以上のことをいっぺんに考えると頭が混乱する、ということだ。
この楽器は頭を混乱させるには“もってこい”のものだ。(多分コンサルティーナもそうかも)更に、ボケの防止には結構いいかも。とにかく一生懸命想い出すための努力をする、ということが一番大切だ、と女医の卵も言っている。
ま、そういったことは、久しぶりにバンジョーを引っ張り出して弾いてみた人にはよく分かるだろう。いや、僕だけかな。
なにはともあれ、魅力的な楽器である。その“とんでもない重さ”というところを除いては。
ブルーグラス・ミュージック その3(ブルーグラス45とBOM サービス)
ブルーグラスファンなら、もはや知らない人はいないだろうこの会社は設立してからもう40年にもなるだろうか。
この、言うなれば超マイナーな音楽を、今日まで日本という国の中で紹介し続けた功績は偉大なものだ。
ものごとをやり続けることの大切さ、そして情熱を持ち続けることの大切さ、自分たちが愛して止まない音楽に対する飽くなき研究心を持ち続けることの大切さ、それらのことを、このBOMから学ぶことができる。
中心人物の渡辺兄弟。お兄さんの敏雄さんについては個人的にはあまり知らないが、弟の三郎は歳も同じだし、バンジョー弾きということで、すでに45年くらいの付き合いだ。
僕と省悟の“50・50”のビデオの中で、フィドルを弾いているのが彼。ブルーグラス45の初アメリカ・ツァーから帰ってきて「やっぱこの音楽はフィドルやで」と言ってフィドルばかり弾いていた時期があったことを想い出す。
それについては僕も同感だ。スコティッシュ、アイリッシュの流れを汲むこの音楽は正に“フィドル音楽”だ。
それはともかくとして、かなり昔のアルバムで彼はケイのバンジョーを持っている写真があったがいつか聞いてみよう。
ヘッドストックの部分にアメリカの国旗みたいな模様が入っていたと記憶している。
そして大塚兄弟。兄のジョッシュと弟の章さん。ジョッシュは生まれた時からジョッシュではないはずだが、もう40年以上ジョッシュとしてしか知らないので大したもんだ。
章さんにはアメリカで随分お世話になった。しかし関西の人はなんであんななんだろう。
電話してくる時も「角のそば屋です」などと言ってきたものだ。
非常にアグレッシブでエンタテイニングに満ち溢れた超絶テクニックのマンドリン・プレイは今も健在だ。
それに、フィドルの寥さん。ほとんど個人的には知らないが、東のジョー(ジョー・山本)西の寥、は当時日本のフィドラーの代名詞であった。
もうひとり、李さんという人がいたはずだ。かれらがブルーグラス45。60年代後半、日本が生んだスーパー・グループだ。
そのブルーグラス45での活躍を基に立ち上げた会社がBOMサービス。
ナターシャー・セブンからブルーグラスを知った人も、最近ブルーグラスを知った人も、アイリッシュ・ファンの人も、是非、彼らの心を感じてもらいたい。
Irish Music
今回から僕らのレパートリーについて詳しく書いてみよう。いつまで続くか、そして、
あまり書くべきこともないものもあると思うが、アイリッシュ・ミュージックに本格的に取り組みはじめてから23年あまり、希花とのデュオを組みはじめてから3年目、アイリッシュ・ミュージックのひとつの要素であるレパートリーの数もだいぶ増えてきた。
Irish Musicその2
Mayor Harrison’s Fedora/The Humours of Westport/Bucks of Oranmore(Reel set)
★ Mayor Harrison’s Fedora
“3パートのいいメロディを持ったリールで、もう20年以上演奏している曲だが、驚いたことに3パート目を知らない人が結構いるようだ。
ドーナル・ラニー達が2パートだけでやっていたせいだろうか。
オニールのコレクションには既に存在している古い曲である。このモデルになったハリソンは1897年から1915年までシカゴのメイヤーであったらしい。ちょうどオニールがシカゴで多くの曲をコレクションしていた頃だ”
Irish Music その3
The Curlew/Paddy’s Trip to Scotland/Dinkey’s(Reel set)
★ The Curlew
“Josephine Keegan作のこの曲を初めて聴いたのは、まだこの音楽を始めたばかりの頃でAltanの録音からだった。メロディの美しさ、特にBパートの美しさは特筆すべきものだ。
アイリッシュ・ミュージックにのめり込んだきっかけともなった曲といっても過言ではない。コード進行も非常に興味深い”
★ Paddy’s trip to Scotland
“典型的なDonegalチューンといえるだろう。若い人たちのほとんどはDervishの演奏で聴いているが、僕はやはりAltanのバージョンが好きだ。僕はこの曲にテキサス・フィドル・スタイルの伴奏に使うようなコード進行を使っている”
★ Dinkey’s
“この曲を書いたのはFrancis Dearg Byrneだと言うひともあれば、彼はトラベリング・ミュージシャンであるDinkie Dorrianから習った、と言うひともいる。多分にCape bretonフィーリングに溢れる曲なので、どうしてもNatalie MacMasterやAshley MacIsaacの演奏が耳に残っている”
Bush on the Hill/Castletown Connor/McIntyre’s Fancy(Jig set)
このセットはyou tube上で僕らとFrankie GavinとがGalwayで演奏しているものが見れる。
★ Bush on the Hill
“とても幅広い音の動きをする人気の高い曲だ。アメリカではFool on the Hillと呼ばれていた頃がある。ご存知ブッシュが大統領だった頃、ビートルズの曲とかけていたのだ”
★ Castletown Connors
“Ned coleman,Tommy mulhairesなど多くの名前がある曲だが、前の曲からのつなぎがとても好きでくっつけてみた。
★ McIntyre’s Fancy
“Siobhan O’Donnelleの#2だ、という人もあれば、John Bradyの作だという人もいる。
どちらにせよ、いいメロディを持った曲で若い人にも人気がある。Bパートで僕が弾いているコード進行を使う人には会ったことがないが、これをアイルランドで弾くと誰もがにんまりとする”
Irish Music その4
Chief O’Neill’s Favourite/The Galway Bay(Hornpipe)
★ Chief O’Neill’s Favourite
“おそらく、最も多くの録音がのこされているホーンパイプのひとつだろう。親しみやすいメロディと、Bパートで突然雰囲気が変わることで、人気があるのかもしれない。ところで、この人(オニール)は19世紀後半から20世紀に渡る頃のシカゴの警察署長だった人で、驚異的な記憶力で多くの曲を収集していた、とされる”
★ The Galway Bay
“Gマイナーで演奏されることが一般的なとても美しいメロディを持った曲。日本ではあまり聴くことがないが、実に多くの録音が残されている。Tommy PottsはDrunken Sailorを録音しているが、出だしはどう聴いてもこの曲だ。おそらくメドレーだと思うが、どちらもとても美しいメロディで希花のフェイバリッツでもある”
The Choice Wife/The Humours of Whiskey(Slip Jig)
★ The Choice Wife
“実に多くのタイトルを擁する曲でアイルランド語でAn Phis Fhliuchというらしいが、アメリカでもThe Choice Wifeのほうが一般的である。5パートの力強い曲”
★ The Humours of Whiskey
“ずいぶん前からとても好きだった曲。Altanで最初に聴いたかもしれないが、僕らのこのメドレーは実に気持ちのいい運びになっていると思う。Bmベースの曲だがEmで演奏する人も多くいるようだ”
The Twelve Pins/Kilty Town(Reel)
★ The Twelve Pins
“Connemaraの山の名称らしいが、Chalie Lennon作の素晴らしい曲で、日本の演奏家たちにはあまり馴染みがなさそうだが、希花のフェイバリッツのひとつ、ということだ。とても明るいメロディを持っている”
★ Kilty Town
“これもCharlie Lennonの作品だ。セットで演奏されることがほとんど。Frankie Gavinが素晴らしい演奏を残している”
Gypsy/Cavan Pothles(Tune)
★ Gypsy
“Lord of the Danceの中に登場した曲。Ronan Hardimanの作であろう。実際は管楽器で演奏されたものだったが、Gillian Norrisのとても官能的なダンスとともに、印象的なメロディであったので、これはレパートリーに入れない手は無い、と感じたものだった”
★ Cavan Pothles
“Donal Lannyの作になる非常にキャッチーな曲。どこから聴いてもスティングのあの名曲Englishman in New Yorkを素材にしているとしか思えないが、どうだろうか。Sharon Shannonのレコーディングを初めて聴いた時からそう思ったが、それはそれとしてかっこいい曲である。いかにも若者好みだが、ShannonもLunnyもれっきとしたトラッド・ミュージシャンでもある”
Irish Music その5
Forget Me Not/Tripping Down the Stairs/The flowers of Red Hill(Reel)
★ Forget Me Not
“様々なタイトルで呼ばれている。
の演奏でキーはDだったが、
★ Tripping Down the Stairs
“Arcadyの演奏で聴いたものが最初だった。
★ The Flowers of Red Hill
“De Dannanの初期のアルバムの中で(彼らのタイトルはThe Clogherだった)聴いたのが最初だろうか。
Smiling Bride/The Handsome young Maidens(jig)
★ Smiling Bride
“Charlie Lennon作。題名どおり、にこにこしたくなる曲だ。
★ The Handsome Young Maidens
“これもCharlie Lennonの作品。この2曲は、
The Eel in the Sink/McFadden’s Handsome Daughter/The Limerick Lasses(Reel)
★ The Eel in the Sink
“あまりポピュラーではない曲かもしれないが、Jody’s Heavenでの録音が残されている。その時に使ったアレンジ(
★ McFadden’s Handsome Daughter
“3パートの綺麗な曲だ。
★ The Limerick Lasses
“3パートで演奏される場合と4パートで演奏される場合がある。
Lord Gordon(Reel)
★ Lord Gordon
“5パートあるが、どこもかしこも似たり寄ったりで、
フィドラーにとっては永遠の名曲のひとつであろう。“
Dennis Doody’s/Tolka Polka/Tina Lech’s(Polka)
★ Dennis Doody’s
“Donal Lunnyのライブ・アルバムで覚えた曲。
★ Tolka Polka
“Donal Lunnyの作。普通に演奏しても結構トリッキーだが、
★ Tina Lech’s
“
Old Grey Goose(Jig)
★ Old Grey Goose
“Clareで毎日のように聴いていて、
Strayaway Child(Jig)
★ Strayaway Child
“Bothy bandの演奏で聴いてからずっと好きな曲だった。
An Paistin Fionn/Eamonn McGivney(hornpipe)
★ An Paistin Fionn
“同名のエアーも存在する。あまり聴くことがない曲だが、
★ Eamonn MaGivney
“Keep Her Lit とJody’s Heavenでも手がけたJacky Tarとほとんど同じ曲だろう”
Irish Music その6
Morning Dew/Jenny’s Chicken
★ Morning Dew
いつ覚えたか覚えていないくらい有名な曲だ。そのむかし、Stockton’s WingがGolden Studというセットの後半にちょっとメロディを拝借して使っていたような記憶がある。
以後、Dale Russのフィドル教則ビデオでリールのお手本として使っていたものをよく見ていた。その後ケビン・バークとミホーのビデオでも最初のセットの3曲目としてよく聴いたものだ。
基本Emで演奏したらよいのだが、Cmaj7, Am7,A7などを巧みにいれることによって変化がつくが、入れどころが微妙なニュアンスの違いを生む。トニー・マクマホンと演奏する時とマーティン・ヘイズと演奏する時とではギタリストの役割は違ってくるのだ。その辺が最も顕著に表れるタイプの曲かもしれない。因みにPaddy Cunnyは3つのパートの最後のパートから入るが、これもかなり効果的なやりかたかもしれない。
★ Jenny’s Chicken
“Michael Colemanによって一気に有名になった曲だ。ほとんどSleepy Maggieと同じ曲ではないか、と言う人もいる。この曲にいくにはBonnie Kateがベストだ、という人もいるが、ぼくらはMorning Dewからいくのがとても好きだ。そのむかし、スコットランドから来たLiam Whiteという、とても上手いとは言い難いギタリストがいたが、彼のアイデアのいちばん優れたものがこのセットを考えだしたことかもしれない。若手ばかりで、よくセッションに行ったものだ。Liam, Dana Lyn, Tina Lech, Ted Colt, Athena Targis当時、みんな若くて相当勢いに乗ったセッションを繰り広げていた。なかでは僕が一番歳寄りだった。40代後半だったかな。かれらは全員20代初めだった。そんななかで勢いと共に生まれたセットで、希花がその勢いを継いでくれている。
今日はこれだけ。しばらく北海道に出かけるので、帰ってきたらまた書き始めます。
Irish Music その7
Thomas’ Farewell/As the Sun Was Setting(Waltz set)
★Thomas’ Farewell
“読み人知らずだが、トラディショナルではない。美しいメロディを持ったワルツだが、あまり有名な曲ではない。キルフェノラ・ケイリ・バンドのレコーディングだけが唯一残されているというが、ティプシー・ハウスでは随分昔からやっていた。AパートとBパートのテキスチャーの違いはギタリストにとっても非常におもしろい曲だ”
★As the Sun Was Setting
“John Kirkpatrick作曲とされる美しいマイナー調の、どこかウエスタン風の曲だ。僕はデイル・ラスから習った” どこか日本人好みのメロディは、Aパートのウエスタン風からBパートの日本調ともいえる半音階の下がり方が印象的だからだろう”
Gold Ring(Jig)
★Gold Ring
“この曲には3つのバージョンがある。いや、それ以上かもしれない。パート数もいろいろだ。僕らは7パートでやっている。しかも、僕は勝手にパイプ・バージョン、フィドル・バージョン、そしてD Gold Ringと呼んでいるがDのもの以外はどちらもパイプで有名かもしれない。Seamus Ennis,Willie Clancy などで知られているので、やはりパイプ・チューンと言えるだろう。僕はDale Russと録音したことがあるが、これはThe Boys of the Loughのバージョンで、あまり知られていないものだ。整理するとKey of Gがふたつ、Key of Dがひとつ。ただ、Gの方のDaleと録音したものはKey of GだがDコードから始まる。Gold Ringを演奏するのならこの3つとも覚えておきたい。かわいそうな希花である。伴奏に於いても、7つもパートがあると、そのすべてのパートの音の動きを正確に把握する必要がある。それでないと単調な面白くない曲に聴こえてしまう可能性がある。因みにThe Broken Gold Ringという曲もあるが、これはDのバージョンの最初の2パートだけを演奏されるものだ。最後に面白い話をひとつ。Seamus Ennis曰く、この曲はアイルランドの妖精によって書かれた曲、らしい”
Irish Music その8
Galway Reel/Beare Island/Maudabawn Chapel/Hunter’s House(Reel)
★Galway Reel
“これは間違いなくLarry Redicanの作だ、という人もあれば、Paddy Faheyだという人もいる。曲調から察するにFaheyではないと僕は思う。タイトルではIroning Boardという人もいる。少しトリッキーな曲だが、Liz Carollの演奏でよく知られるようになった。伴奏者にとっても面白い曲だ”
★Beare Island
Kevin BurkeのライナーではDale Russの曲だ、と書いてあったが、本人曰く、ずっと前にKevinに教えたことはあるけど、僕の書いた曲じゃない、ということだ。いろいろ調べてみるとRichard DwyerがFinber Dwyerの為に書いたFinber Dwyer’s Fancyという曲だという説が最も有力かもしれない。Key of Eだが BパートでEmになる魅力的な曲”
★Maudabawn Chapel
“Ed Reavyのペンになる最も有名な曲のひとつだろう。BパートはDrowsy Maggieのような出だしだ。Eileen Iversはエアーのようにして弾いているが、それほどに美しいメロディを持ったリールだ。Kevin Burkeでも有名だが、、1979年のEd Reavy本人の録音も残されている。Edは1898年にCavanのMaudabawnで生まれた。これはローカルの教会をモデルにした曲だ。彼は1912年にアメリカに移り、フィラデルフィアで1988年に亡くなるまで水道屋として働いていたようだ”
★Hunter’s House
“前の曲からの繋がりはThe Green Fields of Americaのレコーディングから学んだ。これもEd Reavy の有名な曲で、ただ単にReavy’sというタイトルでも知られている。
Master Crowley’s/Roscommon (Reel)
★Master Crowley’s
“いつ頃から演奏しているだろう。Joe Cooley生き写しの演奏をするPatricia Kennellyのアコーディオン・プレイにしびれたのはもう13年ほど前のことだ。別名(勿論いっぱいあるが)Miss Patterson’s Slipperとしても知られる。Begley家のみんなと演奏してからは、すっかり希花の得意曲となった。なかなか彼女のようなフィドリングはアイルランドでも聴けない”
★Roscommon
“よくMaster Crowley’s #2としてメドレーで演奏される。Andrew MacNamaraが2曲を交互に演奏したが、Brendan Begleyも同じことをやっていた。ふたりともやんちゃな性格だ。僕らもそのやりかたがとても好きだ”
Irish Music その9
★ Boogie Reel
“John Nolan作。Terry BinghamはThe Durrow Reelというタイトルでやっていたが、これだけ作者もはっきりしている曲でも、伝わり方でこのように変化していくのは、この音楽の面白いところだ。BoogieというのはNolanのバンドのキーボード奏者のあだ名。僕らはJosephin Marshの演奏が気に入っている。もう、何年も前から演奏しているが、Bパートにブギーのリズムを使っているのは僕ぐらいかな。僕は90年初め頃、バンジョー弾きのSuzanne Cronninから教わった”
★ Splendid Isolation
“Brendan McGlinchey1973年の作、と言われるが、Kevin Burkeが1972年に、すでに録音している、という情報もあるので、71年から72年の作品ではないかと思われる。73年と言ったのは本人らしいが、多分記憶も定かではないのだろう。数多くの曲を作っていれば無理もないことだ。だが、作った経緯に関してはかなり明確だ。
アイルランド・ツアーを終えた彼は、ダブリンの空港でロンドン行きの飛行機を待っていた。2週間にわたるツアーでは、バンド・メンバーともさほどいい関係を保てず、ストレスを抱えたままコーヒーを飲んでいた。そんな時に、フッとメロディが浮かんだようだ。名作中の名作である”
★ Mrs. Lawrie’s
“同じくMcGlincheyのペンになる曲。2曲はセットで演奏されることがほとんどだが、こちらの方は、いつどのような経緯で作られたのかはわからない”
Sonny Murrey’s/Home Ruler/Kitty’s Wedding(Hornpipe)
★ Sonny Murrey’s
“別名Wicklow Hornpipe。SonnyはWest Clareのコンサルティーナ奏者である。
★ Home Ruler
“County Antrim出身のFrank McCollumの作”
★ Kitty’s Wedding
“これらの3曲はセットで演奏されることが定説”
Irish Music その10
Bold Doherty/Cock and the Hen(Jig/Slip Jig)
★ Bold Doherty
“これは同名の唄をインストルメンタルにしたものだ。そのむかし、シンガーと一緒にやっていたもので、どこかで聴いたことがある、と思っていたら同じ曲だった。僕らは次の曲とのセットでJosephin Marshをフォローしている”
★ Cock and the Hen
“18世紀ころからある曲だ、といわれる。そのタイトルもDoodley Doodley Dankというややこしいものから、Joe Ryan’s,Cathal McConnell’sなど様々だ”
Return To Miltown/The Road To Ballymac/Gun Ainm(Reel)
★ Return To Miltown
“典型的Donegalチューンのひとつ。僕は92年くらいからScott Renfortの得意曲として一緒に演奏していた。DmからBパートでDmajorにいくのが印象的な曲だ”
★ The Road To Ballymac
“アコーディオン奏者のLeslie Creigの作。Jack Gilderから教わったが、最近Steph Geremiaという若手フルート奏者が演奏しているのを聴いた”
★ Gun Ainm
“アイリッシュ・チューンではタイトルの分からない曲をこのように呼ぶ。これは、上の曲とセットでティプシー・ハウスがよく演奏したので、Jackにいつか訊いてみよう。Bパートは非常に珍しい音運びで興味深い曲だ”
Irish Music その11
Blackbird(Hornpipe)/Gallagher’s Frolics/Winnie Hayes/Rolling Waves(Jig)
★ Blackbird
“Kevin Burke&Jackie Dailyでずっと前に覚えた曲。同名のホーンパイプがいくつか存在するので、またそちらもやってみたいと思っている。Set DanceのバージョンはPaddy Keenanで有名だ。また、Bothy Bandが同名のものをReelでやっているものもあるが、これも別物。Andrewがこんなホーンパイプはホーンパイプじゃぁねえ!と捨て台詞を吐いたが、自分の聴いたことのないものは認めない、という意固地さもまた彼らしい。でも無類のブルース好きだし、Deiseal(Cormac Breatnach牽き入る3人組のモダーンなバンド。94年と97年に素晴らしいアルバムを残している)の演奏もすごく好きなようだし。それでAndrewのバンド、The LahawnsにDeisealのベース・マンであったPaul O’Driscollが参加していたことにも納得がいく。
因みにPaulは現在Frankie Gavinのバンドにいる“
★ Gallagher’s Frolics
“The Clareというタイトルでも知られている。O’Gallagher’s Frolicsともいう。日本のセッションでもよく登場する、比較的ポピュラーな曲だ”
★ Winnie Hayes
“作者はわからないが、れっきとした個人名がついている。Micho Russellの演奏でも良く知られるようだが、それについての興味深い話しがある。MichoはClareのコンサルティーナ奏者Kitty Hayes(つい最近亡くなった)のご近所さんで、同じくご近所さんのWinnie(同じHayesだが親戚関係はないらしい)に曲を習っていた。それは40年代初め頃の話で、お互いに行き来があったなかで、Winnieという人物がいたわけだ。
因みにPackie Russell(Michoの弟でコンサルティーナ奏者)はKittyの結婚式で演奏したそうだ。1948年のことらしい。結局のところ出どころはわからないのだが、多分WinnieからMichoが教わったうちのひとつで、このタイトルがついているのだろう。Eminorで演奏する人も多い、と聞くが、僕らはAminorでやっている。
★ Rolling Waves
“僕らのバージョンはJohn Williamsから得たものだが、それにしてもRandal Baysのバッキング・ギター・スタイルはとても魅力的だ。Kevin Burkeの演奏でもポピュラーになった曲
Rolling in the Barrel/Lafferty’s/Lads of Laoise(Reel)
★ Rolling in the Barrel
“僕らはMartin Hayesの演奏からヒントを得ているが、かなり前からAndrewの演奏などでも聴いていた曲”
★ Lafferty’s
“Sean Ryan(Tipperaryのフィドラー)の作といわれるが、彼が作曲を始めるよりも、かれこれ20年以上も前にJames Morrisonが録音している、という説もあり、定かではない。タイトルも、どちらかといえばGlen of Aherlow(AhelowはSean Ryanの出身地)というほうが正しいという説もあるが、これに関しては明確な事実があるようだ。Paddy CannyとP J Hayesが録音した時のピアニストが最も好きだった曲ということだが、彼女の名前がBridie Laffertyという。そこで、Lafferty’s Favouriteなどと言われるようになり、この名前に変わってしまって一般的にはこう呼ばれるようになった”
★ Lads of Laoise
“古いスコットランドの曲でLads of Leithというらしいが、アイルランドで演奏されるようになって、このタイトルに変わったそうだ”
Irish Music その12
Morgan Magan(O’Carolan)/Shaskeen/Congress(Reel)
★ Morgan Magan
“クラシック・フィーリング溢れるこういう曲は僕らの最も好きな分野かもしれない。僕は多分アイリッシュを始める前から知っていた曲だ。アメリカの演奏家にも人気の高い曲だけに、様々な人が演奏していた”
★ Shaskeen
“めずらしく他の名前で呼ばれることのないとてもポピュラーな曲。前の曲と出だしが同なので繋げてみた”
★ Congress
“Gordon Duncanの作といわれるが、いや、もっとむかしからあったスコティッシュ・チューンだ、というはなしもあり、よくわからない。非常に“のり”のいい曲だ”
Lover’s Waltz(Waltz)
★ Lover’s Waltz
“2010年、電車の中でPaddy Keenanが「いい曲があるぞ。この間友達の結婚式で聴いたんだけど」と言って聴かせてくれた。「Jayなんとかっていうやつがつくったんだけど」「Jay Ungerか?」そう、メロデイの創り方が、かの名曲Ashokan Farewellによく似ていたのですぐに分かったのだ。Fiddle Feverは大好きだった。特にAshokan..の入っていたアルバムはジャケット・デザインからして、今でも最もお気に入りの一枚かもしれない。希花のフィドル・スタイルにもよく合っている曲だ”
Two Days to Go/Beaujolais in Boston/Jimmy’s Trip to Clonmel
★ Two Days to Go
“とてもセンスのいい曲を沢山創っているパイパー、Diarmaid Moynihanの作曲。
Deantaの演奏から覚えた”
★ Beaujolais in Boston
“この3曲はDeantaによって、セットで演奏されていたもので、とても気に入っている。
メンバーのフィドラーKate O’BrienとフルートのDeirdrie Havlinの共作、ということだ。
とても美しいメロディーで前の曲とも後の曲ともとてもつながりがいい”
★ Jimmy’s Trip to Clonmel
“北アイルランド出身のDeirdrieが父のJimmyとのアイルランドの旅を想い出して書いた曲。おそらくAll Irelandのフェスティバルに参加した時のことではないか、と思うが、この3曲のセットは希花の最も好きなセットのひとつかも知れない”
Irish Music その13
George White’s Favorite/Lad O’Beirne’s/Sweeney’s Buttermilk(Reel)
★ George White’s Favorite
“非常にとっつきやすい、いいメロディだ。キーはGだが、多くの人はEminorから入る。
僕は過去、Michael O’Domhnaillで聴いたCmajor7のコードが好きだが、これは独特な世界観を持つので、相手に尋ねてからのほうがいいかもしれない”
★ Lad O’Beirne’s
“Co.Sligo出身のこのフィドラーはPaddy Killoran,Michael Coleman,Ed Reavyらと並ぶ人物だ。1911年に生まれ、‘28年にアメリカに渡ったが、いわゆるコマーシャル・レコーディングは残されておらず、ほとんどがプライベートなテープ録音だといわれている。
しかし、名曲をたくさん残している”
★ Sweeney’s Buttermilk
“Brendan McGlinchey作。こんな逸話が残されている。あるワークショップで一人の少年になにか弾くように促したところ、出て来た曲がこれだった。彼はすかさず「なんていう曲か知ってるか?」と尋ねたところ、少年は胸を張って答えた。「Sweeny’s Buttemilk」
彼はさらに質問した「誰が書いたか知ってるか?」少年は首を横に振った。彼は言った。「俺さ」少年のその時の驚きようと、目の輝きはこのワークショップでの語り草となっている。
因みに変わったタイトルだが、これは、彼の友人の一人であるSweeneyという男と彼とがバターミルクが大好物だったので出来た曲らしい…“
Dunmore Lasses/Sporting Paddy/Sean Sa Ceo(Reel)
★ Dunmore Lasses
“Tom Morrisonの1927年の録音ではAパートとBパートが逆に演奏されている。Chieftainsのアルバムでは普通のリールとして演奏されているが、Matt Molloyはスローで演奏している。Mick moloneyはMorrisonと同じ手法を取っている、など様々だが、僕等はA,Bと演奏している。イントロにスーパーギタートリオの地中海の舞踏のイメージを使わせてもらっている”
★ Sporting Paddy
“特筆するような情報はないが、とてもポピュラーな曲で200以上の録音が残されている”
★ Sean Sa ceo
“John in the Mistという英語のタイトルでも知られているこの曲は、DonegalのフィドラーであるNeillidh Boyleの作と言われているが、本人は、うんと古い曲で母から習ったと言っているらしい”
Irish Music その14
Concert/Now She’s Purring/Ivy Leaf(Reel)
★ Concert
“Frankie Gavinが次の曲と共にConcert Reelとして録音を残しているので、混乱している人もかなりいる”
★ Now She’s Purring
“そういうわけで、こちらもConcert Reelだと思っている人がいるが、こんなタイトル、あるいはCallaghan’sともいわれている”
★ Ivy Leaf
“Micho Russellの非常に強いクレアー・アクセントからI Will Leaveだと勘違いしている人もいるらしい。まるでJody’s Heavenだ”
The Monaghan Jig/The Hungry Rock (Jig)
★ The Monaghan Jig
“Patric(Patsy)Touheyのパイプ・バージョンは圧巻だ。その昔、3パートで演奏されていたものを1921年のマイケル・コールマンのニュー・ヨーク録音で、彼が4パート目を作りあげたらしい”
★ Hungry Rock
“Liam Kelly(Dervishのフルート奏者)のペンになるとても難しい曲だが、とことんかっこいい”
The Humous of Tullycrine/The Garden of Daisies(Hornpipe)
★ The Humous of Tullycrine
“12~3年前、Terry Bingham,Andrew MacNamaraと共によく演奏した曲だ。Dm,Em,Gm,Amと、いろんなキーで演奏されるが、僕等はDmでやっている。あの時はAmでやっていて、しかも面倒くさがりやのAndrewはTerry’s Hornpipeなんていっていたなぁ”
★ The Garden of Daisies
“Padraig O’Mileadhaの作、といわれている。小節数からいって、セット・ダンスだと思うが、ホーンパイプとして扱っている書物もあるので、とりあえずホーンパイプにしておいた。僕等はPaddy Keenanから教わった”
Irish Musicその15
The Banks of the Ilen/The Scartaglen/Eddie Moloney’s Favorite(Reel)
★ The Banks of the Ilen
“Tipsy Houseでもよく演奏したセット。次の曲とは決められたように、誰もがセットとして演奏する。因みにHumours of Drinaghという曲もあるが、この曲のJigバージョンだ。
IlenはCo. Cork, Skibbereenを流れる川で、アイ・レンというような発音だ“
★ The Scartaglen
“Dennis Murphy とJulia Cliffordの録音で有名な曲”
★ Eddie Moloney’s Favorite
“ほとんどの演奏は上2曲で終わるが、Tipsy House3代目のFiddlerであったLaura
Riskが突然この曲を弾き出した。僕もジャックもそのアイディアの素晴らしさに感動したものだ。それ以後、この3曲はセットとして演奏することにしている”
The Rose in the Heather/The Banks of Lough Gowna(Jig)
★ The Rose in the Heather
“とても落ち着いたいいメロディを持った曲で、初心者にもとっつきやすい。こういう曲におけるギター・プレイがいちばん難しいかもしれない“
★ The Banks of Lough Gowna
“この2曲のセットはDale Russからいただいた。たまにこのセットのあとSaddle the Ponyにいくこともある。セッションでも比較的よく登場する”
Irish Music その16
Down the Hill(Set Dance )/The Yellow Tinker/The Drunken Tinker(Reel)
★ Down the Hill
“James Kelly,Paddy O’Brien(Co.Offaly)の演奏で覚えた曲。長いことワルツだと思っていたが、いろいろ調べているうちにセット・ダンスということが判明”
★ The Yellow Tinker
“これはいかにも若者好みの曲だと思うが。文献からは作者などに行きあたらないので、トラッドとみていいかも”
★ The Drunken Tinker
“前の曲とはとても興奮を呼ぶつながりかたをする。決して誰もがやっているわけではないが、Tipsy Houseの当たりナンバーだった”
The Fly Fishing/Michael Tennyson’s/John Burke’s (Reel)
★ The Fly Fishing
“Jackie Dalyの作。Verena ComminsとJulie Langanのパブ・ライブで覚えた曲。アコーディオンとフィドルのこのデュオはとても優雅で、本物のトラッドを聴かせてくれたものだ”
★ Michael Tennyson’s
“別名Poor but Happy at 53というが、VerenaがMichael Tennysonから習ってこう呼んだらしい。実際の作者はダブリンのフルート奏者で1994年に亡くなったPaidi Ban O’Brien”
★ John Burke’s
“ Verenaの作品。フィドルではかなり音が飛ぶので難しいと思うが、希花の得意曲の一つとして存在している。この3曲のセットは彼女たちのものをそのまま頂いた”
Irish Music その17
Irish Musicその17
Red Crow/Darley’s/Big John McNail(Reel)
★ Red Crow
“AltanのMairead Ni Mhaonaighの作。初めて聴いた時、とても興奮したことをよく覚えているほどの名曲だ”
★ Darley’s
“1920年以前にフィドラーであり、バイオリニストのArther Darley(Donegal)によって書かれた曲だが、アルタンの二人(MaireadとFrankie Kennedy)の演奏で有名になった。彼らはRaddy Redicanから習った、ということだ。僕等はJohn Williamsの演奏を参考にしている”
★ Big John McNeil
“Peter Milneの作。典型的スコットランド・タイプの曲だが、僕は70年代からよく聴いていた。オールド・タイマーたちはよくSt. Anne’s Reelの後にこの曲を演奏するらしい。Jon Hicksが強烈なギタープレイを聴かせてくれたのもこの曲だ”
Swan LK 243(Waltz)
★ Swan LK 243
“美貌のハープ奏者、Catriona Mackay作の、この世で最も美しいと思えるくらいの曲だ。変わったタイトルだが、1999年に彼女がCutty Sark Tall Ships Raceに行った時に、この古い船であるSwan LK 243に乗った。その時の想い出をもとに書いた、と言われる。これは希花が僕に教えてくれたが、本当に美しい曲だ”
O’Carolan’s Concerto/Planxty Joe Burke(O’Carolan/Hornpipe)
★ O’Carolan’s Concerto
“特に好きな曲ではなかったが、Frankie Gavinと一緒にやってから何故か好きになった曲。日本のプレイヤーもよく演奏する比較的有名な曲だ”
★ Planxty Joe Burke
“Anamの演奏で初めて聴いたときはJoe Burkeの作品だと思ったが、考えてみたら自作のPlanxtyはおかしい。これはCharlie Lennonの作品だ。どこかバロック風の美しい曲だが、前曲のクラシック・フィーリングとよく合っていると思い、つなげてみた”
Irish Music その18
Maid I Never Forget/JB’s/Lad O’Beirne’s(Reel)
★ Maid I Never Forget
“かなり前にArty McGlynnとNollaig Caseyの演奏で聴いていたものだが、僕らは
Padraig Rynneの演奏からレパートリーに入れている。Padraigはクレアー出身のコンサルティーナ奏者だが、2002年頃、Breda Smythと共に行ったGalwayのパブ・セッションで一緒に演奏したことがあった。若手ナンバーワンのコンサルティーナ奏者というふれこみ通り、素晴らしくテクニカルな演奏を聴かせてくれた。その時にはCherish the Ladiesのアコーディオン奏者Mary Raffertyとも久しぶりに演奏した 。大きなセッションだったけど、どこだったんだろう”
★ JB’s
“全く何の情報も得られないが、Padraigのセットから学んだ。とまで書いたところ、待てよ、他に調べる方法があるだろう、と思い情報をひっくり返していたら見つかった。その文献によると、James Murdoch Hendersonによって1932年頃に書かれた曲らしい。そしてJBとはスコットランドのフィドラー、James B Patersonという人のことだそうだ”
★ Lad O’Beirne’s
“Sharon Shannonの演奏でも有名だが、この3曲セットはPadraigのものだ。キーは何故か必ずF”
Cutting A Slide Reel(Reel)
★ Cutting A Slide Reel
“これは、Irish Musicその10の項目でGun Ainmとしておいた曲だ。(Road to Ballymacとのセット)95年頃、ジャックの家で教わった曲で、それから15年ほど経って、今度は僕が希花に教えた。Bパートがとても特徴あるメロディで、当時ジャックはPhil Cunninghamと言っていたような覚えがあり、正確なタイトルを知りたかったので、ジャックに電話したが、もう長年弾いていないので覚えていない。どんな曲だった?というので弾いて聴いてもらったところ、確かにPhilの曲だと思うけど調べておくよ、ということだった。数時間たってメールが入った。わかったぞ、Cutting A slide Reelだ。有難うジャック。タイトルの分からない曲もたくさんあるが、こうして情報をえられることはとても嬉しいし、とても楽しいことだ。アイリッシュという音楽をどういうかたちであれ、すこしでも自分たちの音楽の一部としてでも取り上げている人達は、タイトルを知ることや、古い録音に耳を傾けることや、いろんなバージョンを知ることに努力すべきだ”
The Rights of Man/Pride of Petravore(Hornpipe)
★ The Rights of Man
“あまりにも有名な曲だが、誰がいつごろ書いたものかは分かっていない。僕はその昔、1972~3年頃かな、Incredible String Band のRobin Williamsonの演奏で聴いたのが最初だと思うが、彼は3パート弾いていた。だが、それ以後他の人の演奏では3パート目は聴いたことが無いが、それはスコットランド・セッティングらしい。因みにナターシャー・セブンではそれをお手本にして録音したことがある。また、Lord Cedar Hillというタイトルの詩がついている、という話もある”
★ Pride of Petravore
“上記の曲とのセットを有名にしたのはDe Dannan。Rights & Prideという上手いネーミングで人々に知られている。イアンとシルビア(カナダのフォーク・デュオ)の1963年のアルバムでこの曲を取り上げていた、という話もあるが、もしかしたら高校時代、フォークソングに明け暮れていたころに聴いたかも知れない。Percy French(1854~1920)の詩で歌われることもある。因みにタイトルはEileen Oge(Young Eileen)だそうだ”
Lane to the Glen/Man of Aran/The Musical Priest(Reel)
★ Lane to the Glen
“Ed Reavy作の有名な曲のひとつ。僕はRandal Bayes&Joel Bernsteinの演奏から学んだ”
★ Man of Aran
“ダブリンのパイプ&ホイッスル奏者、Darach de Brunが、友人である同じくダブリンに住むアコーディオン奏者のTommy Walshの結婚のお祝いとして書いた、とされる。尚Tommyは、かの有名な曲Inisheerの作者である、ということだ”
★ The Musical Priest
“Bmのとても人気の高い曲だが、アイリッシュ・ミュージックを始めたばかりの希花さんは、ある人達が、半音高いアコーディオンに合わせてみんなが半音高くチューニングをしていることも知らず、Cmでコピーしてしまった。後に本当のキーはBmだと知ったわけだが、いっそのこと両方ともやろう、ということになり、僕らは両方のキーを交互に演奏する。今までに聴いたことのないフィドル・プレイだ。因みにフォギー・マウンテン・ブレークダウンの最初の録音は、やはり半音高いのだ。そうともしらない希花さん。G#というとんでもないキーで事もなげに弾いていたが、ブルーグラスのフィドラーも大したもんだ。こんなに難しいキーでこんなことやるんだ、と感心していたそうだ。彼女にとってキーというものはテクニック的なことでいえば、まったく関係ない”
思い出 ~映画編~
しばらくアイリッシュ・ミュージックのレパートリーについて書いてきたが、そろそろ飽きてきている人もいるだろう。
まだまだあるが、ここらで一休みして、少したわいのない話でもしてみようかと思う。
久しぶりに生まれ故郷、静岡を訪れて様々なことを思い出した。映画に熱中していた頃、プラモデルに熱中していた頃、そしてフォークソングに明け暮れていた頃。
特に、子供の頃は映画が好きだった。初めて観た映画というのは、おそらくこれだったろう、というものを思い出した。タイトルまでは定かではないが「連合艦隊司令長官、山本五十六」というような感じ。
僕はまだ6~7歳だったと思う。
父に連れられて、近くの南風座という、かなり小さな映画館に行った。混んでいて後ろのほうで立っていた記憶がある。
そして、しきりに「どっちがいい人?どっちが悪い人?」と訊いていた。
それから後は、よく覚えていないが、とにかく洋画に移行するまでは東宝の怪獣もの、例えば「モスラ」「マタンゴ」勿論「ゴジラ」も。今思い出したが「日本誕生」なんていう映画も観に行った。それにご存知「月光仮面」この辺までが日本映画。
中学生くらいからはもっぱら洋画に走った。
はじめて観た洋画はジョン・ウエインの「荒鷲の翼」とかいう映画だったと思う。
それからはジョン・ウエインの映画に明け暮れた。戦争映画、西部劇、どれをとってもカッコよかった。
スティーブ・マクイーンもカッコよかったし。「荒野の7人」は最高だったし「大脱走」も素晴らしかった。
これを読んでいる人のなかにも懐かしいな、と思う人がいるだろう。
結局、そうした映画の影響でモデルガンやプラモデル、そしてブルージーンズなどにも憧れるようになった。
よくあるふつうの男の子像だ。
自分の中のベスト5くらいは挙げてみようかな。
古い映画だと
1 荒野の7人
2 史上最大の作戦
3 橋(ドイツ映画)
4 西部開拓史
5 ナバロンの要塞
新しいところでは
1 未知との遭遇
2 戦場のピアニスト
3 ET
4 AI
5 トップ・ガン
勿論、他にも想いだせばまだまだ出てくるだろう。
映画もお金がかかるし、時間もかかるのであまり映画館にも出向かなくなった。昔は2本立てや3本立てなんていうのがあって、休憩時間にはお菓子や飲み物を売っていた。
つまらない話で申し訳ないが、映画は今の自分を形成しているひとつの要素になっているものかもしれない。
次はプラモデルなんかについても書いてみたいが、そちらのほうは中川イサトさんには負けるかな。
思い出 ~プラモデル編~
多分、小学校の4~5年くらいから凝りだしたものだろう。子供のころ「丸」という本を読みあさっていた。丸は日の丸の丸だったろう。1948年から出版されていた月刊誌、ということだ。
激戦地から戻ってきた父親に色々なことを聞きながら…。彼は最初サイパン島に配属になった。もしそのままサイパン島にいたら、今の僕はいなかったかも。
ともかく、後にトラック島に配属が変わったそうだ。だから、なんとか生き残って帰ってきたが、かなりの激戦地であったことに変わりはなさそうだ。
戦艦大和がトラック島に寄港した時には、まるで山がひとつ増えたようだった、というような話しを聞いた覚えがある。
グラマンの操縦士の顔が見えるほどの至近距離での機銃掃射の話し等、子供の僕には実感のない、ただただかっこいい話しに聞こえたもんだ。
そんな中でプラモデルに興味を持ちだしたのは、やっぱり零戦からだろう。あの美しさはとても言葉では表せない。
世界的に見ても最も美しい飛行機のひとつだろう。僕がよく作ったのは日本のものでは隼、紫電改、アメリカものではP-51ムスタング、カーチスP-41、P-38ライトニング(山本五十六の搭乗機を落とした)他にはドイツのメッサーシュミット、フォッケウルフ イギリスのスピットファイヤー、そこら辺が戦闘機では圧倒的だった。
爆撃機でもっとも美しいものはB-17だと思うが、その思いは今も変わらない。因みにこの機はほとんどヨーロッパ戦線で使われたようで、僕の父のところにはB-25ミッチェルが来て雨あられと爆弾を落としていったそうだ。
僕らの家の隣はアメリカから来た宣教師さんで名前が“ミッチェルさん”だったが、“昨日の敵は今日の友”だ。
一日に数回プラモデル屋さんに行っては、いろんな縮尺のいろんな機種を買い求め、プラカラーもきっちり揃えて、先出の“丸”を見ながら、マークや数字も手描で細かく描いたものだ。
そのころから少しグラフィック・デザイナーにも憧れていた。プラモデル熱が冷めてきたのは多分ギターに出会ったころかな。
時は中学3年くらい。間もなくフォーク・ブームが押し寄せてくるころだった。
Irish Music その19
Jug of Punch/Eddy Kelly’s (reel)
★ Jug of Punch
“この曲はかなり前にDale Russと演奏していたものだが、後年になって、John Williamsの素晴らしいアコーディオンプレイで聴いて以来、ずっと演奏している。もっとも彼はEmでやっていたが、オリジナル・キーはDmのようだ”
★ Eddy Kelly’s
“前の曲とのセットとして演奏する人が多い。EddyはCo.Roscommonのフィドラーで、この曲を1966年頃に10分ほどで書きあげた、という話だ。普通のリールテンポより少し遅いくらいのスピードが良い、という人もいっぱいいる。実際に美しいメロディを持った曲だし、それも確かなことだ。最初のころの録音物ではシングルで演奏されているのもそんな理由かもしれない”
Galtee Hunt/Stolen Apple (Set Dance/Waltz)
★ Galtee Hunt
“Clannadの演奏でかなり前に覚えた曲。ちょっと変わった拍数で覚えにくい曲である。
でも、なんとも言えない、初めはなんとなくダサいと思える曲でも、やりはじめるとくせになるような曲がたまにあるが、これもそのひとつかもしれない”
★ Stolen Apple
“Lunasaがやって有名になった曲。Slip Jigだという人もいるが、ワルツとして考えたほうが分かりやすいかもしれない。Grey Larsonによって書かれた可愛らしい曲。彼とはアメリカで一緒に演奏したことがあるが、セッションにヒョコっと現れて、「Hi, I’m Grey」
と言ったので「Hi, I’m Red, and This is Green」なんて言ってしまった。まさかGrey Larsonだとは思わずに。とてもいいフルート奏者兼コンサルティーナ奏者だ“
The Stage/The Messenger (Hornpipe)
★ The Stage
“僕自身はJames KellyやPaddy Glackinの演奏で覚えた曲。聴いたところ、かなり難しそうだが、希花がいい感じで弾いてくれる。日本ではあまり聴くことが無い曲だ”
★ The Messenger
“この曲はシアトルに住むJoel Bernsteinによって書かれた美しいものだ。Joelはシアトルに行くと、必ず一緒に演奏した仲だ。バンジョー、フィドル、コンサルティーナ、そして彼の代名詞でもあるハーモニカを全部自転車に積んでシアトル中を走り回ってセッションに出かける。そう、彼の昼間の仕事はバイク・メッセンジャーなのだ”
Jackson’s/Come West Along the Road (Reel)
★ Jackson’s
“Frankie Gavinの演奏で覚えた曲だが、本当にこのタイトルかどうかがわからない。しかも、2曲のメドレーであるが、ただJackson’sとしかクレジットされていない。しかし、フィドラーにとってはやりがいのある曲だと思う。
★ Come West Along the Road
“Gで演奏されることが多いようだが、僕らはAでやっている。Martin Hayesの演奏でもよく知られるポピュラーな曲”
Young Tom Ennis/Langston’s Pony (Jig)
★ Young Tom Ennis
“これは非常に変わったタイトルを持つ曲だ。このタイトルで知ったのはTony MacMahonの演奏からだが、本来はThe Banshee’s Wail Over the Mangle Pitという。Martin Hayesも不思議に思ってPaddy O’Brienに、一体このタイトルはどこから出てきたものかを尋ねたことがあるらしい。しかし、詳しい事はわからない。一説によると本来The Banshee’s wailらしいがPaddy O’Brienが後からOver the Mangle Pitを付け加えたようだ。どちらにせよ、多くの人にはYoung Tom Ennisのほうが簡単かもしれない”
★ Langston’s Pony
“古くはThe Moving Heartsの演奏で聴いた覚えがある。Moon Coin Jig という曲と、ある意味酷似しているので、メロディ楽器は大変だ。そういう意味でも伴奏者が曲を知らなければいけないことになる。同じような伴奏をしていたら惑わされてしまうだろうし、曲にも変化が出なくなる。こういう曲のひとつひとつの音にしっかり即した伴奏をすることが僕の信条だ”
Irish Music その20
The Oak Tree/The Foxhunter’s(Reel)
★ The Oak Tree
“僕がこの曲を初めて聴いたのは、おそらくDick Gaughanのアルバムだっただろう。スコットランドのシンガーである、彼のギター・アルバムだった。後年彼と同じフェスティバルに出演する機会があったので、ミーハーにも、少しだけお話させてもらったが、いかつい風貌から想像もつかないくらいに穏やかそうな人だった。美しいメロディを持った、3パートのリールで、多くの人が(しゃれではない)演奏している”
★ The Foxhunter’s
“これはThe Bucks of Oranmoreと共にエンディングに持ってこいの曲だ。GかAで演奏される。どちらで弾くのがよりよいか、という事に関する意見交換などもよくあるらしいが、Andrew MacNamaraとの演奏では交互にやった。それはそれは盛り上がるやり方だ。
フィドルではJames KellyやSean KeanがAEAEというチューニングで演奏するらしいが(勿論、キーはA)これはまるでBlack Mountain RagをAEAC#にチューニングする、ブルーグラスでの手方に似ている”
The Green Fields of Glentown/Tamlin/The Mouth of Tobique (Reel)
★ The Green Fields of Glentown
“初めて聴いたのはSilly Wizardのアルバムだったが、かれらは3パート目を抜かしていた。‘92年頃のことだ。セッションで弾いたら「あんた、Silly Wizardでおぼえたんでしょ」と誰かに言われたもんだ。Tommy Peoplesの作になるとても魅力的な曲で、典型的フィドル・チューンと言えるだろう”
★ Tamlin
“West Coast Seamus Eaganのバンジョー教則ビデオの最初の曲だ。彼はソーラスのSeamusとは違う。当時、オレゴンに住んでいたバンジョー弾きで、非常にパワフルなヒッピーである。Dale Russが最近、自転車に乗った彼を見たらしいが、あのぴちぴちのパンツだけはやめて欲しい、と言っていた。彼のことを僕らが呼ぶ時はこう呼ぶ。Seamus Reel Eagan。Reelを弾かせると、物凄く太い腕で、まるで大砲のような音量で、機関銃のように弾くからだ。Tamlinは初心者にもとても親しみやすい曲である”
★ The Mouth of Tobique
★ “この曲を初めて知ったのは、ジョン・ヒックスのプレイからだと思う。セッションでは大受けに受ける曲だ。作者は分からないが、カナダのTobique Riverというところで、Fiddlers on Tobiqueという集まりがあるそうだ。そんな意味でも典型的な、フレンチ・カナディアン・チューンのような気もするが、何故かTexas Quickstepというタイトルもついている。日本ではシャロン・シャノンの演奏で有名になった曲だろう。これをよく演奏していたころの彼女のバンドのフィドラーはAthena Targisだった。そういえば、彼女とあと数人の若者とセッション・サーフをしていたころから、彼女の得意曲だった”
Irish Music その21
The Graf Spey/Paddy Fahy’s #25/Never Was Piping So Gay/Hut in the Bog
★ The Graf Spey
“1884年に出版されたScottish dance Collectionの中にThe Rothiemurchus Rantとして記載されている曲だろう、といわれる。かなり古い時代にアイルランドに渡ったスコットランドの曲のひとつらしいが、僕はクレアにいた時に最もよく聴いた曲だ。多くの人が何かあるごとに演奏していた。キーは普通Cである”
★ Paddy Fahy’s #25
“結構難易度の高い曲だと思うが、希花がとても上手く弾く。こういう曲を弾くと、どこかAthena Targisと似ている。かつての彼女の相棒、Laura RiskとAthenaをたして2で割ったような感じかもしれない。そう言えば、僕自身は希花のフィドル・プレイはNollaig Caseyの音に似ていると思っていたが、ある時ジョン・ヒックスが偶然にも同じことを言ったのには驚いた。みんな素晴らしいフィドラーだ。彼女たちに似ている、というのは大きな賛辞だ。若いうちはそんな風にいろんな人に影響を受けて、やがて自分のスタイルを見つけ出していったらいい”
★ Never Was Piping So Gay
“Ed Reevyの作。このタイトルはW.B YeatsのThe Host of the Airという詩の最後の一節から取っているらしい。これもかなり難易度の高い曲だと思う”
★ Hut in the Bog
“Paddy Killoranの作でOn the Road to Lurganだ、という説、更にキーはEmだ、という話があり、普通Amでやることが多いこの曲のことを調べていたら、どうやらThe Cashmere Shawlという曲ではないか、というところに到達した。ただ、この曲は長い事Hut in the Bogとして知っていたのだ。Andrewのバンドの一員としてツアーしていた時に彼から習い、「タイトルはHut in the Bogって言うんだ」と教えてもらった。アイリッシュ・チューンではよくあることなので、こんな風にいろんな角度から曲のことを知っておくに越したことは無い”
Letter to Peter Pan(Air)
★ Letter to Peter pan
“Liz Carroll作の美しい曲で希花のお気に入りだ。自分のブログのタイトルにも使っているくらいに好きな曲。確かにどこかメルヘンの香りがする”
Air Tune/MacLeod’s Farewell (Air/Reel)
★ Air Tune
“Liz Carrollの作。とてもきれいな曲で、単独でもいいが、僕らはそんなに速くないリールを後に持ってきている”
★ MacLeod’s Farewell
“多くの人がWedding Reelという名前で覚えているだろうが、それはLunasaの影響である。本当のタイトルはMacLeod’s Farewell (written by Donald Shaw)という。作者はCapercaillieというバンドのメンバーでキーはEで書いた、ということだが、Sean Smyth以来みんなDで演奏する”
Irish music その22
Sailor on the Rock/Last Night’s Fun/Toss the Feathers(Reel)
★ Sailor on the Rock
“これは2001年にAndrew MacNamaraとレコーディングしたことのある、僕の大好きなセットの最初の曲。80年代にかなり人気のあった曲らしい。古くはEast Galwayの伝説的音楽家であるEddie Moloneyの演奏が有名だが、Frankie Gavinのそれは明らかに同じ地方の出であるEddieから習ったものだろうと言われている。因みに彼の息子であるSean Moloneyも演奏している”
★ Last Night’s Fan
“Joe Cooley’s #1ともKilloran’s Reelとも言われている、出どころが分からない曲だが、とても人気が高い”
★ Toss the Feathers
“様々なバージョンがある。最も有名なのはEmのバージョンだが、僕はそのBパートがあまり好きではない。Solasのバージョンもあるが、日本のプレイヤーたちにはこの二つが有名だろう。ここに登場するのはクレアーバージョンだ。最もすきなメロディ。この3曲をレコーディングした時Andrewはなにも言わずに目をつぶったまま弾き始めた。なにが出てくるかわからないままに進行していったが、キーはすべてDである。最後の曲を弾き始めた時、僕はまだこのバージョンをはっきり知らなかった。どこかで聴いたことがあるな、と思いながら弾いていて3まわり目くらいからToss the Feathersだと思ったものだ。Andrewと出会ってから9年目くらいの時。クレアのリズム、タラ・ケイリ・バンドのリズム、Andrewのたたきだすリズムは胸に響く”
Holly Bush/The Boy on the Mountain Top(Reel)
★ Holly Bush
“これも同じころTerry Binghamとレコーディングしたセットだ。Finber Dwyerの作。Terryのコンサルティ-ナ・プレイには心がこもっている。見た感じ、少し体重オーバーのシルベスタ・スタローンだが、めっちゃやさしい。彼についてはコラムの別な項目でも触れている。毎年アイルランドはドゥーランで一緒に演奏する希花も、最も好きなミュージシャンのひとり。シャイなわりに話し好きでもあるし、トラッドの本当の姿を音で教えてくれる素晴らしい演奏家だ”
★ The Boy on the Mountain Top
“この2曲のセットは何故か頭から離れない。いいメロディだ。この曲はもしかしたらフルート・プレイヤーに向いているかもしれないが、シングル・リールの美しいメロディをTerryが軽やかに聴かせてくれた。The Boy on the Hilltopとも言う”
The Cuckoo’s Nest (Hornpipe)
★ The Cuckoo’s Nest
“僕らはPaddy Keenanから習っているが、僕はブルーグラス時代、よく演奏した。あの時は今演奏している3パート目から入り(少しメロディは違うが)2パート目(ここも少し違う)を演奏した。その2パートの繰り返しだった。John HartfordやNew Grass Revivalで覚えたものだが、アメリカに渡って変化したものだろう。また面白い事にJackie Tarというタイトルも付いているが、僕らは全然違うJackie Tarをファースト・アルバムでレコーディングしている。もうなにがなんだかよくわからない、というところもトラッドの面白いところではある”
城田純二ソロアルバム「Music From Distant Shore」 残りわずか
「Music From Distant Shore」
2010年にリリースした城田純二ソロ・アルバムですが、残りわずかとなり、このホームページ上からの販売をいたします。
坂庭省悟との演奏でお馴染みのDa Slockit Lightのギター演奏からはじまる、全体的には
テナー・バンジョーのアイリッシュ・チューンがメインのアルバムです。
ベースに河合徹三さんを迎え、さらに珠玉の一曲として、パディ・キーナンがロー・ホイッスルを吹いています。アイルランドの至宝、パディ・キーナンをして「このトラックを俺のアルバムに入れたい」と言わしめた迫真の演奏が入っています。
また、彼の生い立ちの話しの中から生まれた、城田純二オリジナル曲、Paddy’s Napも収録しています。
オーダーはこちらのページから→10strings CDs
Irish Music その23
Gentle Dentist (Reel)
★ Gentle Dentist
“この曲を覚えたのはHarry Bradleyの演奏からだった。ある朝Athenaから電話があり、今度、若いフルート奏者と一緒に行くからギター弾いてよ、と言ってきた。そしてやってきたのがHarryだ。30分ほど練習して、4日間のツアーに出た。彼らについてはコラムで既に書いている。最初聴いた時にはBパートの不思議な進行に耳を疑った程に変わった曲だ。希花も同じことを言った。レコ―デイングされたものはおそらくひとつしか存在しないくらいポピュラーではない。Desi Wilkinsonの作。アイルランドに親切な歯医者なんていない、という人も多いが…。僕は生れてこのかた、出来た虫歯は1本しかない。それもつい最近。そしてすぐに治った。Gentle Dentistは希花には必要な歯医者さんかもしれない”
70th Year (Jig)
★ 70th Year
“これはかなり変な曲だ。CapercaillieのCharlie Mckerronのペンになる。以前レコーディングしたことがあったが、希花にこんな変な曲があるけど、何故か結構“くせ”になる、と言って教えたところ、やっぱり“くせ”になったようだ。Fから始まってBパートはDになる。おまけにメロディがなかなか考えられない進行で、これ以上変な曲は、なかなか存在しないだろう、と思われる曲だ。上記のGentle Dentistと合わせて変な曲を2曲掲載してみたが、どちらも僕らの頭の中から離れない。と言うことは、いい曲なんだろうか”
Humours of Ballyconnell (Hornpipe)
★ Humours of Ballyconnell
“いつどこで、また、誰が演奏していたか全く記憶にないのだが、変なメロディが長い事頭から離れなかった。そんなわけで僕らも音楽会では1回、あるいは2回くらいしかやっていない。しかし、これはトラッド好きにはたまらない変わったメロディ。常にレパートリーのひとつとして覚えておきたくなるようなものだ”
今回はあまり演奏したことがない、ちょっと変わった曲を掲載してみた。僕と希花は幸運にも音に関して好みが似ているので、変なのに好きになる曲、どうしても好きになれない曲、物凄く好きな曲、など、レパートリーも選びやすい。
レパートリーは多いに越したことはない。そして、それら全て正確に覚える必要がある。(あくまで僕の考え)その上、厄介なのがリズムだ。弾く人の出身地などによっても変わってくる。
最近思うことだが、これはもう生活のリズムだろう。幸運にも僕はアンドリューと寝食を共にし、パディ・キーナンやフランキー・ギャビンといったような超大物とかなりの間共にツアーをしている。あの面倒くさかったトニー・マクマホンとも何日も共に過ごして対等にやりあったし、彼らの生活のリズムというものも垣間見ることが出来た。
僕がアイルランドで希花にいろいろな演奏家を紹介するのも、ただただこの音楽を勉強するためだけではない。彼らの話しを聞いたり、一緒に食事したり、彼らの大切な自然の中を一緒に歩いたり、そういうことが大事だと思っている。
しかしここまでくるとちょっと可哀そうな気もする。深く彼等と付き合えば付き合うほど、この音楽の素晴らしさに惹かれてしまう。もっと簡単に気軽に楽しめれば良かったかもしれないのに。
でも、それはそれでいいだろう。希花も音楽に限らず適当な気持ちで物事に対処できない性格だし。
希花が生まれるよりはるか前、僕はヴァージニアで毎朝ジャネット・カーターの作るグレイビービスケットを食べ、ジョー・カーターと共に農作物を植え、川にボートを浮かべて晩ごはんのナマズを釣って、夜には村の集会に出て演奏した。
本当の意味でのオールド・タイム生活を垣間見たものだが、それはアイルランドでの生活とほとんど変わりはない。かけがえのない経験だ。
希花にも、もっともっと経験してもらおう。なめくじの一匹や二匹でピャーピャー言っているようでは…しかし、それでよく解剖なんて…と言うと、解剖でなめくじは出てこない、と言いやがるし、なかなか一筋縄ではいかないが、いいフィドラーになってほしいので我慢がまん。
Irish Music その24
Tom Ward’s Downfall/Hunter’s Purse/Dinny O’Brien (Reel)
★ Tom Ward’s Downfall
“Jody’s Heaven当時から演奏しているセットの最初の曲で、かなりポピュラーなものだ”
★ Hunter’s Purse
“これも、誰もが知っているくらいの曲だが、最も衝撃を受けたアレンジメントはギタリストのArty McGlynnによるものかもしれない。エレクトリック・ギターとパーカッションを駆使した独特なサウンドとリズムで、僕はこの音楽を始めた当初からよく聴いていた。Bパートのコード進行は今までに無かった独特なものだ”
★ Dinny O’Brien
“Co. Tipperary出身のPaddy O’Brienが父親Dinny(フィドラー)のために書いた曲とされる。ロビン・ピトリーも大好きだったとてものりのいい曲だ”
The Boys of the Lough/The Tap Room/The Galway Rambler (Reel)
★ The Boys of the Lough
“有名な曲だ。1930年代のEd Reavyのものが最も知られるかたちだが、他にもPaul BrockやThe Boys of the Loughの演奏で知られている。僕らは僕の以前のバンドである、
Tipsy Houseのアレンジからこのセットを演奏している。
★ The Tap Room
“Mary MacNamaraの演奏でよく知られるが、The Tap Room Trioの演奏が一番だ、という人も多い。僕は先の曲から2小節空けて(ギター)この曲に入るやり方を創り上げて大層受けたものだ”
★ The Galway Rambler
“この曲をひっつけたのは僕だ。先の曲からの音の繋がりはとてもスムーズだと思う”
Irish Music その25
Killavil/Paddy Canny’s/Drag Her Round the Road/John Brady’s (Jig/Reel)
★ Killavil
“比較的有名なジグだ。Killavilは、かのMichael Colemanが生まれた場所。Co.Sligoにある”
★ Paddy Canny’s
“前曲とのつながりが良く、Tipsy House時代からやっていた曲で、とてもムーディな響きがある”
★ Drag Her Round The Road
“ジグからリールと、リズムが変わるが、音の関連性があるため非常にスムーズに繋がる。これもTipsy House時代から組んでいたセットだ”
★ John Brady’s
“僕らは最後にこれを付けてみた。Gの曲だが、頭からCで始まる。ただ最初の一発がCであるだけなので、そんな時リード奏者は伴奏者にCと伝えるがすぐにその次のGを把握するかが伴奏者の度量である。ましてや聴いたことが無かったりしたら、勘で行くしかない。しかし次のパートでは、もう勘では許されない。確固たる理由が必要となるため、曲の把握は即座におこなわなくてはならない。伴奏者の難しい、そしてやりがいのあるところだ”
Sgt. Early’s Dream/Blocker’s/Dan Breen/ Palmer’s Gate
★ Sgt. Early’s Dream
“いつ覚えたか定かではないが、多分Dale Russの演奏で聴いたのが最初だったか、それ以前から知っていた曲かもしれない。マイナー調のとてもいいメロディの曲だ。
★ Blocker’s
“これは明らかにDaleのセットで覚えた。この繋がりはとてもいい。ただ、これを書いたのはTipperaryのフィドラー、Sean Ryanで、オリジナル・キーはGらしい。その後なぜかFrankie GavinがDで演奏してからそのキーで知られるようになった、ということだが、僕らもDでやっている。とにかく前曲との繋がりがいいのだ”
★ Dan Breen
“West Clare Reelとしても有名な曲。僕らはAmとBmの両方でやっている。この曲に関して僕は、かの名曲「Summer Time」でよくつかわれるコード進行を利用している”
★ Palmer’s Gate
“LeitrimのJoe Liddyのペンになる曲。Darvishの演奏で有名かも知れない。Maj7thが多用できる若者向きの曲のような気がする”
Irish Music その26
The New Mown Meadow/The Bag of Spuds (Reel)
★ The New Mown Meadow
“O’Neillの本ではThreepenny Bitというタイトルで掲載されている。Bパートで転調するとてもエキサイティングな曲だ”
★ The Bag of Spuds
“この曲をくっつけたのは、サン・フランシスコに住むパイプ奏者のTodd Denmanだ。素晴らしい録音を古くからの友人であるDale Russと共に残している。この2曲のセットが入っているのは、消防士でフィドラーのBill Dennehyとのアルバム「Like Magic」だ。このアルバムでは、同時にGerry O’Beirneの素晴らしいギター・プレイも聴くことができる”
Byrn’s/Cronin’s (Hornpipe)
★ Byrne’s
“とてもポピュラーな曲で初心者向きでもある。むかし、De DannanがWill You Merry Meという唄とひっつけてやっていた。75年くらいのアルバムだったか”
★ Cronin’s
“Dennis MurphyかPaddy Croninで有名な曲。これも比較的初心者向きであろう。よく知られたメロディだ”
Poppy Leaf/O’Callaghans (Hornpipe)
★ Poppy Leaf
“あまり知られていない曲だが、美しいメロディだ。僕はKieran Hanrahanのプレイから習った。Brian Rooneyの演奏も素晴らしいというはなしだが、まだ聴いたことが無い。たしかFrankieもすごいスピードでやっていたと思う”
★ O’Callaghan’s
“Mickey Callaghan’sとしても知られる曲。BパートでEmにいくところが非常に魅力的な曲だ”
近況
暫し新しいCDの録音で忙しく、コラムもあまり更新していませんでした。おかげさまで形になりそうです。
今回はMusic in the Airでの、ギター、フィドル&ハープに加え、バンジョーもコンサルティーナもボーカルも、ちょっとだけマンドリンも入っていてにぎやかです。
そして、もうすぐアイルランドへ行くので、また暫くお休みしますが、帰ってきたらアイルランド紀行をお楽しみにしていてください。
帰ると同時に京都へ行き、それと並行してCDのジャケット製作にはいらなければなりません。
なので、更新も少しゆっくりになるかもしれませんが、気長におつきあいください。
そういえば、アイルランド紀行で想い出しましたが、週刊朝日で「司馬遼太郎の街道」という連載をやっています。そこに希花さんが登場します。こちらも“乞うご期待”です。
それでは、留守の日本をよろしくおねがいします。
2013年 アイルランドの旅 7月23日~24日 ダブリン~エニス
7月23日、くもり。気温16度。今ごろ日本はとんでもない暑さだろう。こうして時間はかかれども空を飛んで海外に来れるなんて、ライト兄弟に感謝だ。
ダブリン空港に着くと示し合わせた様にギターが出てこない。
去年と同じようにケース全面に大きく「DUBLIN」という紙を、ごていねいに裏にも表にも貼っておいた。
チェックイン・カウンターでも、乗り換えがあるので充分気を付けるように言っておいた。ただ、日本人相手なら間違いない事は分かっている。
飛行機の中では、さすがJAL系列だ。CAの人に事情を話すと、パリのドゴール空港に電話して乗り換え便を間違えないよう、パイロットから連絡を入れてくれる、という。
ここまでは日本人相手だ。
ここから先はもう人間相手ではない。
そこまでしてくれたのにやっぱり僕等と同じ飛行機には乗っていなかったのだ。猿なみだ。
だがダブリンの空港の荷物係の女性がとても熱心になってくれて、結局、僕らが移動するエニスに10時間ほど後にタクシーで届いた。
取りあえず、そんなこんなで疲れたのでその日は爆睡してしまった。
7月24日 エニス。雨。気温15度。
明日からDoolinに行くつもりでTerryと電話で話したが、彼は今Kinvaraというもう少し北のCo.Galwayに住んでいるという事だ。でもDoolinにはセッションで必ず出て行くから会えるらしい。
少し仕切り直しを、と考えていると誰かから電話だ。「おーい、じゅんじ。仕事だ。Kerryまで明日来い」ブレンダン・ベグリーだ。
ちょうどいい。今日が水曜日。テリーがDoolinで誘ってくれたのが月曜、火曜だ。それまでブレンダンのところに居ればいい。上手い具合に予定が立った。
こうなったら、少し楽器もひいておかなくちゃ、と思い、近所を見渡すと、むかしアンドリューと何度か一緒にやったキーランズというパブがある。たしか去年ジョン・キングとやったのもここだ。その時オーナーがぼくのことを覚えてくれていた。
よし、ここでやらせてもらえないか頼んでみよう、と思ったところ「おー、来たか。二人で好きなだけ飲んでいいぞ。そこのテーブルでやってくれ」
日本のアイリッシュ・パブの迷惑そうな対応とは違う。大体、飲み客にとって訳の分からないトラッド・アイリッシュが日本の場合迷惑なんだろう。アイリッシュ・パブなのに。
店に勤めている人もほとんどが“いけいけ、いぇいいぇい音楽”がいいのだろう。アイリッシュ・パブなのに。
8時から2時間ほどやらせてもらい、少しだけ飲ませてもらい(まだ時差ボケなのでご勘弁を、といって限りなく出てきそうなギネスを断った)そのままブローガンズにいくと、大きなセッションの中にオーイン・オニールとイボンヌ・ケーシーがいてにっこりここに入れよ、と合図をくれるが、あまりに沢山の人なのでひとまず挨拶だけにしておいた。
通りを歩いていると軽快なバンジョーの音が聴こえて来た。
窓越しに中をのぞくとこちらに気が付いたマーカス・モロニーが入ってこい、と首を振る。5~6人の質のいいセッションだ。
なんともうひとりのバンジョー弾きは前々から観たかったデシ・ケリハーではないか。それにフィドラーはシボーン・ピープルだ。こちらは希花のアイドルの一人。
それにサラ・コリーもいた。
1時過ぎまで一緒にやって、戻った。
みんな、いい友達だ。
旅の初めにふさわしい、いい音楽といい出会いがあった。
明日からCo.Kerryだ。
2013年 アイルランドの旅 7月25日~ Co.Kerry
7月25日 よく晴れていて涼しい。エニスを出て一路ディングルへ。“テスコ”というスーパーでブレンダンと待ち合わせている。
相変わらずパワー全開のブレンダンが「家にサーモンがあるからみんなで食べよう。みんなといっても、もう子供たちもそれぞれ違うところに住んでいるし、俺しかいないけど」と言う。
じゃあご飯でも炊いて久々に塩ジャケでも食べるか。すでに日本食が恋しくなっている。「内緒だけど、海で釣ってきたやつだ」と自慢げに話すブレンダンも、ずっと前からだが結構日本食には興味を示している。
寿司も作ってくれという彼の要望に応えたいが、まず安全性から確かめなくては。一応冷凍はしたようだし、見たところ大丈夫そうだ。後は購入してきた醤油と米酢。のりは彼が前に買ったものがあるといってだしてきたものが、“のり”とは言い難いものだったが、仕方ないだろう。これを使って得意のサーモン・スキン・ロールでも作ってあげよう。
しかし、問題は包丁だ。アイルランドのどの家庭でも、切れる包丁に当たったことは無い。それから最も大事な衛生面だ。
泥んこの靴のまま家の中に入ってダンスをする人達だ。
一応、まな板と呼べそうなものを熱湯消毒し、洗剤で洗って、さらに熱湯消毒し、サラも包丁も洗い直してからでないと病気にでもなったら 大変だ。
まぁ、彼らなら大丈夫だろうけど、なにせ食べつけない食材だし。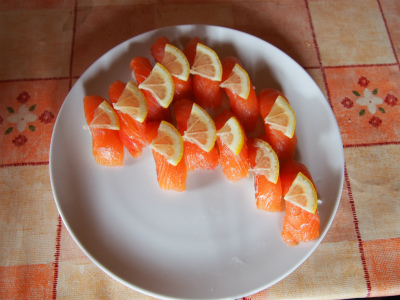
白身のチキンのピーナツソース和えと、じゃがいもとアボカドのサラダを添えて、それでも豪華な食事ができた。
今日7時半からDingleの楽器屋さんでコンサートをやるのだ。ダンスもあり、ブレンダンと長男ブリアーンとのデュオあり、店のおやじのアコーディオンあり、僕と希花の演奏ありで、約2時間。
30人ほどのお客さんだが、さすがに地元だ。拍手の大きさが日本での100人規模のコンサートくらいで、みんなにこにこして体を乗り出して、リズムを刻みながら聴いている。
ところで、店のおやじと一緒にフィドルを弾いたのが、かの有名なるフィドラー兼コンポーザーであるMaire Breatnachだと知ったのは次の日になってからだ。そのあとセッションにまで一緒に行ったのに。
12時頃、真っ暗なブレンダン家に到着。山に囲まれた牧草地のあちこちから羊の鳴き声がときおり聞こえてくる。家のあかり以外は辺り一面真っ暗闇だ。
外からブレンダンの大声が聞こえた。「おーい、ふたりとも出て来いよ。ドラゴンがいるぞ」
何事かと思って外に出てみると、つい2時間ほど前に暗くなった空に月があがり、浮かんでいる雲がドラゴンのような形をしているのだ。それでも段々崩れていくその雲を観て大笑いする彼はまるで無邪気な子供のようだ。
しばし、静寂と暗闇の中、空を見上げる3人。時計は1時をまわっていた。
7月26日 晴れ時々雨
8時半に起きてブレンダンが1時間ほど走ろうというので、勿論!と言ってついて行った。希花さんはまだ夢の中だ。
羊の糞を踏みながら、大西洋を見下ろす丘を越え、山を目指す彼はこのコースを走り慣れているのだろう。こちらにとっては山登りという感じだ。
よく晴れている大空と広大な大地。人ひとりいない草原とそびえたつ山。眼下には大西洋の波が岩肌にしぶきを当てている。
僕らの愛してやまない音楽が生まれたところだ。
戻ってきてシャワーをあびると、半ズボン一枚になったブレンダンが「さぁ、山に音楽を捧げるぞ」と言って、やにわにアコーディオンをかついで裏庭に座った。
ちょうど正面に山がある。そこに向かってエアーやポルカを弾くブレンダン。こんなシーンを見てしまうと、やっぱり生半可にこの音楽は出来ないな、と思ってしまう。
その騒ぎに希花さんも起きてきた。ちょうどよい。このシーンは絶対に見ておくべきだ。日本から来るアイルランド音楽を目指す人達の多くが触れることのできないシーンかもしれない。そしてもっとも大切なシーンのひとつだ。
昼から3人でディングルへ出かける。コーヒー・ショップで地元の人達と会話に興じて家に戻り、晩ごはんの最中にとんでもない計画が持ち上がった。
3人でボートにのって海に出ようというのだ。ボートは庭に置いてある。よく観光地で湖に浮かんでいるくらいのおおきさの、もっと頑丈そうだがボロボロのやつだ。
「ここに二人分ライフジャケットがあるから着けたらいい。じゃいくぞ」ちょいちょいと車に接続していざ出発。希花さん恐怖。
船着き場でウエットスーツを来た彼の友人が写真を撮りたいから一緒に乗せてくれるか、と尋ねる。プロのカメラマンらしく、水平線の写真を撮りたい、と言うのだ。
「3人乗りで4人乗った試しは無いけど…」といいながら小さくて細い希花を見て「大丈夫だろう。そのかわり絶対に立ちあがらないこと、重心は常に真ん中だぞ」と言って船を出す。
希花さんぴゃーぴゃー。ブレンダンは物凄い腕力で沖を目指す。「ブレンダン!もういい!ここで充分!もういい!」とひたすら叫び続ける声を無視して沖へ沖へと。そろそろ海も暗くなりかけているが、まだまだ美しい空と水平線がきれいに見える。波はそれなりにある。僕のうしろからぴゃーぴゃー声が聞こえる。
ブレンダンが糸を垂らすと、あっという間に30センチほどのたらが釣れた。慣れたものだ。さぁもっと行ってみよう、とブレンダン。ぴゃーぴゃーはさらに大きくなる。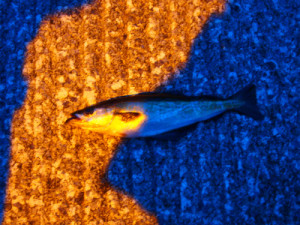
カメラマンが希花に水平線を見れば絶対に酔わない、と教えてくれる。遠くに見える岩肌なんか見てると酔うから、とにかく水平線を見ていなさい、と。少しぴゃーぴゃーが治まった。
段々暗くなってきた。雨も少し落ちてきた。やっと帰る気になったブレンダン。船着き場に到着すると先ほど釣れた魚を不器用に3枚におろしアイスボックスに入れた。明日、娘のクリーナに会うからこれをクックして食べさせると言うのだ。良かった。これで寿司を作ってくれと言われなくて。
しかしこれもいい思い出になった。希花さんにもそうだろう。ここからも力強い音楽が生まれているのだ。
アンドリューからメッセージが入った。8月11日、フィークルのペパーズでギグらしい。彼のメッセージはいつも短い。
じゃ、その日か前の日に会おうぜ、と僕も短いメッセージを送って眠りに就いたが、まだ体が揺れているようだ。
7月27日 晴れ時々雨
11時からレコード店(前日とは違う所)でちょっとした店の宣伝を兼ねた演奏を3曲やってそれを撮影させて欲しいという店主のおばちゃんの要望があり、出かけて行った。
ちょうどエニスのカスティーズでの撮影のような、もうちょっとそれよりも店の宣伝ぽい感じだが。
11時からと張り切って言っていたおばちゃんは11時半になっても現れない。「いつもこうなんだよ」とブレンダン。そういえば彼は時間には正確だ。
やっと来たおばちゃん。「さぁ、始めましょう。タイム・イズ・マネーよ」ここはつっこむところだ。「あんたが言うか!」
無事終了のあと、今日は4時からシェーマス・ベグリーの息子でコンサルティーナ奏者のオーインとの演奏がSmall Bridgeというパブである。
そのあとはブレンダンの長男ブリアーンとオーインがシェアーしているアパートに泊めてもらうのだ。
コンサルティーナ、フィドル、ギターの三人の演奏は心地よい。オーインもかなりの腕前だ。3時間ほど演奏していい気持になり、戻ってから豚の生姜焼きを作って「トンとご無沙汰」なんていいながら食べて、気持ちよく寝ていたら、11時ちょっと前にブリアーンから電話。慌てた様子で「Mighty Sessionというパブに今から行って希花とふたりで演奏してくれ。今日オーインとやったところの隣だ。金はちゃんと出る。いますぐ行ってくれるか?」
慌てて「なんだかよく分からないけどギグらしい」と希花を起こした。歩いて10分ほどのところだ。雨が結構降っているがなんとかなる。
行ったパブは結婚式のアフターパーティでもしていたのか、30人ほどの若者が思い思いのコスチュームで大騒ぎしている。
バーテンダーに「おい、まさかここでやれっていうんじゃないだろうな」と聞くと「ま、ここでだ」と向こうも悪そうに言う。
「状況を見てから早く帰ってもいいぞ」というので「金は出るんだろうな」と確かめて取りあえずスタートする。
奥の30人程は大騒ぎしているが、手前の人達は興味を示してくれている。しかしこんな状況なのでオーナーが1時間で開放してくれた。それでもお金はちゃんともらえた。Co.Kerry最後の夜、またまたあまり出来ない経験ではあった。
2013年 アイルランドの旅 7月28、29日、30日 Ennis~Doolin
7月28日 晴 Dingleを12:20のバスで、まずTra-leeに着く。そのころにはすごい雨。待合室のすぐ近くでコーヒーを買い、昨日買ったチョコレート・ファッジ・ケーキと一緒に食べる。あー、コレステロールが…。
ちょっとバスの乗り継ぎが悪く、6時過ぎにエニスに着く。
少しは休むつもりだったが、近くでジョセフィン・マーシュがセッションをしている。そこで、Brogansというパブだが、出かけてみよう。
ジョセフィンとイボンヌ・ケーシーが「あ、来た来た」と出迎えてくれる。15人ほどの質のいいセッションだ。
コンサルティ-ナを弾く小学生くらいの女の子も二人いる。ふたりとも、どこからみてもクレアー・スタイルをきっちり教わっている子だ。
そのうちの一人がディッパーというメーカーの素晴らしいコンサルティーナを持っていた。希花さん、早くも興味津々。なんでも、タッチが軽く、今彼女が使っているものより弾きやすいそうだ。もちろん彼女が使っているサットナーも超一流品だが、かなりパワーが必要な楽器らしい。
こうなるとマーチンを持っていた人がローデンを弾いてみて、これも欲しいな、と思うある種病気みたいなものだ。
でもその病気がどんどん上達していく結果を産むこともあり得る。そうでない人もいるが、彼女の場合、機会があったらどんどんアプローチしていけばいいと思う。
赤嶺君がブズーキを持って現れた。もう長くアイルランドに住む人だ。しばし楽しい話しに華が咲く。とても熱心で一途なひとだ。
結局、彼と別れたのが12時半頃。ジョセフィンもイボンヌもほかのメンバーもすっかり帰った後まで赤嶺君と話し、またフィークルでの再会を約束して別れた。
7月29日 晴れ後雨
Doolinに行く時は何故かいつも雨が降っている。それでも出るころにはあがったので、ラッキー。
お昼すぎに目指すMcGanne’sというパブ兼B&Bに到着。テリーが8時過ぎに寄ってくれるので、まず腹ごしらえ。
このパブのシチューは美味しい。パスタも。アイルランドでも数少ない“美味しい”と言える所だ。
夜はO’Connorsというパブで、クリスティ・バリー、ジェイムス(ラストネイム訊き忘れた)とテリー、という去年と同じメンバーによるセッションに参加。
3人とも素晴らしいトラッド・ミュージシャンだ。
テリーはよくこう言う。「この世で本当のトラッド・アイリッシュをやる人間は数少ない。みんなすぐにかたちを変えたがる。今そこら中で聴かれるアイリッシュ・ミュージックは決して本物ではない」
そんな頑固な彼が、必ず僕等を呼んでくれると言うのは本当に嬉しい事だ。若い希花も、見せかけではない本物のアイリッシュ・ミュージックにどっぷりつかることができるのだ。
比較的早く、1時頃帰る。
7月30日 晴れたり雨だったり。
しかし、午前9時には晴れる。どうせまた降るかもしれない。晴れているうちに、テリーが薦めてくれたウォーキング・コースを歩いてみよう。
遠くにモハーの断崖が見渡せるパノラ マのような風景をひたすら歩く。ゆったりした風を体に受け、彼らの音楽を生み出した全ての景色を見ながらのウォーキングは、本当にこの音楽が心の中に染みわたるような、そんな気がする。
マのような風景をひたすら歩く。ゆったりした風を体に受け、彼らの音楽を生み出した全ての景色を見ながらのウォーキングは、本当にこの音楽が心の中に染みわたるような、そんな気がする。
1時間ほど歩き、少し休んでからまた同じメンバーでセッションだ。テリ-には本当に感謝している。
素晴らしい音楽を、体で感じることの大切さを、そして本当のトラッド・アイリッシュ・ミュージックを教えてくれる彼にまたフィークルで会う約束をして1時頃戻った。
明日からゴールウェイだ。
2013年 アイルランドの旅 7月31日~ ゴルウェイ
7月31日 雨 肌寒い
朝、B&Bで少し音を出させてもらった。雨が降っているにも関わらず、乾いた張りのある音がするのはとても不思議だ。
11時45分のバスで2時頃ゴルウェイに着いた。これからしばらくはコーマック・ベグリーのアパートに泊めてもらう。
なめくじはいないだろう。一応、町のど真ん中だし。コーマックとも久しぶりの再会だ。日本でお世話になった、と感じているのだろう。いろいろ細かく面倒をみてくれる。その辺りもアイルランド人と日本人は似ているような気がする。
しばらくすると妹のクリーナが帰ってきた。僕等と入れちがいに出て行ったので、どこに行くのか訊いたら、泳ぎに行くと言っていた。雨の中を、だ。どうせ濡れるから、それに海の方が暖かいし、と言って出て行ったのだ。限りなくパワフルだ。いちばんブレンダンの血をひいているかもしれない。男ばかりのなかの兄弟のなかで唯一の女の子なのに。
次は一緒に行こうよ、と希花がさそわれたが、なめくじがいるかもしれないし、と訳の分からないことを言って断っていた。
夕方、パブを覗くとデクラン・コリーがやっていた。偶然入ってきたフランキー・ギャビンとも出会った。トイレを借りに来ただけだ。連絡をくれ。また一緒にやろう、と言って出て行った。
僕らも、このパブの裏にあるセント・ニコラス・チャーチで今晩演奏を頼まれている。正式には一週間後の水曜日に、僕等とメアリー・バーガンとのコンサートがあるのだ。
メアリー・バーガンはティン・ホイッスルの代名詞のような人だ。僕等にとっても共演できることは限りなく嬉しいことだ。
これもコーマックが設定してくれた。今晩はコーマックとクリーナの会にゲストとして演奏する。
素晴らしい音の響き。ステンド・グラスからこぼれる光。歴史のある建物の中で、観光客や地元のひとを対象に、夏の間、週3回、各地の有名なミュージシャンが演奏する。ここの牧師さんは、もとディ・ダナンとのツァーにも参加していた凄腕フルート吹きだが、全然そんなことを感じさせない。
おー、君たちか。よろしくね、と巨体で満面の笑みを浮かべてあっさりと挨拶してくれた。
ここではまた来週やるので詳しくはそのレポートの中で。
とりあえず、ゴルウェイ一日目はゆっくり過ごすことができた。
2013年 アイルランドの旅 8月1日、2日、3日 ゴルウエィ
8月1日 曇り
珍しく早起きしたコーマックがキッチンでコンサルティーナの練習をしている。
「いいリールだね。なんて言うタイトル?」「多分、Kit O’sheaだと思う」「次の曲は?」「これはJohn Brossnanだ」
そんな感じで2時間ほどがあっというまにすぎて行く。
少し降っていた雨もやんだようなので、外に出てみる。今日は特に予定もないので町の様子を見に行くが、この時期のゴルウェイは人でごった返している。
有名なゴルウェイ・レースもあるし、なんやかやフェスティバルが目白押しだ。
町は観光客や、大騒ぎの大好きな若者達でいっぱいだ。こんな日は部屋でゆっくり過ごすのが一番。
パディ・キーナンやジョニー”リンゴ”マクドナーからメールが入った。また忙しくなるかもしれない。
8月2日 晴れ
洗濯ものを持って、コーマックと一緒にランドリーに出かける。その後、妹と日本食を食べに行くけど一緒に行くか?と訊かれるが、
僕らはマックでいい、と、そこで別れる。
ついでにちょっとバスキングでもして洗濯代を稼ごう。ここでは20~30分やれば洗濯代くらいには十分なるし、その気になれば晩ご飯代にもなるが、
そこまでの気もないし、早々に引き上げてマックへ。
Wi-Fiがいちばんつながりやすくて長居できるのはマックだ。いろいろ調べなくちゃならないこともあるし。
今晩もゆっくりして今後の計画を練ろう。しかし、すぐ近くにCrainsというよく知られたパブもあるし、今日くらいは行ってみるか、と外に出る。
Crainsは町の喧噪とは少し離れたところにあるので、行きやすい。
店の前につくと2階からブルーグラスのようなサウンドが聴こえて来た。一杯の人をかき分けてのぞいてみると、見た顔がベースを弾いている。
ずっと前にロハウンズでアメリカに来て、その後デシャールやジョセフィン・マーシュ・バンドでも活躍していたベース・マン、ポール・オドリスコだ。
アイリッシュは勿論のこと、ブルース、ジャズ、ブルーグラス、それに渋いボーカルも聴かせるベテラン・ミュージシャンだ。
バンドも女性二人、男性二人、ギター、マンドリン、クラリネットなどを使い、コーラスがばっちり決まった、なんとも独特な音楽を聴かせてくれる。
みんながよく知っている曲などを、いっぱいのお客さんと一緒に歌い、やんやの喝采を浴びている。素晴らしいグループだった。
ポールとは12~3年ぶりの再会を祝して12時半頃帰宅するが、3時頃ブレンダンが来るらしい。くわばらくわばら、早く寝たふりを決め込もう。
8月3日 晴れ
夜中にブレンダンが来た形跡はなかった。ゆっくり眠れたようだ。それでも予定を変えた彼が現れたのが11時頃。そのままケリーへ向けて車を飛ばすらしい。彼の場合、すっ飛ばすという表現がピッタリかも。
僕らは今日、リンゴとのギグが6時からTi Coilisである。その前に昼飯でも一緒に食べよう、という話になり、Monroesという、ちょうどコーマックのアパートの隣にあるパブで待ち合わせる。
リンゴはとても面倒見がよく、日本人の多くはアイルランドに行ったら、まずリンゴに連絡したらなんとかしてくれると思っているらしい。
また日本の巷では、初めてアイルランドを訪れる若い人たちに、簡単に「リンゴとコンタクトを取ったらいい」という話まで出ているらしい。
実際には彼にとって少し重荷になりつつあるようだ。「なんとかしてあげたいが、見も知らず人に、今ダブリンに着いたけど迎えに来てほしい、などと急にいわれても困惑してしまうんだよ」
お人好しのリンゴだからこそ抱える悩みなんだろう。
そんな話をしている最中にフランキーが、これから会おう、とメールしてきた。
リンゴにその旨を伝え、6時にTi Coiliで会う約束をして、僕らはフランキーの指定したCrainsに向かった。
現ディ・ダナンのアコーディオン奏者も加わっての2時間ほどのセッションに興じ、6時からリンゴとのギグ。
カレーを食べて別れてから、帰り道にあるアイルランド語パブというコアなパブに寄る。今晩はここでもいいセッションがあるらしい。
若者たちのセッションだが、どうもアコーディオン奏者とブズーキ奏者とは12~3年前に一緒にやったことがあるということだ。
そんなに前だったら彼らはまだ少年だったのだろう。「日本人でこれだけのギターを弾く人はそんなにいないだろう。だから覚えているのさ」
確かにアイルランド人で信じられないくらいの演奏をする子供達はごろごろしている。
しばし、若者のパワーを体に感じて、12時半ころ帰宅。どっと疲れて爆睡。
2013年 アイルランドの旅 8月4日 快晴
今日はリンゴが僕等をコネマラに連れて行ってくれる、ということだ。「コネマラってどんなところ?」と希花が訊く。「うーん、何にもないところ」
実際、荒涼とした土地が広がり、奥へ奥へ行くとアイルランド語しか通じなくなってくる。
僕は10年ほど前に訪れたことがある。その時は、雨が降ったかと思ったら、瞬く間に陽の光が差し、そしてまた雨が降る。パノラマのような景色の中には人っ子一人見当たらない。
羊が道路わきにまで出てきて「バァァァ~」と鳴く。そんなところだったが、 きょうは珍しいくらいの快晴だ。でも、おそらく景色は何一つ変わっていないだろう。
きょうは珍しいくらいの快晴だ。でも、おそらく景色は何一つ変わっていないだろう。
車の中でリンゴお気に入りの音楽を聴く。驚いたことに“ライ・クーダー”あり、“ザ・バンド”あり、オールドタイミーからブルーグラスまで、ほとんどぼくが聴いてきた音楽と一緒のものを好んで聴いているようだ。
若い人達とはなかなか盛り上がれない話題も、僕とならいっこうにとどまるところを知らない。
何故か去年、初めて会った時から僕と希花のデュオをえらく気にいってくれていた。多分、トラッドをリスペクトしている姿をわかってくれたのだろう。
「最近のバウロン奏者は曲も知らないで叩いている。そんなのはひとつの音でわかってしまうんだ。あ、こいつ他人の音聴いてないなって。お前のソロじゃないぞ。お前はなんでここにいるんだ。やめてしまえっていいたくなるよ」
バウロンという楽器で、その名を世界に轟かしている人だ。さすがに見る目が鋭い。やっぱり、リード楽器の人と同じように曲を知っている。
僕のやりかた(考え方)と一緒だ。
だいたい、曲を知らずに伴奏なんか出来るわけがない。希花も出来るだけたくさんの曲を覚えて、僕がどういう伴奏をつけるか聴きながら弾いたらいい、と僕は思っている。
そしてアイルランドに来たらその道のトップの人達からリズムを覚えたらいい。もちろんユー・チューブでもCDでも聴けるけど、生活と密着したリズムだ。
この厳しい自然の中から生まれた音とリズムをいっぱい体に受けて僕等は5時間ほどもコネマラに滞在した。

今日はゴルウェイに戻ってアンドリューとセッションだ。僕がゴルウェイに来ているのでリンゴが呼んでくれたらしい。
そういえば彼のメールに“See u on Sunday”と書いてあった。だから今度の日曜日はまだクレアーにはいかないのに、って思っていたけどこの事だったんだ。
彼の文章はいつも短すぎて難解(南海)ホークスだ。
途中、リンゴが「そうだメアリー・バーガンの家がすぐそこだ。寄ってみよう」という。「こんど教会で一緒にやるし、挨拶できるからちょうどいい」と僕も大賛成。
ティン・ホイスルというとメアリー・バーガンだ。彼女も「最近の若い人は基本を知らずにやっているから、私たちがきちんとトラッドを教えてあげなくちゃいけない」と盛んに言っていた。
教会ではリンゴも一緒に出てくれることになった。
さて、8時。場所はいつものTi Coiliだ。「Andrew!」「Junji!」といつものように大声で呼び合う。
それから先はまた大爆発だ。僕と希花でアンドリューを挟み、希花の横でリンゴがバウロンを叩く。
とどまるところを知らない音の嵐が続く。
アンドリューと演奏するのはすごく好きだ。リズムがたまらない。リンゴは着実にバウロンを叩く。いい伴奏、いい音楽、まさにそのものズバリだ。
興奮もさめやらないうちに1時近くになってしまった。帰りにチキン・バーガーとガーリック・マッシュルーム・フライをテイクアウトしてしまった。
僕のコレステロールは?…先生。
それにしても最高の天気にコネマラ観光ができて、やっぱり僕は晴れ男かなぁ。因みにコネマラになめくじはいなかったので、今日は静かだった。
2013年 アイルランドの旅 まだゴルウェイ
8月5日 晴れ
バンク・ホリデイということで、町のあちこちが休んでいる。もちろんパブは開いている。
夜は教会でLaoise KellyとKathleen Maclnnesのコンサートがある。素晴らしいハーピストとシンガーのコンビだ。
僕らもビラ配りに参加。
そのかいあってか(?)会場はいっぱいの人で埋め尽くされた。ほとんどが観光客だろう。しかし名前のある人達だ。地元っ子も来ているにちがいない。
素晴らしくプロフェッショナルなふたりだ。聴いていて寒気がするような演奏と歌をたっぷり聴かせてもらった。
今晩はもうどこにも寄らずに帰ろう。気持ちのいい音楽の後はワインでも飲んでサッと寝るのが良い。
8月6日 晴れ
今日はフランキーの兄である、ショーン・ギャビンと待ち合わせをしている。
「フランキーにフィドルを弾くように薦めて、最初にあなたが持ってきた曲がBroken Pledgeだった、という話しは本当なの?」と訊くと、「あー、そんなこともあったなぁ」と、懐かしそうに微笑んだ。
ショーンもかなり話し好きだ。そして他のアイルランド人と同じ、次から次へとよく飲む。
そして「今からどこかセッションができるところに行こう」と僕等を彼の知り合いのパブに連れていってくれた。
彼は弟のようにスーパー・スターではないが、いいアコーディオン弾きだ。僕は2002年だったかな。トニー・マクマホンと一緒にツアーをしていた時会ったことがある。
その時彼はDe Danannのアコーディオン奏者だった。
想い出話しやこれからの話し等に華が咲き、午前1時半頃帰宅。もっとも待ち合わせたのが9時ころだから、そんなもんか。
明日はいよいよ教会でのコンサートだ。Mareka&Junjiという名の知れない東洋人のコンサートにどれだけ集まるだろうか。
それでも、メアリー・バーガンもいるし、いい経験になるに違いない。
2013年 アイルランドの旅 まだまだゴルウェイ
8月7日 晴れ
妹のクリーナの友人がふたりほど泊まっている。コーマックはコンサルティーナ講師として、昨夜一足先にフィークルに向かった。
2日ほど前から考えていたことだが、今日が水曜日、一日おいて金曜日にJohn Cartyのコンサートが同じ教会である。アンドリューとのギグが日曜だし、それまでに行けばいいだろう。唯、それにはホステルをキャンセルせねばならない。
しかし、この時期フィークルには沢山の人が行くので、ホステルも引く手あまた状態だろうし、そんなに問題はないだろう。
そんなことを考えながら顔を洗い、歯を磨いているとみんながおきてきたようだ。ふとみると、僕は個人的にはあまり知らないが、希花がよく話していたアンドレアという若者が布団の中で携帯を見ていた。
確か、3年前にフィークルで会った時にはまだ子供という感じだったが、わずか3年くらいで、もう立派な青年だ。いちばん変わる時期だろう。
マーティン・ヘイズ命、というようにマーティンそっくりに弾く少年だった。しばらく話していると希花も起きてきた。
そして…やっぱり誰だか分かっていないようだ。「アンドレアだってさ」というと「えっ、こんなに小さかったのに」と言って驚いた様子で腰のところに目安を置いた。
そんなわけはないが、それくらいにまだ子供というイメージだったのだ。彼女にとっては弟と変わりないくらいの年齢の男の子で、そんな感じがするのだろう。
しばし一緒に弾いたり、話しをしたりして時間を過ごした。
そして、今晩の教会でのコンサートの計画を練るために、ぼくらはまたMacに向かった。いや、それだけではない。
Wi-Fiをつないで、フィークルの宿をキャンセルせねばならない。悪いなぁと思いながら、明日から2日間だけのキャンセルを申し出ると、なんの問題も無くオーケーの返事が出た。 去年と同じ、そう、ぼくらの横で、オーダーしたものと同じ食事を2匹の犬が美味しそうに食べていたところだ。
犬もきっと「美味しいなぁ、彼らにもこの味が、この喜びが分かるかなぁ」と僕等をみていたに違いない。
さて、コンサートの時間だ。驚いたことに結構人が入ってきた。教会はすごく大きいが、コンサートをやるスペースは80人くらいがいいところだろう。それでもすでに60人は超えているようだ。
みたことのある男が入ってきた。そのむかしアンドリューのバンドでギターを弾いていたKevin Hughだ。見るからに、とてもいい人、という感じのおじさんで(といっても、ぼくよりかなり年下だろう)よく色々なことを話したものだ。
お互い15年ぶりくらいなので、再会を楽しんだ。もっとも彼はこの近くに住んでいて、僕の名前をみて来てくれたようだった。
僕らがファーストセットを担当。25分ほどで、美しいエアーあり、日本民謡あり、典型的なトラッドありで、やんやの喝采を浴びた。
休憩の間は、クリスというこのコンサートの世話係の人がみんなを連れて教会の歴史や、展示物などを見せるミニツアーを行う。
そしていよいよセカンド・セット。メアリー・バーガンとリンゴの登場だ。ティン・ホイスルとバウロンという組み合わせ。もちろんここは常にノー・マイクロフォンだ。
リンゴのバウロンは素晴らしい。彼が言うようにバウロン奏者は常に影の功労者でなければならない。それが本当によくわかるプレイだ。
メアリーのティン・ホイスルもさすがなものだ。コンサートは大盛況のもとに、最後は僕等4人でクリーナのダンスのバックを演奏。そして、無事終了。
リンゴもメアリーも僕等の演奏を、超一流のミュージックであり、本物のトラッド・アイリッシュだ、と評価してくれた。
とてもいい一日だった。
2013年 アイルランドの旅 結局まだゴルウェイ
8月8日 晴れ
今日はOranmoreでMick Conneelyとセッションだ。この辺でも全アイルランドでも高名なフィドラーである彼も僕等とは初めて会う。
最初、希花に「君が曲を出してくれたらいい」と言っていた。初めて会う人がどれだけのレパートリーを持っているか分からないし、自分が出した曲についてこれなかったらつまらないからである。
Ringo,Mickそして僕と希花の4人だ。希花がキックオフをする。Mickが追う。Mickが始める。希花が追う。
そうこうしている間に「この二人は他の東洋人とは違う。アイルランド人よりもよく知っている」と、彼は矢継ぎ早に曲を出してくる。
そしてセッションが終わって、11時頃、「今からリンゴの家に寄るから少し俺のアイディアを希花に伝授したい」と申し出てきた。
チャンスだ。よっぽどの相手でない限りそんなことも無いはずだ。
1時間ほど、とても嬉しそうに希花にいろいろ教えてくれていた。こんなにいい経験はなかなか無いだろう。
有意義な一日だった。
8月9日 晴れ
今日はJohn Cartyのコンサートを見に行くのだ。その前に教会のすぐ隣にある、いつものパブTi CoiliでRingoとRonan(フィドラー)とのセッションがある。
John Cartyとも久しぶりに会う。そして彼のプレイはどこをとってもとことんJohn Cartyなのだ。
僕にとっても希花にとってもフェイバリット・プレイヤーの一人だ。
8月10日 晴れ
Ti CoiliでまたRonanとセッション。彼もいいフィドラーだ。
夜、フィークルへ様子を見に行く。いろんな人に挨拶だけして帰ることにした。すこし秋になったのだろうか。寒いと感じるようになってきた。
12時頃Ringoの家に戻ってきた。今日でゴルウェイとお別れだ。明日はフィークルに行ってそのままタラのアンドリューの家に泊まる。
そういえば、ゴルウェイでは昔の友達と会った。Kyleという奴で、サン・フランシスコで一緒にバンドをやっていた。彼はギターとブズーキとボーカルで、二人のフィドラーと、計4人で“Gnarly Pilgrims”というバンドだった。
もう15年ぶりにもなるだろうか。お互い驚きのあまり声も出なかったくらいだ。
なので、僕も日記に書き忘れていたが、衝撃的な再会だった。
こうして、音楽をやり続けていれば懐かしい友人たちと再会できる。日本でもアイルランドでも…。
2013年 アイルランドの旅 フィークル~タラ(最終回)
8月11日 晴れ
今日こそはフィークルに行かなくてはいけない。もともとフィークルも大きな目的の一つだったのだが、他で沢山の仕事を得たので、結局最終日だけになってしまった。でも今日はアンドリューと一緒だ。きっといい一日になるだろう。
昼からRingoがCoole Parkに連れて行ってくれた。クールパーク(日本語表記)は自然保護地区に指定されている、素晴らしく広い公園だ。
元はグレゴリー邸と呼ばれていた個人の持ちものだった。W.Bイエィツや、ショーのサインが刻まれている「署名の木」は有名だ。
しばし、深い緑に囲まれる。サーッと雨が降り、そしてまた止む。全てがゆっくりと大自然の営みを楽しんでいるように感じる。
僕らも、マフィンと紅茶で時を過ごした。
そしていざ、アンドリューの待つフィークルへ。セッションは3時からだが、どうせそんな時間には始まらない。
アンドリューを探す。ちょうど日本人の女の人が二人歩いていたので「すみません、アンドリュー・マクナマラ見ませんでしたか?」と尋ねたが、なに、この人、というような顔をされた。彼女達何しにここまできているんだろう。
でも考えたら知っている可能性はごくわずかだ。無理もない。
僕らが演奏するPeppersというパブは、人、人、そしてまた人でごった返している。もちろん、このフェスティバルの間じゅうフィークルに4つしかないパブは大賑わいだ。
この1週間でこの村はもっているのかもしれない。
去年まで、僕等はフィークルでのフェス参加をメインにしていた。ここに来れば長年の友人達とも会えるし、クレアーという、音楽の聖地の伝承者たちとも演奏ができる。
しかし、今年は毎日のように演奏をお金にすることができた。これは正直素晴らしい事だと思う。お金をもらって演奏する、ということがどういうことなのかを40年の間学んできたのかもしれない。
セッションに出て、みんなと一緒に知っている曲を弾き、知らない曲を学び、というのもこの音楽の基本だ。
そんななかでも多くの人達、バンドなどがアイリッシュ・ミュージックを世に広めるために、或いは商売としながら世界の様々な場所に出て行っている。
どちらにせよ、基本、この音楽は伝承であり、伝統をきちっと守らなくてはいけない。そのうえで独自の音を提供するのだ。
それを心がけていると今回のように“トラッド・ミュージシャン”としてあちこちから声がかかる可能性が生まれてくる。
僕らもこの国でそんな存在になりつつあるのかも知れない。
アンドリューも一時期より更に激しく(いい意味で)なってきたようだ。やりたくないことを頑なに拒んできて、その結果爆発しているのだろうか。彼のプレイはおもしろい。ブルース好きのアンドリューはB.B Kingが顔でギターを弾いているのと同じように顔でアコーディオンをかき鳴らす。
まるでいたずらっ子のように「見てろよ、いくぞ!」というような合図を送り、強烈な不協和音を破裂させる。
そんなアンドリューの横でRingoがひたすら正確にリズムを刻む。時としてあまりに同化していて聞こえず、はっとした瞬間に“ドスン”とお腹に響く。
まさにDavid Lindleyと一緒に演奏した時のWally Ingramもそうだった。決して出しゃばらず、的確に音楽のハートを掴むのだ。
Ringoは7時くらいにGalwayに戻った。今年は彼にだいぶお世話になった。できれば、彼とアンドリューを一緒に日本に呼んでやりたいが、いいギグを見つけてやれることができるだろうか。
セッションが終わってもアンドリューは暫くここで飲んでいくようだ。僕等は彼の家の鍵をもらい、赤嶺君と一緒にフィークルを出た。
真っ暗な田舎道をひたすら走ると、タラのメイン・ストリートに出る。赤嶺君とも再会を約束してアンドリューの家に入って、暫しソファーで落ち着いてまわりを見回した。すると、不思議な感覚におちいった。
まるで故郷に帰ってきたようだ。1991年、この家から出てきた男と知り合いになり、2000年、この家で2週間過ごしながら、2人でアイルランド・ツアーをし、それから事あるごとにここに寝泊まりしている。
僕のアイリッシュ・ミュージックのルーツがここにある。
そして、今晩、ここに泊まることを決めたのにはもうひとつの理由があるのだ。それは、フランのパブに行くことだ。(2012年 アイルランドの旅 8月7日 タラ 参照)
彼も、もう13年来の顔見知りだ。必ず顔を見に行くことにしている。85歳にもなるし、いつまでお店があるかもわからない。
10時半、正装したフランが店を開ける。僕等が入っていくと「やぁ、よく来たね」とギネスをご馳走してくれるが、僕等はそんなに強くないので、これが限度だしお金は払うから、と言っても受け取らない。
遠く日本から来て、必ず健康でいるかチェックしにくることが彼にも嬉しいのかもしれない。
あと10年くらい続けて欲しい。そしたら、立派なお医者さんになった希花さんが付いてくれるだろう。
2013年のアイルランドの旅はこれでおしまい。明日ダブリンに戻って、それから日本に帰るのだ。
Irish Music その27
今回はブルーグラス界でも比較的よく演奏されるIrish Tuneを集めてみた。その中には、70年代、80年代、ブルーグラスに夢中だった僕等が、IrishやScottishとは知らずに、或いは知っても、それはブルーグラスとして演奏していたものだ。
そんな曲が数多くある。
★ Cooley’s Reel
“初めてこの曲を聴いたのは、もしかするとCountry Cookingかも知れない。ギタリストのRuss Barenbergが弾いていた記憶がある。アイリッシュのセッションでは通常この後にWise Maidが来るが、ブルーグラスでは、それぞれが思い思いのソロを展開して1曲で終わるのが普通だ。まだ、若かった僕等はこれがJoe Cooleyの曲とは知らずにブルーグラス独特の通称“ドライブ”という感覚で弾いていた。70年代半ば頃ならきっと“スイング”感覚もあっただろう。後にアンドリュー・マクナマラと出会った時、彼は“Flow”という言葉を使っていた。“川の流れのように”というのだろうか。彼は美空ひばりを知っていたわけではない。
★ Blackberry Blossom
“これは初めてのナターシャー・セブンのLPで僕がソロのバンジョー曲として録音したものだ。アイリッシュにもブルーグラスにも同名曲があるが、これは全く違うメロディを持った曲だ。何故、この曲を選んだのかは理由がある。僕にとってはとても興味深い経験があるからだ。
それは、サン・フランシスコのプラウ・アンド・スターズという僕等のバンドのホーム・グラウンドでのセッションに於いてだった。いつものように僕とジャックとケビンがホストのセッションに、Fタイプのマンドリンを持った男が現れた。それだけで僕には、“あ、彼はブルーグラス畑の奴だな”という想像がつく。ジャックが尋ねた。「アイリッシュ・チューンは知ってるか?」すると彼が答えた。「よく知らないけどフェイクできる」彼は彼なりの解釈でアドリブできると言うのだ。ジャックはきっぱり言った。「NO FAKE!」
これはブルーグラスのセッションではない、と言う。少し険悪な雰囲気になったが彼は真面目な顔をしてしばらくおとなしくしていた。さすがに可哀そうに思ったのか、ジャックが「なんか知ってる曲があるか?」と聞くと「う~ん、そうだ。Blackberry Blossomなら知っている」と言って弾き出したのがブルーグラス・バージョン。始まったとたんにジャックが「ブラックベリー・ブロッサムはそれじゃない」とむりやり止めて、やにわにフルートを吹き始めた。明らかに違うメロディだ。僕も両方知っている。3回も4回も目をつぶって続けるジャック。終わってからあまりに可哀そうだったので「僕がギターを弾くからあんたブラックベリー・ブロッサム弾いたらいいよ」と言ったら、彼は喜んでブルーグラス・バージョンを弾いた。ジャックはもうバーの方でギネスを飲んでいた。「ごめんね。ここのセッションはきびしいんだ。メロディを正確に覚えないと参加できないことになっている。ブルーグラスのセッションみたいにフレンドリーではないんだ」彼はその1曲だけで、僕にお礼を言って帰っていった。僕にとっても想い出深い曲のひとつだ”
★ Pigtown Fling (Stoney Point)
“1962年 12月8日、カーネギー・ホールでのFoggy Mountain Boysのライブで“Fiddle&Banjo”というタイトルで演奏された曲だ。むかしはギターが入らず、ポーチなどでよくこんなかたちで演奏されたものだ、というような解説で、アイリッシュからするとBパートと言われる方から始まっている。アイリッシュ・ミュージックに関わるまで何も気にしていなかったのだが、(ましてや忘れていた曲だったが)ある時「あれ、もしかすると聴いたことがあるかもしれない」と思い始めてもう一度聴いてみると、明らかに同じ曲なのだ。ブルーグラス畑でもよく知られている曲らしい、と言うアイリッシュ関係者はいるが、それがFoggy Mountain Boysからなのか、それ以前なのかはわからない。どちらにせよ、ブルーグラス畑では多分タイトルはFiddle&Banjoになっているだろう。
★ Earl’s Chair
“時々ブルーグラス畑でも演奏されることがある、という程度の曲だがコード進行についていろいろ考えられるので面白い。この曲をセッションでやる時、先ず最初のコードを何にするか。Bm|BmかG|Gか。或いはBm|Gか。G|Bmといのはあまり良くないだろう。BパートではA/Bm|A/Bm|もありだがEm/Bm|Em/Bm|もありだろうし、Em/Bm |Em/D(F#bass)|もありだろうし Em/D(F#bass)|G6/Bm|A/G|D(F#bass)も面白いかもしれない。でも、そんな時考えるのがベースの進行だ。もし自分がこの曲でベースを弾いていたとしたら、いちばん気持ちよく進む音を選びたい。その上、あくまでリード楽器奏者のこだわりについても無視するわけにはいかない。究極のところ、いつも僕が思っているように、全ての曲のメロディを知らなければ、伴奏はただの迷惑になるだけだ。ブルーグラスは多分にジャズの要素も含まれているので、自分なりのリックも要求されるが、そこでもどれだけ基本のメロディを重視しているか、ということも見逃すことが出来ない。この、Earl’s Chairに於いてはブルーグラスの演奏家たちがどんなコード感覚の中でどんなリックを展開するか楽しみだ。そんな意味でこの曲を選んでみた。
★ Saint Anne’s Reel
“これはよくブルーグラスでも演奏されるフレンチ・カナディアン・チューンだ。アイリッシュのそれとは出だしが少し異なることが多い。カナディアン・フィドラーとして有名なJoseph Allardの1930年の録音を聴くと、ブルーグラスで弾かれるバージョンに近い。アイリッシュの曲よりスコティッシュやフレンチ・カナディアンの曲の方がリズムも含めてブルーグラスに近いような気がする。
★ Lord McDonald’s (Leather Breeches)
明らかにLeather Breechesという曲として、60年代からPete Seegerの演奏で聴いていたものだ。ブルーグラス・フィドル・チューンとしても、よく取り上げられる。単調な曲だが、深い趣がある。フレイリング・スタイルのバンジョーでもいいが、僕はよくPaddy Keenanと一緒に演奏した。こういう単調な曲では、どのパートを盛り上げて、どのパートでどういうテキスチャーで伴奏するか、メロディを聴きながらよく考える必要がある。伴奏者の真価が問われる曲のひとつかも知れない。
Irish Music その28(27の続き)
★ Miss MacLoeod’s
“これはひょっとすると、高校時代から知っていた曲だ。多分ニュー・ロスト・シティ・ランブラーズが演奏していたものを聴いたのだろう。フォークソングをやっていたあのころは、勿論キングストン・トリオや、ブラザース・フォア、ピーター・ポール・アンド・マリー、その他あらゆる情報にアンテナを張り、そのルーツなどを紹介する、ニュー・ポート・フォーク・フェスティバルの録音などにも興味を持った。ドック・ワトソン、クラレンス・アシュレィ、モリス・ブラザース、カーター・ファミリーなどに加え、ニュー・ロスト・シティ・ランブラーズは衝撃的だった。彼らのレパートリーに多く、アイリッシュやスコティッシュの曲が含まれていることはまだ知る術もない時代だった。Miss MacLeod’sはもともとスコティッシュ・チューンのようだ。そちらのバージョンは確かにアイリッシュで弾かれているものよりアメリカで聴かれるバージョンに近い。アンドリュー・マクナマラはジョー・クーリーから習ったバージョンを弾いている。1923年のTom Ennisの録音では既にアイリッシュでよく聴かれるバージョンになっている。こんなことを頭に入れながら弾くのと、ただ弾くのとでは全く違う、と僕は思う。伴奏者も知るべきことだ”
★ Rickett’s Hornpipe
“Bill Keithのバンジョー演奏で70年代からよく知っていた。別名Manchester Hornpipeというもので、ほとんどアメリカン・チューンといってもよさそうだ。この手の曲は沢山ある。Fisher’s,Sailor’s,Soldier’s Joy,などアメリカで創られたものか、もともとあったものかを調べるのはおもしろい。尚、これらの曲をアイリッシュ・ミュージシャンが演奏することはまず無い。多分嫌っているのだろう。イギリス方面の曲だから、ともいわれているし、聴くに堪えないつまらないものだ、と酷評する人もいるくらいだ。そこら辺が特にアイリッシュ・ミュージシャンからすると、ブルーグラスなんてやっていられない、という話しにつながってくるのだろう。30年ほどもブルーグラスに関わってきてアイリッシュに移行した僕にとっては分からないことでもないが、スタンレー・ブラザースなんかを聴くと、アイリッシュと同じように胸が熱くなることも事実だ。
★ Mason’s Apron or Devil’s Dream
“驚いたことにDevil’s DreamはHornpipeとしても記載されている。勿論「Reelだと思った」という意見もあるのは、普通ブルーグラスではかなり速く弾かれることが多いからだろう。一方Mason’s Apronは2パートだけの場合もあれば、7つものパートを演奏する場合もある。ほとんどバリエーションとも言えるが…。とりあえず最初の2パートはほとんど一緒だと言える。ブルーグラスでは2パートだけで、それぞれが自分のソロが回ってきた時点でバリエーションを展開する。どちらにせよ、出どころはスコットランドだろうか。
瀬戸内寂聴さんと会う
突然ですが、9月15日、寂庵に於ける寂聴さんの法話を聴いて、そのあと僕と希花とで少しだけ演奏させていただきました。ぼくら二人合わせた年齢よりも多い、という寂聴さん。声の張りもさることながら、お話も面白く、お元気そうで驚きました。
衝撃の出会いでした。嬉しかったので、まーるい頭をなでなでさせていただきました。有難うございました。
Irish Music その29
John Brosnan’s/The Crock of Gold (Reel)
★ John Brosnan’s
“Co.Kerry 出身のアコーディオン奏者John Brosnanが1974年に書いた曲。コーマック・ベグリーが彼のアパートのキッチンで練習していた時に曲名を尋ねた。BパートがちょっとCongressのAパートに似ているが、さほどにこんがらからないのはBパートがお互いにそっくり、というわけではないからだろう”
★ The Crock of Gold
“1920年にCo.Galwayで生まれたフルート、パイプ奏者Vincent Broderickによって書かれた曲とされている。シングル・リールという人もいるが、ダブルで演奏する人も多い”
Up Sligo/The Golden Stud (Jig/Reel)
★ Up Sligo
“80年代、よくStockton’s Wingで聴いていたセットだ。驚いたことにCape Breton
のフィドラーMike McDougallという人の書いたIngonishという曲らしい。Michael ColemanやKevin Burkeの演奏でもよく知られている。
★ Golden Stud
“Maurice Lennon作のスロー・リール。Paul Rouchが書いたという人もあれば、同じグループのKieran Hanrahanが書いた、という人もいる。いずれにせよ、シンプルで美しいメロディを持った曲だ。僕等はこの後、Morning Dew/Jenny’s Chickenをひっ付けて最近レパートリーに取り入れている”
The Kylebrack Rambler/Paddy Fahey’s#1 (Reel)
★ The Kylebrack Rambler
“Finber Dwyer の作になるとても魅力的な曲だ。かなり前ティプシー・ハウスのフィドラーPaulがよくやっていたのを覚えていた”
★ Paddy Fahey’s#1
“数多い彼の作品のなかでも、最も有名な曲かもしれない。前の曲との繋がりはスムーズ過ぎて変わったことが分からないかもしれないが、テンポが絶妙に合う”